労務の採用が難しい理由と、解決策としての優秀な人材の見つけ方
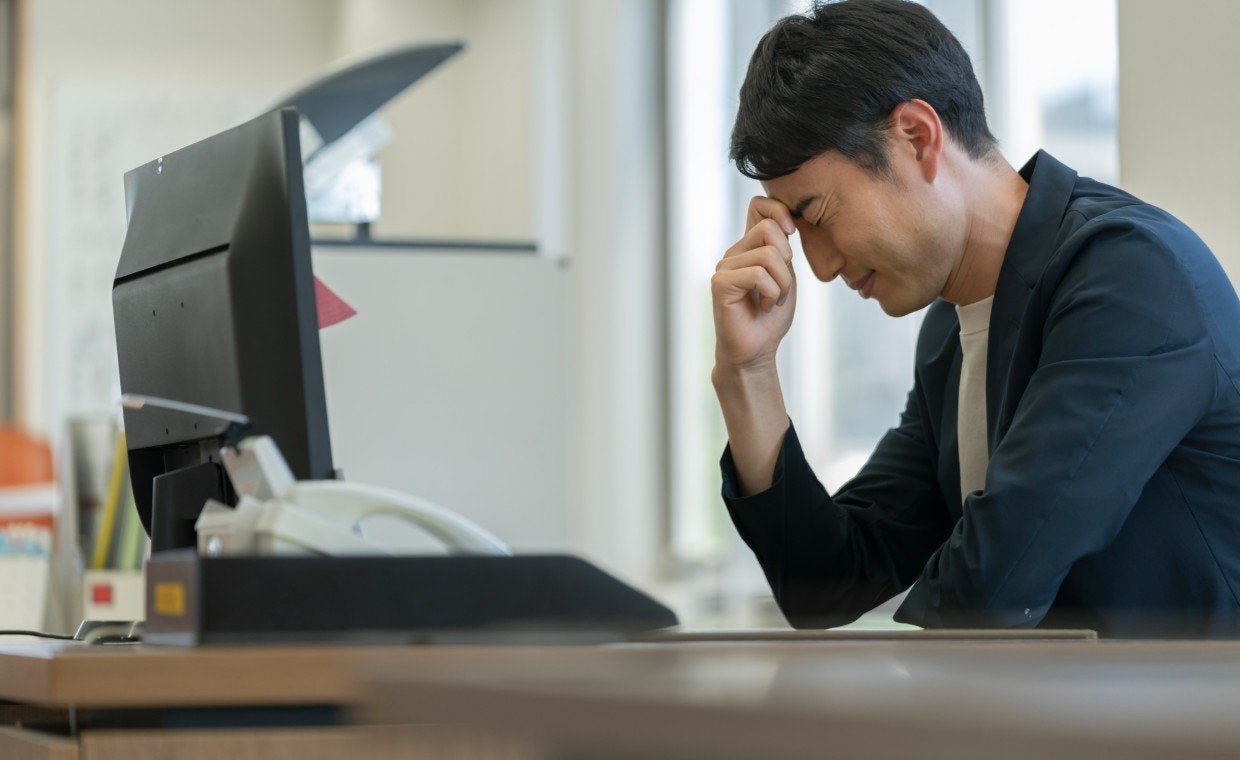
終わらない!

- リリースからわずか2年で
累計1000社以上が採用したサービス - 厳選された優秀なアシスタントが支援
- あらゆる労務業務を専門チームが代行
- 人手不足を解決し、安定した労務体制へ

目次
労務の仕事内容とは?
「労務」と聞いて、具体的にどのような業務を思い浮かべるでしょうか。
多くの人が「給料計算」や「入社手続き」といったイメージを持っているかもしれません。
しかし、労務の仕事はそれだけにとどまらず、企業の健全な運営を支える多岐にわたる業務を担っています。
まず、日々の業務としては、社員の勤怠管理や給与計算、入社・退職手続き、社会保険や雇用保険の手続きなどが挙げられます。
これらの業務は、法律に基づき正確かつ迅速に行う必要があり、企業のコンプライアンスを維持する上で欠かせません。
特に、毎月の給与計算は、社員の生活に直結する重要な業務であり、ミスが許されません。
また、労務の仕事には、社員の働きやすい環境を整備する役割もあります。
例えば、就業規則や各種規定の作成・改定、人事評価制度の運用、ハラスメント対策やメンタルヘルスケアなど、社員が安心して働ける職場づくりに貢献します。
これらの業務は、企業の生産性向上や離職率低下にもつながるため、非常に重要な役割を担っています。
さらに、労務は法律改正への対応も重要な仕事です。
労働基準法、労働契約法、男女雇用機会均等法など、労働関連法規は頻繁に改正されます。
これらの情報を常にキャッチアップし、社内の規定や運用を適切に変更していく必要があります。
企業の労務担当者は、専門的な知識を持ち、社員と経営陣の双方にとって最適な環境を構築する、いわば「縁の下の力持ち」のような存在なのです。
労務の採用が難しい理由は?
企業の経営において不可欠な存在であるにもかかわらず、なぜ労務担当者の採用は難しいと言われているのでしょうか。
そこにはいくつかの複合的な要因が存在します。
第一に、労務の業務範囲が広く、専門性が高いことが挙げられます。
前述の通り、給与計算や社会保険手続きといった実務から、就業規則の策定や労働問題への対応といったコンサルティング的な業務まで、求められるスキルは多岐にわたります。
さらに、法律や制度の知識は常にアップデートする必要があり、実務経験が豊富な人材は限られています。
そのため、即戦力となる人材を見つけるのは至難の業です。
第二に、労務の業務は企業の機密情報や個人情報を扱うため、高い倫理観と守秘義務が求められます。
給与情報や評価情報など、社員のプライバシーに深く関わる情報を扱うため、信頼できる人材でなければ任せることができません。
しかし、求人広告や面接だけで、その人物の倫理観や信頼性を深く見抜くことは難しいものです。
第三に、労務担当者のキャリアパスが明確でないことも、採用を難しくする一因です。
労務の仕事は、会社の事業や売上に直接的に貢献するものではないため、評価されにくく、キャリアアップの道筋が見えにくい場合があります。
そのため、優秀な人材が労務職を敬遠し、よりキャリアパスが描きやすい職種に流れてしまう傾向があります。
特に、採用に携わる人材は、自身の経験からキャリアの展望を描きやすいため、労務という職種に対するイメージが定着しづらい側面があります。
第四に、そもそも労務という職種自体の認知度が低いことも挙げられます。
人事や経理といった職種に比べて、労務の仕事内容を具体的に理解している求職者は多くありません。
そのため、求人を出しても応募が集まりにくかったり、ミスマッチが起こりやすかったりします。
このように、労務という職種の特性上、採用は非常に難しい状況にあると言えるのです。
そもそも労務に向いている人はどんな人?
労務の仕事は、高い専門性と倫理観が求められる一方、人とのコミュニケーション能力も重要です。
では、具体的にどのような人が労務に向いているのでしょうか。
いくつかの特徴を挙げてみましょう。
まず、正確性と几帳面さは必須です。
給与計算や社会保険手続きなど、数字や書類を正確に扱う業務が多いため、細かな作業を丁寧にこなせる人が向いています。
少しのミスが大きなトラブルにつながることもあるため、慎重に物事を進められる人が適任です。
次に、論理的な思考力と問題解決能力です。
労働関連法規に基づき、様々なケースに対応していく必要があるため、論理的に物事を考え、適切な解決策を導き出せる力が求められます。
法律の解釈や複雑な手続きを理解し、それを実務に落とし込む能力も重要です。
また、コミュニケーション能力も欠かせません。
労務担当者は、社員からの様々な相談に対応したり、経営陣に制度の改善提案を行ったりと、多くの人と関わります。
相手の気持ちに寄り添い、円滑な人間関係を築ける人が、労務の仕事で活躍できるでしょう。
さらに、変化に対応できる柔軟性も重要です。
労働関連法規や社会情勢は常に変化しており、それに伴い業務内容や制度も変更していく必要があります。
新しい知識を積極的に学び、変化を柔軟に受け入れられる人は、労務担当者として長く活躍できるでしょう。
最後に、秘匿性と誠実さです。
個人情報や機密情報を扱う業務が多いため、高い倫理観を持ち、守秘義務を遵守できる人が求められます。
社員からの信頼を得るためには、誠実な対応が不可欠です。
労務担当を採用できない場合の影響は?
労務担当者の採用が難しい状況が続くと、企業は様々な悪影響を被ることになります。
第一に、法律違反のリスクが高まります。
労働基準法や社会保険関連法規の改正に対応できず、知らないうちに違法な状態になっている可能性があります。
例えば、残業代の未払い問題や、社会保険の未加入問題などが発生すると、企業は多額の追徴金や罰則を科されるだけでなく、企業の社会的信用も失墜してしまいます。
第二に、社員のモチベーション低下や離職率の増加につながります。
給与計算や勤怠管理にミスが多発したり、社員からの相談に適切に対応できなかったりすると、社員は会社への不信感を募らせてしまいます。
その結果、働きがいを感じられなくなり、優秀な人材から離れていってしまうリスクが高まります。
特に、新しい採用活動で入社したばかりの社員が、このような事態に直面すると、早期離職につながりやすくなります。
第三に、管理部門の負担増です。
労務の専門知識を持った担当者がいない場合、経営者や他部署の社員がその業務を兼務することになります。
しかし、専門外の業務を片手間にこなすには限界があり、業務効率の低下や他業務の停滞を招きます。
結果として、組織全体の生産性が低下してしまうのです。
第四に、労使トラブルのリスクです。
労務の専門家がいないと、労働問題が発生した際に適切な対応ができず、トラブルが長期化したり、訴訟に発展したりする可能性があります。
このようなトラブルは、企業のブランドイメージを著しく損ない、優秀な人材の採用にも悪影響を及ぼします。
労務担当を採用する際に注意すべきこと
労務担当者の採用を成功させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
難しい採用活動を乗り越え、自社に最適な人材を見つけるために、以下の点に注意して求人活動を行いましょう。
まず、自社の課題を明確にすることです。
労務担当者に何を求めているのか、具体的にどのような業務を任せたいのかを明確にすることで、求める人物像がはっきりします。
例えば、「給与計算を正確に行ってほしい」のか、「就業規則を整備してほしい」のか、それとも「社員からの相談窓口になってほしい」のかによって、適任の人物は異なります。
次に、専門的なスキルと経験を正しく見極めることです。
履歴書や職務経歴書だけでは、その人の実力を判断するのは困難です。
面接では、具体的な業務経験や、過去にどのような課題を解決してきたかなどを詳しく尋ねることで、その人のスキルや能力を把握することができます。
また、社会保険労務士などの資格を持っているかどうか、最新の法改正についてどの程度知識を持っているかなども確認しましょう。
さらに、自社の企業文化や価値観に合うかを重視することです。
労務は、社員と密接に関わるため、社内の雰囲気に馴染めるか、コミュニケーションを円滑に取れるかは非常に重要です。
面接では、一方的に質問するだけでなく、候補者の人柄や考え方を知るための対話の時間を設けるようにしましょう。
そして、採用後の育成計画を立てることも重要です。
たとえ経験者であっても、入社後すぐにすべての業務を完璧にこなせるわけではありません。
OJT(On-the-Job Training)の仕組みを整えたり、外部研修の機会を提供したりすることで、社員の成長を支援する体制を整えましょう。
これにより、優秀な人材の定着率を高めることができます。
優秀な労務担当を採用するために記載すべき求人情報
求人情報を工夫することも、優秀な労務担当者を採用するための重要なポイントです。
単に業務内容を羅列するだけでなく、求職者の心に響くような情報を盛り込むことで、応募数の増加や質の向上が期待できます。
まず、仕事内容を具体的に記載しましょう。
単に「労務事務」と書くのではなく、「社員30名の給与計算(弥生給与を使用)」や「入社・退職手続き(SmartHRを使用)」など、具体的な業務内容や使用するツール名を明記することで、求職者は入社後の仕事内容を具体的にイメージできます。
また、「就業規則の見直し」や「人事評価制度の運用サポート」といった、より高度な業務をアピールすることで、キャリアアップを志向する人材にも魅力を感じてもらいやすくなります。
次に、会社の魅力や働くメリットをアピールしましょう。
「残業が月平均10時間未満」や「リモートワーク可」といった働き方の柔軟性や、「資格取得支援制度あり」といった自己成長をサポートする制度を記載することで、求職者の関心を惹くことができます。
また、労務の仕事が会社にどのような影響を与えているのか、その重要性ややりがいを伝えることも有効です。
さらに、求める人物像を明確に記載しましょう。
「労務経験者」というだけでなく、「主体的に業務改善に取り組める方」や「コミュニケーション能力の高い方」といった、スキルだけでなく人柄やマインドを伝えることで、自社にマッチした人材からの応募を促すことができます。
最後に、給与や待遇を具体的に記載しましょう。
給与は「月給〇〇万円~〇〇万円」のように幅を持たせるだけでなく、モデル年収の例を挙げるなど、より具体的に提示することで、求職者の安心感につながります。
また、福利厚生や手当など、給与以外の待遇も漏れなく記載することが重要です。
これらの情報を網羅的に記載することで、採用のミスマッチを防ぎ、本当に自社に合った人材を見つけることができるのです。
労務に限らず人を雇うのは難しい
これまでに述べてきたように、労務担当者の採用は難しい課題です。
しかし、この課題は労務に限ったことではありません。
人手不足が深刻化する現代において、どの職種においても優秀な人材を採用するのは難しいのが現状です。
採用活動には、求人広告費や人材紹介手数料、面接にかかる時間など、多大なコストがかかります。
また、せっかく採用しても、ミスマッチや早期離職が発生すれば、再び採用活動を始めなければなりません。
これは、企業にとって大きな負担となります。
特に、中小企業やベンチャー企業では、人事や労務を専門とする担当者がいないことが多く、経営者や他部署の社員が兼務しているケースが少なくありません。
本業の傍らで採用活動を行うことは、時間的にも精神的にも大きな負担となり、企業の成長を阻害する要因にもなりかねません。
このような状況下で、いかにして企業の生産性を維持・向上させていくかが、多くの企業にとって喫緊の課題となっています。
採用が難しいからといって、必要な業務を放置することはできません。
かといって、時間やコストをかけても、必ずしも希望する人材が見つかるとは限らないのが現実です。
そこで注目されているのが、外部の専門家に業務を委託するアウトソーシングという選択肢です。
採用という難しい課題を抱える中で、即戦力となるプロの力を借りることは、企業が成長するための有効な手段となり得ます。
即効性のあるプロ『Chatwork 労務アシスタント』にお任せ!
「労務の採用が難しい」「採用に時間やコストをかけられない」とお悩みの企業様におすすめしたいのが、Chatwork 労務アシスタントです。
Chatwork 労務アシスタントは、労務の専門家がお客様の労務業務を代行するサービスです。
最短5営業日で採用活動にかかる時間とコストを大幅削減が期待できます。
また、上場企業直雇用の専門的な知識を持つプロが、給与計算や社会保険手続きといった業務を滞りなく進めます。
これにより、業務の属人化を防ぎ、経営者はノンコア業務を手放して本業に集中することができます。
また、Chatwork 労務アシスタントは、最新の労働関連法規に対応した専門家が業務を行うため、コンプライアンス遵守の面でも安心です。
労務の専門家を新たに採用することなく、高度な専門知識を自社に取り入れることができます。
さらにチャットツールを通じて気軽にコミュニケーションを取れるため、仕事内容に関する質問や相談にも迅速に対応できます。
これにより、社員からの問い合わせにもスムーズに対応でき、社員の満足度向上にもつながります。
採用が難しい時代だからこそ、外部のプロの力を借りて、業務効率化と経営基盤の強化を図ることが重要です。
採用に難しいと感じている企業様は、ぜひ一度ご相談ください。





