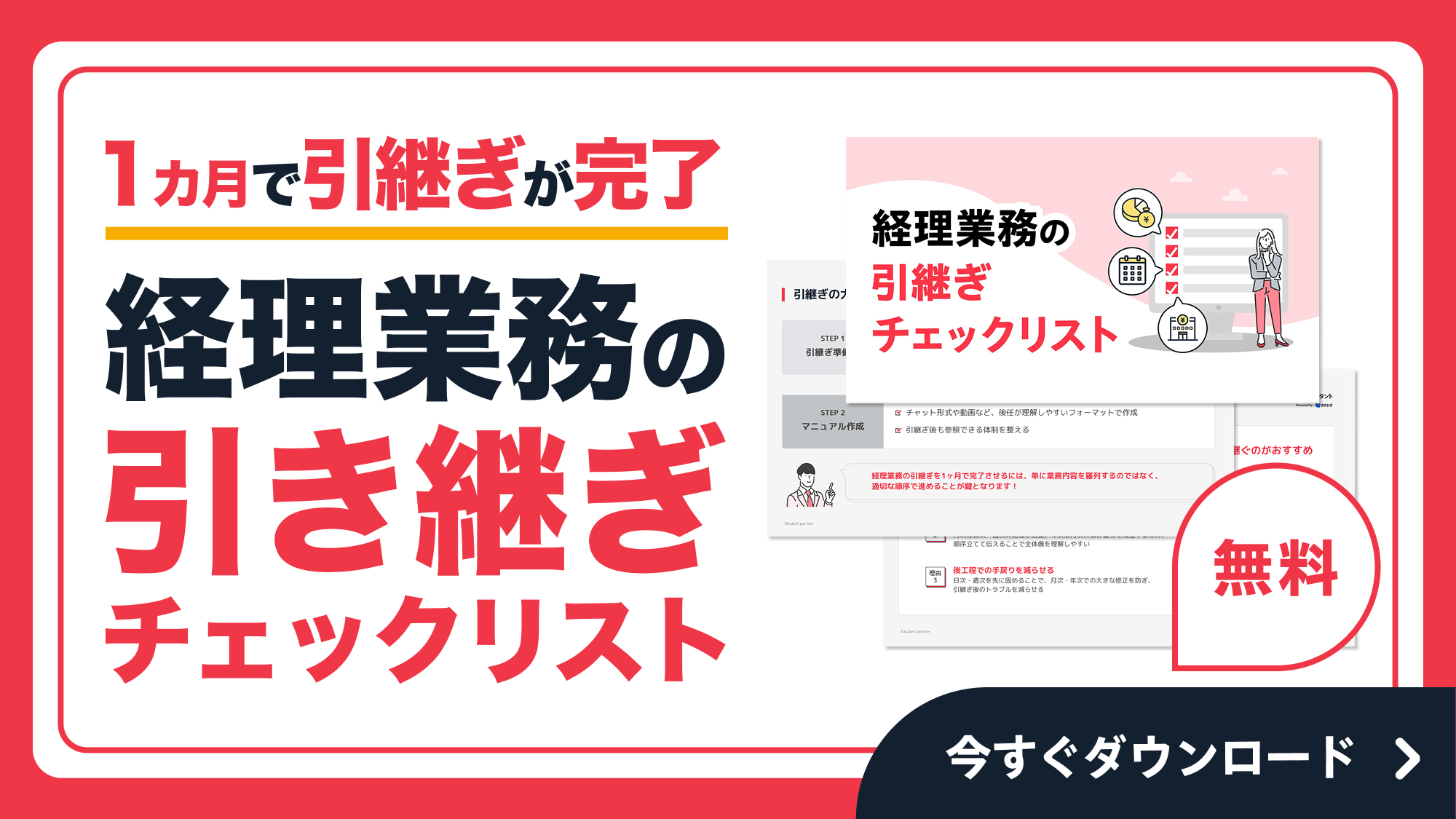確定申告の代行は税理士に依頼すべき?料金相場や依頼先の選び方まで徹底解説【2025年最新】

終わらない!

- リリースからわずか2年で
累計1000社以上が採用したサービス - 厳選された優秀なアシスタントが支援
- あらゆる経理業務を専門チームが代行
- 人手不足を解決し、安定した経理体制へ

目次
毎年、確定申告の時期が近づくと、憂鬱な気分になる個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
「日々の業務が忙しくて、経理作業が後回しになっている」。
「大量のレシートや領収書の整理を考えるだけで疲れてしまう」。
「そもそも、このやり方で本当に合っているのか不安だ」。
このような悩みは、多くの事業者が抱える共通の課題です。
確定申告は、国民の義務であると同時に、専門的な知識が求められる複雑な作業でもあります。
もし、あなたがこうした悩みを抱え、貴重な時間と労力を確定申告に費やしているのであれば、「専門家への代行依頼」を検討してみてはいかがでしょうか。
この記事では、確定申告の代行、特に税理士への依頼に焦点を当て、そのメリット・デメリットから気になる料金相場、依頼する際の注意点まで、あらゆる角度から徹底的に解説します。
また、確定申告の準備を効率化する便利なサービスもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
確定申告の代行を依頼するメリット
確定申告の代行を専門家、特に税理士に依頼することには、単に「面倒な作業から解放される」以上の、事業を運営する上で見逃せない多くのメリットが存在します。
ここでは、その代表的なメリットを5つご紹介します。
メリット1:本業に集中できる時間が増える
最大のメリットは、何と言っても「時間」の創出です。
個人事業主にとって、時間は最も貴重な経営資源の一つです。
領収書の整理、帳簿付け、申告書の作成といった一連の作業には、慣れていないと数十時間、場合によってはそれ以上の時間がかかります。
この時間を、専門家である税理士に代行してもらうことで、商品開発や営業活動、顧客対応といった、事業の売上に直結する「コア業務」に集中できる時間が増えます。
専門外の作業に費やしていた時間を事業成長のための時間に変えられることは、大きなメリットといえます。
メリット2:正確な申告で税務リスクを回避できる
確定申告の内容に誤りがあると、後日、税務署から指摘を受け、「過少申告加算税」や「延滞税」といったペナルティ(追徴課税)が課されるリスクがあります。
税法のルールは非常に複雑で、毎年のように改正も行われるため、知らず知らずのうちに間違いを犯してしまう可能性は誰にでもあります。
その点、税務のプロフェッショナルである税理士に依頼すれば、最新の法令に則って正確な申告書を作成してもらえます。
これにより、計算ミスや計上漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、将来的な税務リスクから事業を守ることができます。
メリット3:専門的な節税アドバイスを受けられる
税理士は、単に申告書を作成するだけの代行業者ではありません。
事業内容や財務状況を深く理解した上で、法律の範囲内で最大限の節税が可能になるよう、専門的な視点からアドバイスをしてくれます。
たとえば、経費にできる範囲の判断や、青色申告特別控除、小規模企業共済、iDeCo(個人型確定拠出年金)といった各種控除の活用法など、自分だけでは気づかなかったような節税策を提案してもらえる可能性があります。
適切な節税は、手元に残る資金を増やし、事業の成長を後押しする重要な要素です。
メリット4:青色申告(65万円控除)のハードルが下がる
個人事業主が受けられる大きな節税メリットの一つに「青色申告特別控除」があります。
特に、最大65万円の控除を受けるためには、「複式簿記」での記帳と、「電子申告(e-Tax)」または「電子帳簿保存」が必要です。
複式簿記は専門的な知識が必要なため、独学でマスターするのはハードルが高いと感じる方も少なくありません。
税理士に記帳代行から依頼すれば、この複雑な要件をクリアし、65万円控除の恩恵を確実に受けることができます。
税理士に支払う代行料金を考慮しても、控除額の大きさを考えれば十分にお釣りがくるケースも多いでしょう。
メリット5:税務調査の際に代理人になってもらえる
万が一、税務調査の対象となった場合、多くの人はどう対応して良いか分からず、大きな不安を感じるはずです。
顧問契約を結んでいる税理士がいれば、調査の事前準備から当日の立ち会い、税務署との交渉まで、代理人として専門的な対応を一任できます。
税務のプロが間に立つことで、不利な状況に陥るのを防ぎ、心理的にも安心して調査に臨むことができます。
確定申告の代行を依頼するデメリット
多くのメリットがある一方で、確定申告の代行依頼にはいくつかのデメリットや注意点も存在します。
良い面と悪い面の両方を理解した上で、慎重に判断することが大切です。
デメリット1:費用(コスト)がかかる
当然のことながら、専門家に依頼するには一定の料金が必要です。
事業の売上規模や依頼する業務範囲によって費用は変動しますが、個人事業主の場合、数万円から十数万円の出費となります。
事業を始めたばかりでまだ売上が少ない方や、少しでもコストを抑えたい方にとっては、この費用が負担に感じられるかもしれません。
ただし、前述のメリット(節税効果や時間の創出)と比較して、費用対効果を総合的に判断することが重要です。
支払う料金以上の価値があると感じられるかどうかが、1つの判断基準になります。
デメリット2:経理や税務の知識が身につきにくい
確定申告に関する作業をすべて税理士に「丸投げ」してしまうと、自分自身で経理や税務について学ぶ機会が失われてしまいます。
事業主として、自社の財務状況を正しく把握し、お金の流れを理解しておくことは非常に重要です。
「税金のことはよく分からないから、全部お任せ」という姿勢でいると、経営判断に必要な数字の感覚が養われない可能性があります。
良い税理士は、作成した決算書の内容を分かりやすく説明してくれます。
依頼する側も、積極的に質問するなどして、自社の経営状況を理解しようと努める姿勢が大切です。
デメリット3:コミュニケーションの手間が発生する
税理士に代行を依頼するということは、他人と連携して仕事を進めるということです。
必要書類の受け渡しや、事業内容の説明、経費に関する質問への回答など、ある程度のコミュニケーションは必ず発生します。
相性の悪い税理士を選んでしまうと、このやり取りがストレスになったり、意思疎通がうまくいかずにスムーズに申告が進まなかったりする可能性もあります。
信頼でき、気軽に相談できる相性の良い税理士を見つけられるかどうかが、重要なポイントになります。
確定申告代行の依頼費用相場
確定申告の代行を検討する上で、最も気になるのが「いくらかかるのか」という料金の問題でしょう。
費用相場は、事業の規模や依頼する業務範囲によって大きく異なります。
ここでは、個人事業主が税理士に確定申告代行を依頼する場合の一般的な料金相場を解説します。
料金体系の種類
税理士への依頼方法は、主に2つの契約形態があります。
1. スポット契約(単発契約)
確定申告の時期だけ、申告書の作成と提出を単発で依頼する契約です。
日々の記帳(帳簿付け)は自分で行い、そのデータをもとに税理士が決算と申告作業のみを行います。
年間のコストを抑えたい方や、まずは一度税理士に依頼してみたいという方に適しています。
2. 顧問契約(継続契約)
毎月一定の顧問料を支払い、年間を通じて経理や税務に関するサポートを受ける契約です。
日々の記帳代行から、決算、確定申告、年末調整、さらには経営相談まで、幅広いサービスが含まれるのが一般的です。
税務に関するあらゆることを継続的に相談したい、経営のパートナーが欲しいという方に向いています。
料金が決まる要因
代行料金は、主に以下の要素の組み合わせで決まります。
売上規模:売上が大きいほど、取引の量が増えて作業が複雑になるため、料金は高くなります。
記帳代行の有無:日々の帳簿付けを自分で行うか、税理士に任せる(記帳代行)かで料金が大きく変わります。
記帳代行を依頼する場合、月々の顧問料や追加料金が発生します。
依頼内容の複雑さ:消費税の申告が必要な課税事業者であったり、不動産所得や譲渡所得など複数の所得があったりすると、料金は加算されます。
【個人事業主】依頼内容別の費用相場
ケース1:記帳は自分で行い、確定申告のみ依頼(スポット契約)
クラウド会計ソフトなどを使って自分で帳簿付けを行い、最終的なチェックと申告作業だけを税理士に依頼するパターンです。
| 年間売上高 | 料金相場 |
|---|---|
| ~500万円 | 5万円 ~ 10万円 |
| 500万円 ~ 1,000万円 | 7万円 ~ 15万円 |
| 1,000万円 ~ 3,000万円 | 10万円 ~ 20万円 |
ケース2:記帳代行+確定申告を依頼(顧問契約)
領収書や請求書を渡して、日々の記帳から確定申告まですべてを税理士に任せるパターンです。
料金は「月額顧問料+決算・申告料」で構成されるのが一般的です。
| 年間売上高 | 月額顧問料 | 決算・申告料 | 年間合計の相場 |
|---|---|---|---|
| ~1,000万円 | 1万円 ~ 2.5万円 | 月額顧問料の4~6ヶ月分 | 15万円 ~ 40万円 |
| 1,000万円 ~ 3,000万円 | 2万円 ~ 4万円 | 月額顧問料の4~6ヶ月分 | 30万円 ~ 60万円 |
※上記はあくまで一般的な相場です。
税理士事務所の方針や提供するサービス内容によって料金は異なりますので、必ず複数の事務所から見積もりを取って比較検討することをおすすめします。
確定申告の代行を依頼する際の注意点
専門家に確定申告の代行を依頼する際には、いくつか知っておくべき注意点があります。
トラブルを避け、スムーズに申告を終えるために、以下のポイントを必ず押さえておきましょう。
注意点1:「丸投げ」はできないと心得る
「代行を依頼したから、自分は何もしなくていい」というのは大きな誤解です。
税理士は、提供された資料(売上の記録、領収書、請求書など)をもとに申告書を作成します。
そのため、日々の取引を記録し、必要な書類をきちんと整理して保管しておくのは、事業主自身の責任です。
資料が不十分だったり、内容に不明な点があったりすれば、税理士から質問が来ますし、正確な申告書は作れません。
あくまで「専門的な作業を代わってもらう」というスタンスで、依頼者としての協力は惜しまないようにしましょう。
注意点2:税理士資格を持たない代行業者に注意する
確定申告書の作成や税務相談、税務代理(税務署とのやり取り)は、法律によって「税理士」の資格を持つ者だけが行えると定められています(税理士の独占業務)。
しかし、中には税理士資格を持たないにもかかわらず、「格安」をうたって確定申告の代行を請け負う無資格業者も存在します。
こうした業者に依頼してしまうと、申告内容に誤りがあった場合に責任を取ってもらえなかったり、最新の税法に対応できていなかったりするリスクが非常に高くなります。
依頼先が税理士資格を持っているか、税理士会の名簿に登録されているかなどを確認してから依頼することが重要です。
注意点3:依頼はできるだけ早めに行う
確定申告の期限(通常は3月15日)が迫る1月下旬から3月にかけては、税理士事務所も繁忙期を迎えます。
期限ギリギリになってから依頼しても、すでに受付を締め切っていて断られてしまったり、通常よりも高い「特急料金」を請求されたりする可能性があります。
また、短い期間では税理士が事業内容を十分に把握できず、最適な節税提案を受けられないかもしれません。
可能であれば年が明けたらすぐに、遅くとも1月中には相談を始めるのが良いでしょう。
確定申告の代行依頼に必要な書類
税理士に確定申告の代行をスムーズに進めてもらうためには、事前の書類準備が欠かせません。
具体的にどのような書類が必要なのか、以下で紹介します
本人確認・基本情報に関する書類
マイナンバーカード(または通知カード+運転免許証などの本人確認書類):申告書にマイナンバーの記載が必須のため必要です。
前年分の確定申告書の控え:前年の申告状況を確認し、引き継ぐ情報(減価償却資産など)を把握するために重要です。
事業内容がわかる資料:どのような事業を行っているのかを税理士が理解するための資料です(ウェブサイトのURLやパンフレットなど)。
収入(売上)に関する書類
1年間(1月1日~12月31日)の売上金額がわかるものすべてが必要です。
売上台帳・総勘定元帳:会計ソフトで作成している場合はそのデータ。
請求書の控え:発行した請求書はすべて保管しておきましょう。
支払調書:取引先から源泉徴収されている場合に送られてくる書類です。
事業用の預金通帳:売上の入金記録を確認するために必要です。
経費に関する書類
事業を行うために支払った費用を証明する書類です。
これらが経費として認められることで、所得金額を圧縮し、節税につながります。
領収書・レシート:日付、金額、支払先、内容がわかるように整理しておきましょう。
請求書:仕入れや外注費などの請求書です。
クレジットカードの利用明細:事業用のカード明細は経費の証明になります。
事務所の賃貸契約書や光熱費の明細:家賃や水道光熱費を経費にする場合に必要です。
借入金の返済予定表:事業資金の借入がある場合、利息部分が経費になります。
各種控除に関する書類
所得から差し引くことができる「所得控除」を受けるために必要な証明書です。
控除が多いほど、納める税金は少なくなります。
国民健康保険料・国民年金保険料の控除証明書:支払った全額が社会保険料控除の対象になります。
生命保険料・地震保険料の控除証明書:保険会社から秋頃に郵送されてきます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金払込証明書:掛金の全額が控除対象です。
医療費の領収書・明細書:年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合に医療費控除を受けられます。
寄附金の受領証:ふるさと納税などが該当します。
確定申告の代行を依頼する際の流れ
初めて確定申告の代行を依頼する場合、どのような手順で進むのか不安に思うかもしれません。
ここでは、依頼から申告完了までの一般的な流れを、6つのステップでご紹介します。
ステップ1:依頼先の選定・問い合わせ
まずは、どの税理士に依頼するかを探すところから始まります。
インターネットで検索したり、知人や取引先から紹介してもらったりする方法があります。
気になる税理士事務所が見つかったら、ウェブサイトの問い合わせフォームや電話で連絡を取り、確定申告の代行を依頼したい旨を伝えます。
このとき、事業内容や年間の売上見込みを伝えると、その後の話がスムーズに進みます。
ステップ2:面談・見積もりの提示
次に、税理士との面談を行います。
最近ではオンラインでの面談も増えています。
この面談で、事業の詳細や依頼したい業務範囲(記帳代行は必要かなど)を伝え、税理士からの質問に答えます。
ヒアリング内容をもとに、税理士からサービス内容と料金の見積もりが提示されます。
複数の事務所と面談し、見積もりを比較検討するのがおすすめです。
ステップ3:契約の締結
サービス内容と料金に納得できたら、契約を締結します。
契約書には、依頼する業務の範囲や料金、双方の責任などが明記されていますので、必ず内容をよく確認してから署名・捺印しましょう。
不明な点があれば、契約前に必ず質問して解消しておくことが大切です。
ステップ4:必要書類の準備と提出
契約が完了したら、申告に必要な書類を税理士に渡します。
書類準備は、依頼者が行う最も重要な作業となります。
前述の「確定申告の代行依頼に必要な書類」を参考に、漏れなく準備しましょう。
領収書や請求書などを紙のまま渡すのか、スキャンしてデータで渡すのかなど、提出方法は税理士の指示に従ってください。
ステップ5:税理士による申告書の作成と内容確認
提出された資料をもとに、税理士が会計ソフトへの入力、決算書の作成、確定申告書の作成を行います。
作業の途中で、取引内容について税理士から質問が来ることがありますので、迅速に回答しましょう。
申告書が完成したら、最終的な内容について税理士から説明を受け、納税額などを確認します。
内容に問題がなければ、税理士が代理で税務署へ申告書を電子申告(e-Tax)で提出します。
ステップ6:納税と控えの受け取り
申告が完了したら、確定した税額を納付期限(所得税は通常3月15日)までに自分で納付します。
納付方法には、口座振替やクレジットカード納付、コンビニ納付などがあります。
後日、税理士から提出した申告書の控えと、預けていた資料一式が返却されて、一連の流れは完了となります。
確定申告の代行依頼先を選ぶポイント
ここでは、依頼先を選ぶ際にチェックすべき重要なポイントを解説します。
ポイント1:税理士資格をきちんと確認する
基本中の基本ですが、最も重要なポイントです。
前述の通り、税務代理や税務書類の作成は税理士の独占業務です。
必ず、税理士証票(資格の証明書)を見せてもらうか、日本税理士会連合会のウェブサイトにある「税理士情報検索」で登録情報を確認しましょう。
「税理士事務所」「会計事務所」「税理士法人」といった名称の事務所であれば、まず問題ありません。
ポイント2:料金体系が明確で分かりやすいか
「確定申告一式〇円」と書かれていても、その料金にどこまでのサービスが含まれているのかを詳しく確認する必要があります。
記帳代行や相談料、消費税申告などが別途オプション料金になっていないか、後から追加料金を請求されることがないか、料金体系が明確で分かりやすく説明してくれる税理士を選びましょう。
また、見積書にサービス内容の内訳が細かく記載されている事務所を選ぶと安心です。
ポイント3:自分の業種に詳しいか、実績は豊富か
税理士にも、それぞれ得意な業種や分野があります。
例えば、IT業界、飲食業界、建設業界など、業界特有の会計処理や税務上の慣行が存在します。
あなたのビジネスと同じ業種の顧客を多く抱えている税理士であれば、業界への理解が深く、より的確なアドバイスが期待できます。
面談の際に、同業種のクライアントの実績について質問してみると良いでしょう。
ポイント4:コミュニケーションが取りやすく、相性が良いか
税理士は、お金に関する非常にデリケートな情報を共有するパートナーです。
そのため、専門知識があることと同じくらい、人としての相性やコミュニケーションの取りやすさが重要になります。
専門用語ばかりで話がわかりにくい、高圧的で質問しづらい、といった相手では、長期的に良い関係を築くことは難しいでしょう。
話を親身に聞いてくれる、専門外の人間にもわかりやすい言葉で説明してくれるなど、信頼できる人柄の税理士を選びましょう。
ポイント5:レスポンスの速さや連絡手段は適切か
ビジネスではスピード感が求められます。
質問のメールを送っても何日も返信がない、電話をしてもなかなかつながらない、といった税理士では、不安になったり、業務が滞ったりしてしまいます。
問い合わせや面談の際の対応の速さは、契約後の仕事ぶりを判断する上での1つの目安となります。
また、連絡手段が電話やFAXだけでなく、メールやビジネスチャットなど、自分が使いやすいツールに対応しているかも確認しておくと良いでしょう。
ポイント6:ITツールやクラウド会計に強いか
近年、会計業務の世界でもクラウド化が急速に進んでいます。
普段はクラウド会計ソフト(freeeやマネーフォワード クラウドなど)を利用している、またはこれから利用したいと考えているのであれば、それらのツールに詳しい税理士を選ぶことが不可欠です。
クラウド会計に精通した税理士であれば、データの共有がスムーズになり、リアルタイムで経営状況を把握しながら、より効率的なサポートを受けることができます。
確定申告の補助業務依頼には『Chatwork 経理アシスタント』がおすすめ!
「税理士に確定申告の代行を依頼したいけれど、その前に、溜まった領収書の整理や日々の記帳を片付けなければ」。
「顧問契約を結ぶほどの規模ではないけれど、経理作業の一部だけでも誰かに手伝ってほしい」。
このような悩みを持つ個人事業主の方に、ぜひご紹介したいのが『Chatwork 経理アシスタント』です。
Chatwork 経理アシスタントは、確定申告前に済ませておかなければならない「日々の経理業務」をオンラインでサポートしてくれるサービスです。
具体的には、領収書や請求書のスキャンデータを送るだけで、面倒な記帳作業(会計ソフトへの入力)を代行してくれます。
いわば、税理士に確定申告を依頼するための「下準備」を、まるっとお任せできるサービスです。
日々の記帳がきちんと行われていれば、税理士に支払う確定申告の代行料金も安く抑えることができます。
経理担当者を雇うことなく、必要な分だけプロのサポートを受けられる、新しい形のアウトソーシングと言えるでしょう。
Chatwork 経理アシスタントを導入するメリット
『Chatwork 経理アシスタント』を活用することで、個人事業主が得られるメリットを紹介します。
メリット1:面倒な記帳業務から完全に解放される
最大のメリットは、日々の記帳作業という、経理の中でも特に時間のかかる定型作業から解放されることです。
レシートや領収書をスマートフォンで撮影したり、スキャナで取り込んだりして送るだけで、専属のアシスタントが正確に会計ソフトへ入力してくれます。
そのため、経理作業に追われる時間が減り、安心して本業に専念することができます。
また、確定申告の直前になって、1年分の領収書の山と格闘する必要もなくなります。
メリット2:リーズナブルな料金で利用できる
経理担当者を1人雇用すれば、月々数十万円の人件費がかかります。
『Chatwork 経理アシスタント』は、月額制のリーズナブルな料金で、必要な経理サポートを受けることができます。
取引量に応じた複数のプランが用意されているため、事業規模に合わせて無駄なく利用を開始できます。
コストを抑えながら経理業務を効率化したい個人事業主やスタートアップにとって、非常に費用対効果の高い選択肢です。
メリット3:Chatworkで手軽にコミュニケーションが取れる
アシスタントとのやり取りは、すべてビジネスチャット「Chatwork」で完結します。
メールのように形式的な挨拶は不要で、チャットで気軽に質問や依頼ができます。
データの受け渡しもチャットにアップロードするだけなので、非常にスムーズです。
使い慣れたインターフェースで、まるで社内の経理担当者とやり取りするかのように、ストレスなくコミュニケーションを取ることができます。
確定申告は、1年に1度の義務であり、事業の成績表をまとめる重要な作業です。
その負担を専門家の力で軽減し、生まれた時間を事業の成長のために活用してください。