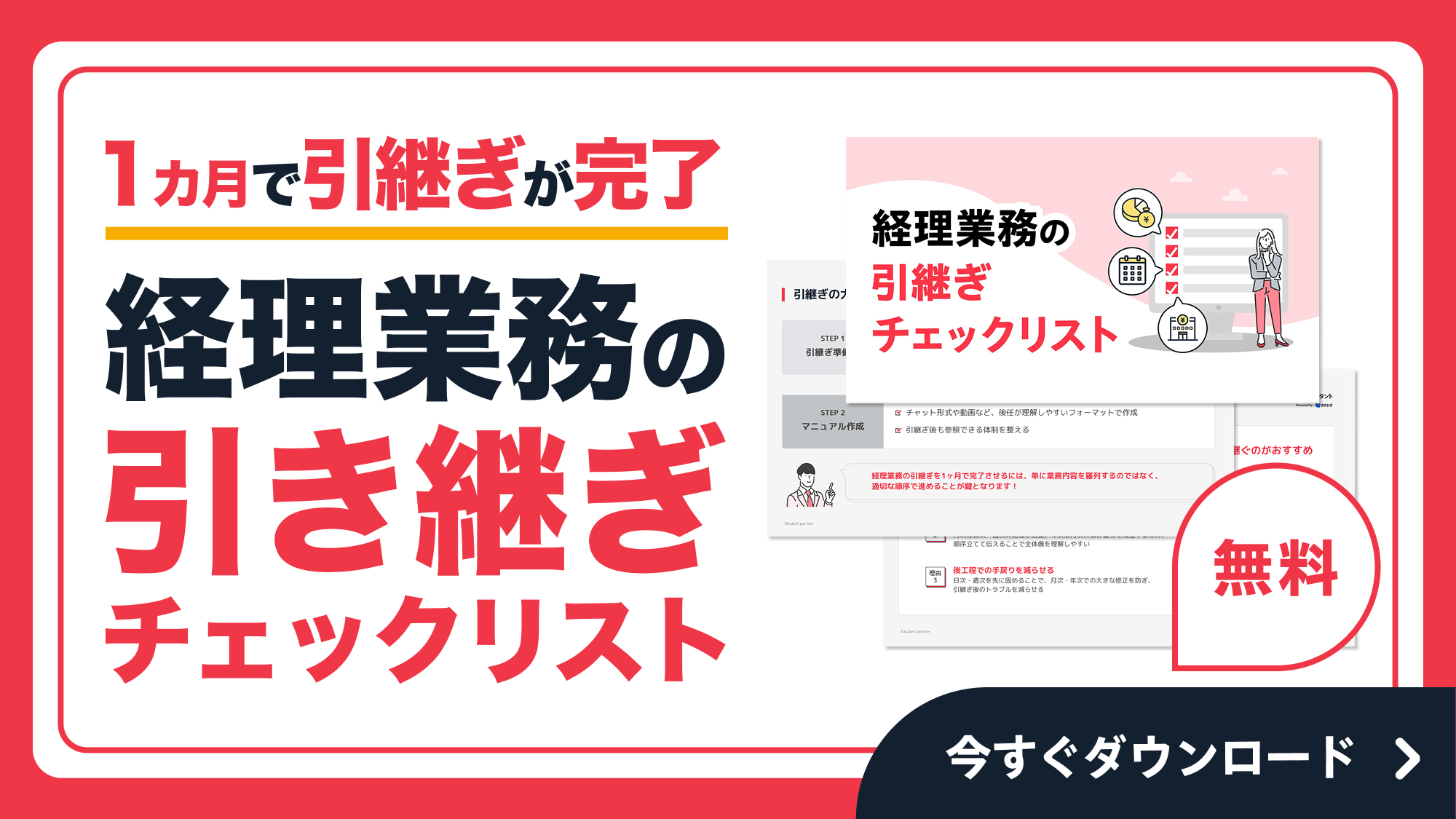助成金申請代行は誰に依頼すべき?違法になるケースや費用相場、補助金との違いとは

終わらない!

- リリースからわずか2年で
累計1000社以上が採用したサービス - 厳選された優秀なアシスタントが支援
- あらゆる経理業務を専門チームが代行
- 人手不足を解決し、安定した経理体制へ

目次
企業の成長や雇用の安定を目的に、国や地方自治体はさまざまな助成金を用意しています。
返済不要の資金として活用できる制度ですが、スムーズに申請できないケースもあります。
また、「自社がどの助成金を使えるのかわからない」。
「申請書類が複雑で、作成する時間がない」。
「計画書の作成や要件の確認が難しく、途中で諦めてしまった」。
このような理由から、本来活用できるはずの助成金を見送ってしまっている企業は少なくありません。
この課題を解決する有効な手段が、「助成金申請代行」です。
この記事では、助成金申請代行とは何かという基本から、依頼先の正しい選び方、違法となるケース、気になる費用相場まで、詳しく解説します。
助成金申請代行とは
助成金申請代行とは、企業が国や地方自治体の助成金制度を活用する際、申請に関わる一連の手続きを、専門家に依頼できるサービスのことです。
助成金には、いくつかの申請プロセスがあります。
まず、数多く存在する助成金の中から自社の状況に合致するものを探し出す必要があります。
次に、対象となる助成金の公募要領を詳細に読み解き、受給要件を満たしているかを確認します。
そして、事業計画の策定、実施計画書の作成、その他多数の添付書類の準備といった作業をこなさなければいけません。
助成金申請代行サービスは、これらの複雑で煩雑なプロセスを、専門的な知識と経験によって正確かつ効率的に進めてくれます。
そのため、企業は申請手続きにかかる膨大な時間と労力を削減し、受給の可能性を高めることができます。
助成金申請代行はどこに・誰に依頼すればいい?
助成金の申請代行を検討する際、最も重要かつ最初に理解しておくべき点が「誰に依頼するのが正しいのか」という問題です。
結論から言うと、厚生労働省が管轄する雇用関係の助成金申請代行は、「社会保険労務士(社労士)」にしか依頼できません。
これは、社会保険労務士法という法律によって、助成金の申請書類の作成や提出代行が、社労士の「独占業務」として明確に定められているためです。
独占業務とは、その資格を持つ者だけが行うことを法律で許可された業務のことを指します。
したがって、社労士の資格を持たないコンサルティング会社や個人が、報酬を得て雇用関係助成金の申請代行を行うことは、法律違反となります。
一方で、経済産業省が管轄する補助金(例:ものづくり補助金、IT導入補助金など)の申請支援は、税理士や中小企業診断士、行政書士、または民間のコンサルタントなども行っています。
しかし、一般的に「助成金」として広く認知されているキャリアアップ助成金や雇用調整助成金といった、雇用の維持や人材育成を目的とするものは、すべて厚生労働省の管轄です。
そのため、「助成金の申請を代行してほしい」と考えた場合、その依頼先は社会保険労務士(社労士)が唯一の正当な選択肢であると認識しておくことが極めて重要です。
助成金と補助金の違い
「助成金」と「補助金」は、どちらも国や自治体から支給される返済不要の資金であるため混同されがちですが、その性質には明確な違いがあります。
助成金
主な管轄:厚生労働省
主な目的:雇用の安定、人材育成、労働環境の改善など、労働に関連する政策の実現を目的としています。
審査の特徴:定められた受給要件をすべて満たしていれば、原則として受給することができます。
審査は、要件を満たしているかどうかの確認が中心となります。
公募期間:通年で公募されているものが多く、比較的申請のタイミングを計画しやすいです。
具体例:キャリアアップ助成金、人材開発支援助成金、雇用調整助成金など。
補助金
主な管轄:経済産業省、地方自治体など
主な目的:新規事業の創出、設備投資の促進、技術開発、地域振興など、国の産業政策や経済政策の実現を目的としています。
審査の特徴:受給要件を満たしていることに加え、事業計画の新規性や実現可能性、政策目標への貢献度などが厳しく審査されます。
予算や採択件数に上限があるため、応募者の中から優れた事業が選ばれる競争的な仕組みです。
公募期間:特定の期間だけ公募されるものが多く、申請のタイミングが限られています。
具体例:ものづくり補助金、IT導入補助金、事業再構築補助金など。
この記事で主に扱う「助成金」とは、厚生労働省が管轄する、雇用に関連するものを指します。
申請代行してもらえる助成金の種類
社労士に申請代行を依頼できる厚生労働省管轄の助成金には、さまざまな種類があります。
ここでは、多くの企業で活用されている代表的な助成金をいくつかご紹介します。
キャリアアップ助成金
非正規雇用の労働者(有期契約労働者、パートタイマー、派遣労働者など)の企業内におけるキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して給付される助成金です。
人材開発支援助成金
従業員の職業能力開発を段階的かつ体系的に行う事業主を支援する助成金です。
職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための訓練(OJT、Off-JT)にかかる経費や、訓練期間中の賃金の一部などが補助されます。
雇用調整助成金
景気の変動など経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を解雇することなく、一時的な休業や教育訓練、出向によって雇用の維持を図った際に、休業手当や賃金の一部を補う助成金です。
両立支援等助成金
従業員の仕事と家庭(育児や介護)の両立を支援するための助成金です。
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりに取り組んだ場合に支給される「出生時両立支援コース」や、介護離職を防止するための取り組みを行った場合に支給される「介護離職防止支援コース」などがあります。
特定求職者雇用開発助成金
就職が特に困難な人(高齢者(60歳以上)や障害者、母子家庭の母など)を、ハローワークなどの紹介によって継続雇用する事業主に対して支給される助成金です。
上記で紹介したような助成金は、それぞれ詳細な受給要件や申請手続きが定められているため、専門家である社労士のサポートを受けることでスムーズな申請が可能になります。
助成金申請代行が違法になるケースとは
助成金申請代行を依頼する上で絶対に避けなければならないのが、違法な無資格業者に依頼してしまうことです。
前述の通り、厚生労働省管轄の助成金に関する申請書類の作成および提出代行は、社会保険労務士(社労士)の独占業務です。
社労士の資格を持たないコンサルティング会社や個人が、これらの業務を報酬を得て行うことは、社会保険労務士法第27条および第32条の2の規定に違反する明確な違法行為となります。
なぜ違法なのか
雇用関係の助成金は、労働基準法や雇用保険法といった労働社会保険諸法令に深く関連しています。
これらの法令に関する専門的な知識を持たない者が申請を代行すると、誤った内容で申請が行われたり、本来の目的から外れた給付につながったりする恐れがあります。
そのため、労働社会保険諸法令の唯一の国家資格者である社労士に、その業務を独占させることで、制度の適正な運用を確保しているというのが理由です。
違法な代行業者の見分け方
違法な業者は、自らが法律違反を犯していることを隠して営業活動を行っています。
以下のような特徴を持つ業者には、特に注意が必要です。
社会保険労務士の資格や登録番号を明示していない:ウェブサイトや名刺に「社会保険労務士」の名称や登録番号の記載がない場合、無資格者である可能性が非常に高いです。
「100%受給可能」「必ずもらえる」などと過剰な宣伝文句を使う:助成金の受給には審査があるため、100%の受給を保証することはできません。
安易な言葉で契約を迫る業者には注意が必要です。
法外に高い成功報酬を要求する:相場を大幅に超える成功報酬(例:40%~50%)を提示してくる場合があります。
書類の作成・提出のみを請け負う:助成金受給に不可欠な就業規則の整備や労働条件の改善といった労務管理上のアドバイスを一切行わず、書類作成だけを請け負う業者は、制度への理解が浅い可能性があります。
違法業者に依頼してしまった場合のリスク
万が一、違法な業者に申請代行を依頼してしまった場合、企業側にも重大なリスクが生じます。
不正受給に加担させられるリスク:業者が不正な手段で助成金を受給しようとした場合、依頼した企業も不正受給の当事者と見なされ、助成金の返還や加算金、延滞金の支払いを命じられる可能性があります。
企業名が公表されるリスク:悪質な不正受給と判断された場合、企業名が公表され、社会的信用を大きく損なうことになります。
今後の助成金が受給できなくなるリスク:一度不正受給を行うと、その後一定期間、他の助成金も申請できなくなります。
自社を守るためにも、助成金の申請代行は、必ず正規の社会保険労務士に依頼するようにしてください。
助成金申請代行の費用相場
社会保険労務士(社労士)に助成金の申請代行を依頼する場合、その費用(報酬)は、主に「着手金」と「成功報酬」の2つの組み合わせで構成されるのが一般的です。
主な料金体系
1. 着手金
申請業務を開始するにあたって、最初に支払う費用のことです。
申請書類の作成や計画書の策定といった、社労士の稼働に対する費用として支払います。
着手金は、万が一助成金が不支給となった場合でも、原則として返金されない点に注意が必要です。
これは、不支給の場合でも社労士の業務は発生しているためです。
2. 成功報酬
無事に助成金の支給が決定し、入金された後に支払う費用のことです。
実際に受給できた助成金額の〇%という形で計算されます。
企業にとっては、助成金が受給できた場合にのみ発生する費用であるため、リスクの少ない料金体系と言えます。
3. 顧問契約料
日頃からその社労士と顧問契約を結び、月々の顧問料を支払っている場合は、助成金申請の着手金が無料になったり、成功報酬が割引されたりすることがあります。
顧問契約には、日々の労務相談や社会保険手続きなども含まれるため、長期的な視点で労務管理全般を任せたい場合に適しています。
費用相場の目安
具体的な費用は、申請する助成金の難易度や、社労士事務所の方針によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。
【着手金】
相場:2万円 ~ 10万円程度
最近では、顧客獲得のために着手金を「0円」に設定し、成功報酬のみで請け負う事務所も増えています。
顧問契約を結んでいる場合は、着手金が無料となるケースが多いです。
【成功報酬】
相場:受給額の10% ~ 20%程度
最も一般的なのは15%前後に設定されているケースです。
着手金が無料の場合、成功報酬がやや高め(20%~25%など)に設定されていることがあります。
逆に、相場を大幅に下回る成功報酬(例:5%など)を提示している場合は、サービスの質やサポート範囲を確認する必要があります。
例えば、100万円の助成金を受給できた場合、「着手金5万円+成功報酬15%」の契約であれば、支払う費用の総額は「5万円+(100万円×15%)=20万円」となります。
「着手金0円+成功報酬20%」であれば、総額は20万円です。
契約前には、必ず料金体系の内訳を詳細に確認し、納得した上で依頼することが重要です。
助成金申請代行先の選び方
信頼できる社会保険労務士(社労士)を見つけることは、助成金申請を成功させるための最も重要な要素です。
ここでは、依頼先を選ぶ際にチェックすべき5つのポイントを解説します。
ポイント1:社会保険労務士の資格を必ず確認する
繰り返しになりますが、これが最も重要な大前提です。
依頼を検討している相手が、本当に社会保険労務士の資格を持っているかを確認しましょう。
ウェブサイトや名刺に「社会保険労務士」の名称と「登録番号」が明記されているかを確認します。
少しでも疑問に感じたら、全国社会保険労務士会連合会のウェブサイトにある検索システムで、名前や登録番号を照会することができます。
ポイント2:助成金申請の実績が豊富か
社労士にも、それぞれ得意な専門分野があります。
労働問題の解決が得意な社労士、年金相談が得意な社労士など様々です。
その中で、助成金の申請代行を数多く手掛けており、豊富な実績と最新のノウハウを持っている社労士を選ぶことが重要です。
特に、自社が申請したいと考えている助成金について、過去にどのくらいの申請実績があるかを面談時に具体的に質問してみましょう。
ポイント3:料金体系が明確で分かりやすいか
契約後に「こんなはずではなかった」という金銭的なトラブルを避けるためにも、料金体系の明確さは必ず確認すべきポイントです。
着手金と成功報酬の金額や割合はもちろんのこと、それ以外に追加で費用が発生する可能性はないか(例:就業規則の変更費用、出張費など)、書面で明確に提示してもらいましょう。
複数の事務所から見積もりを取り、サービス内容と料金を比較検討することをおすすめします。
ポイント4:コミュニケーションが円滑に取れるか
助成金の申請は、社労士にすべてを丸投げして終わるものではありません。
計画の策定や書類の準備段階で、自社の状況について何度もヒアリングを受けたり、資料の提出を求められたりします。
そのため、担当の社労士と円滑にコミュニケーションが取れるかどうかは非常に重要です。
専門用語を多用せず、分かりやすい言葉で説明してくれるか、こちらの質問に丁寧に答えてくれるか、レスポンスは速いかなどを、契約前の面談で見極めましょう。
ポイント5:助成金受給後のサポート体制
助成金は、受給して終わりではありません。
多くの場合、計画通りに制度が運用されているかを確認するための実地調査や、その後の状況報告が求められます。
申請代行だけでなく、受給後のこれらの対応までサポートしてくれるのか、その場合の費用はどうなるのかを、事前に確認しておくと安心です。
長期的な視点で企業の労務管理をサポートしてくれる、信頼できるパートナーを選びましょう。
助成金申請代行に関する注意点
助成金申請代行をスムーズに進め、期待した成果を得るために、依頼する企業側が注意すべき点を3つご紹介します。
注意点1:「丸投げ」はできないと理解する
専門家に依頼したからといって、自社が何もしなくて良いわけではありません。
助成金の申請には、出勤簿や賃金台帳、労働者名簿といった、会社の労務管理に関する多くの書類が必要不可欠です。
これらの書類を準備し、社労士に提供するのは企業側の役割です。
また、事業計画の策定にあたっては、自社の経営状況や今後の展望について、社労士からの詳細なヒアリングに応える必要があります。
社労士をパートナーとして、二人三脚で申請を進めていくという意識を持つことが、申請成功の鍵となります。
注意点2:労務管理の基礎が整備されていることが前提
助成金は、適切な労務管理を行っている企業に対して支給されるものです。
例えば、「そもそも労働者名簿や出勤簿、賃金台帳といった法定三帳簿を整備していない」「従業員に残業代を支払っていない」といった、労働関係法令に違反している状態では、助成金を受給することはできません。
社労士に依頼すると、まず最初にこうした基本的な労務管理の状況をチェックされます。
もし不備があれば、助成金申請の前に、まずその是正から取り組む必要があります。
注意点3:助成金は後払いであることを認識する
助成金は、申請してすぐに受け取れるものではありません。
原則として、まず企業が計画に沿って従業員の正社員転換や訓練などを「実施」し、それに要した経費を「支払った後」に、支給申請を行います。
そして、審査を経てから数ヶ月後に、指定の口座に振り込まれるという流れになります。
つまり、一時的に費用を立て替える必要があるため、その間の資金繰りも考慮しておく必要があります。
助成金は、運転資金の補填ではなく、あくまでも雇用に関する前向きな取り組みを支援するための資金であると理解しておきましょう。
助成金申請代行にビジネスチャットを活用した事例
助成金の申請代行を依頼する際、社会保険労務士(社労士)との円滑なコミュニケーションは成功の鍵を握ります。
近年、電話やメールに代わる効率的なコミュニケーションツールとして、ビジネスチャットの活用が進んでいます。
ある税理士・社会保険労務士法人では、顧客との情報共有やタスク管理に、ビジネスチャットツール「Chatwork」を導入し、大きな成果を上げています。
【導入前の課題】
従来、顧客とのやり取りは電話やメールが中心でした。
しかし、電話では言った言わないの問題が発生しやすく、記録も残りません。
メールでは、他の多くのメールに埋もれてしまい、重要な連絡や資料の提出依頼が見落とされてしまうことがありました。
特に助成金申請では、多数の書類を期限内に準備してもらう必要があり、進捗管理が煩雑になっていました。
【ビジネスチャット導入後の解決策と成果】
この法人では、顧客ごとにChatworkのグループチャットを作成し、助成金申請に関するすべてのやり取りをその中で完結させるようにしました。
確実な情報伝達:チャット形式のため、やり取りの履歴がすべて時系列で記録され、確認漏れや認識の齟齬がなくなりました。
効率的なタスク管理:顧客に準備してほしい書類を「タスク機能」で依頼。
これにより、依頼内容と期限が明確になり、顧客も何をすべきかが一目でわかるようになりました。
社労士側も、タスクの完了状況をリアルタイムで把握でき、進捗管理が非常に容易になりました。
迅速なコミュニケーション:顧客は、スマートフォンアプリから、場所を選ばずに気軽に質問や報告ができるようになりました。
社労士も、移動中などの隙間時間を使って迅速に返信できるため、コミュニケーションの速度が格段に向上しました。
このように、ビジネスチャットを活用することで、社労士と依頼企業間のコミュニケーションが密になり、助成金申請のプロセス全体がスムーズかつ正確に進むようになります。
依頼先を選ぶ際には、こうしたITツールを積極的に活用しているかも、一つの判断基準となるでしょう。
まとめ
本記事では、助成金申請代行について、依頼先の正しい選び方から、違法となるケース、費用相場、そして成功のための注意点までを解説しました。
税理士という専門家の力を適切に活用することで、助成金申請の煩雑な手続きから解放され、企業のさらなる発展を目指すことができるでしょう。