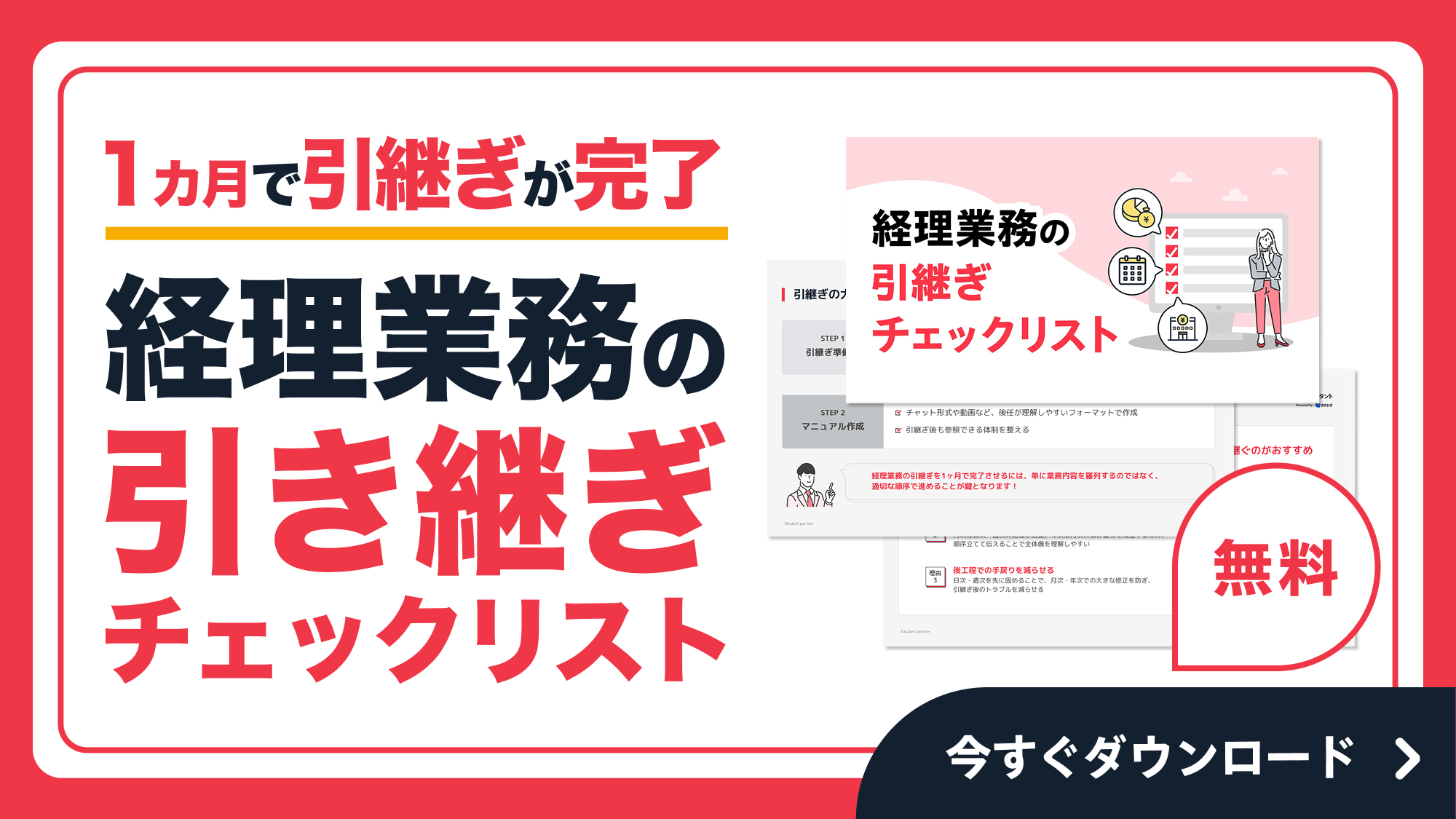年末調整代行サービス徹底ガイド|費用相場や依頼時の注意点、おすすめサービスなどを解説

終わらない!

- リリースからわずか2年で
累計1000社以上が採用したサービス - 厳選された優秀なアシスタントが支援
- あらゆる経理業務を専門チームが代行
- 人手不足を解決し、安定した経理体制へ

目次
毎年、年末が近づくと多くの企業の経理・人事担当者を悩ませる業務が「年末調整」です。
従業員ひとりひとりの所得税を正確に計算・精算するこの業務は、短期間に作業が集中し、専門的な知識も要求されるため、担当者にとって大きな負担となります。
本記事では、この課題を解決する有効な手段である「年末調整代行サービス」の基礎知識から具体的な業務内容、料金相場、サービスの選び方などを詳しく解説します。
年末調整代行サービスとは?
年末調整代行サービスとは、企業が従業員に対して行う年末調整関連の業務を、外部の専門家が代わりに実施してくれるサービスのことです。
年末調整とは、従業員が毎月の給与から源泉徴収された所得税の年間合計額と、その年に納めるべき所得税の正式な金額(年税額)との差額を精算するための重要な手続きであり、従業員が記入した申告書の回収や内容の精査、各種控除額の計算、年税額の算出、源泉徴収票の作成、行政機関への法定調書の提出など、多岐にわたる作業が含まれます。
年末調整代行サービスは、上記のように専門性が高く煩雑な作業を請け負ってくれるため、企業は担当者の業務負担を大幅に軽減することが可能になります。
年末調整代行サービスに依頼できる内容
年末調整代行サービスがカバーする業務範囲は非常に広く、企業のニーズに応じて一部の業務のみを依頼したり、一連のプロセスを全て任せたりすることが可能です。
ここでは、一般的に依頼できる業務内容を、年末調整のプロセスに沿って具体的にご紹介します。
1. 事前準備
年末調整業務をスムーズに開始するための準備段階の業務です。
年末調整の対象となる従業員のリストアップと確認。
従業員への年末調整の案内(スケジュール、提出書類など)の作成と配布。
各種申告書(扶養控除等申告書、保険料控除申告書など)の用紙の準備と配布。
2. 申告書の回収と内容のチェック
従業員から提出された書類を回収し、内容に不備がないかを確認する、最も手間のかかる業務の一つです。
従業員から提出された各種申告書の回収と進捗管理。
申告書の内容(扶養家族の情報、保険料の金額など)と、添付された証明書(保険料控除証明書、住宅ローン控除関連書類など)との突合チェック。
記載内容の不備や添付書類の不足があった場合の、従業員への問い合わせと修正依頼。
3. 年税額の計算
回収・チェックした情報をもとに、従業員一人ひとりの年税額を正確に計算します。
給与計算ソフトなどへの申告書データ入力。
各種控除額(生命保険料控除、地震保険料控除、住宅ローン控除など)の計算。
年間の給与・賞与総額と各種控除額をもとに、年税額を算出。
源泉徴収済みの税額との差額(過不足額)を計算し、還付または追加徴収額を確定。
4. 各種帳票の作成と提出
計算結果をもとに、法律で定められた各種の帳票を作成し、従業員や行政機関へ提出します。
従業員へ交付する「源泉徴収票」の作成。
税務署へ提出する「法定調書合計表」の作成と提出。
各市区町村へ提出する「給与支払報告書」の作成と提出。
5. 従業員からの問い合わせ対応
年末調整の期間中、従業員から寄せられる様々な質問に対応する業務です。
「この書類の書き方がわからない」「この保険は控除の対象になるか」といった個別の質問に対して、専門的な知識をもとに回答します。
この業務を代行してもらうことで、担当者は煩雑な問い合わせ対応から解放されます。
年末調整関連の業務によく見られる課題
多くの企業が年末調整代行サービスを検討する背景には、この業務特有のいくつかの課題が存在します。
短期間での業務量の急増
年末調整の業務は、主に11月から翌年1月までの約3ヶ月間に集中します。
短期間に、全従業員分の書類チェック、計算、帳票作成といった大量の作業を完了させる必要があるため、担当者には通常業務に加えて膨大な業務負荷がかかり、長時間の残業が常態化してしまうケースが少なくありません。
急激に増加する業務量を、社内の担当者へどのように割り振るかは大きな課題です。
専門的な知識の必要性と法改正への対応
年末調整は、所得税法に基づいた正確な知識が求められる専門的な業務です。
扶養控除の条件や各種保険料控除の計算など、その内容は非常に複雑です。
加えて、税制は毎年のように改正が行われるため、常に最新の情報を収集し、知識をアップデートし続ける必要があります。
担当者が他の業務と兼務している場合など、これらの法改正に正確に対応し続けることは大きな負担となり、知識不足による計算ミスのリスクも高まります。
従業員からの問い合わせ対応の煩雑さ
年末調整の時期になると、従業員から申告書の書き方や控除の仕組みに関する問い合わせが殺到します。
ひとりひとりの状況に応じた個別の質問に丁寧に対応する必要があるため、担当者の業務を大きく圧迫する要因となります。
特に、住宅ローン控除の初年度など、複雑なケースの問い合わせには、担当者自身が内容を調べながら対応する必要も生じます。
ヒューマンエラーのリスク
年末調整は、大量の数値を扱い、手作業での確認や入力が多い業務です。
そのため、どんなに注意深く作業を行っても、計算ミスや転記ミスといったヒューマンエラーが発生するリスクを完全には排除できません。
年末調整の計算ミスは、従業員の所得税額に直接影響するため、従業員との信頼関係を損なう原因となります。
また、税務署からの指摘を受け、追徴課税や延滞税が発生する可能性もあります。
年末調整代行サービスの料金相場
年末調整代行サービスの導入を検討する上で、最も重要な判断材料の1つが費用です。
料金体系やその相場は、依頼する業務範囲や企業の従業員数によって変動します。
主な料金体系
多くの年末調整代行サービスでは、以下の2つの要素を組み合わせた料金体系が採用されています。
料金 = 基本料金 + (従業員1人あたりの単価 × 対象人数)
基本料金:年末調整業務全体を管理・進行するための基本費用として、企業の規模に関わらず固定で発生します。
この料金には、基本的なコンサルティングや進捗管理費用などが含まれます。
従業員1人あたりの単価(従量課金):従業員一人ひとりの年末調整処理に対して発生する費用です。
処理する人数に応じて、総額が変動します。
既に税理士や社会保険労務士と顧問契約を結んでいる場合は、顧問料の範囲内で対応してくれるケースや、通常よりも安い割引料金で請け負ってくれるケースもあります。
料金相場の目安
具体的な料金はサービス提供元によって様々ですが、一般的な相場は以下の通りです。
【基本料金】
相場:1万円 ~ 5万円程度
従業員数が少ない企業向けに、基本料金を0円や1万円程度に設定している事務所もあります。
一方で、サポート体制が手厚いサービスでは5万円以上の基本料金となる場合もあります。
【従業員1人あたりの単価】
単価は、年末調整の対象となる従業員の数に応じて変動するのが一般的です。
人数が多ければ多いほど、一人あたりの単価は安くなる傾向があります。
| 従業員1人あたりの単価 | |
|---|---|
| 基本単価 | 1,500円 ~ 3,000円 |
| 住宅ローン控除対象者 | 上記に+2,000円 ~ 5,000円の追加料金 |
| 年の途中で入退社した従業員 | 上記に+1,000円 ~ 3,000円の追加料金 |
住宅ローン控除の計算や、中途入退職者の前職分の給与を含めた計算は、手間が増えるため追加料金が設定されていることがほとんどです。
例えば、従業員30名(うち住宅ローン控除対象者2名)の企業が、基本料金2万円、基本単価2,000円、住宅ローン控除追加料金3,000円のサービスに依頼した場合、費用の総額は「基本料金2万円+(単価2,000円×28名)+(単価5,000円×2名)=8万6,000円」程度が目安となります。
年末調整代行サービスを利用するメリット
年末調整の煩雑な業務を外部に委託することは、企業に多くのメリットをもたらします。
メリット1:担当者の業務負担の大幅な軽減
最大のメリットは、担当者を季節的な業務量の急増から解放できることです。
年末調整に費やしていた膨大な時間を削減できるため、担当者は残業をすることなく、通常業務や、より付加価値の高い業務に集中することができます。
担当者の心身の負担が軽減されることは、離職率の低下や従業員満足度の向上にも繋がります。
メリット2:業務の正確性と品質の向上
年末調整は、税理士や社会保険労務士といった税務・労務の専門家が、豊富な知識と経験に基づいて業務を遂行します。
複雑な控除計算や頻繁な法改正にも、正確かつ迅速に対応します。
その結果、計算ミスや申告漏れといったヒューマンエラーを限りなくゼロに近づけることができ、業務の品質が飛躍的に向上します。
これは、追徴課税などの税務リスクを回避し、コンプライアンスを強化することに直結します。
メリット3:コストの最適化
年末調整の繁忙期のために、追加で人員を雇用したり、派遣社員を依頼したりすると、大きなコストが発生します。
代行サービスを利用すれば、必要な期間だけ、必要な業務量に応じた費用を支払うだけで済みます。
担当者が残業して対応する場合の残業代と比較しても、代行サービスを利用する方が結果的に総費用を安く抑えられるケースは少なくありません。
人件費を固定費から変動費に変えることで、経営資源を効率的に活用できます。
メリット4:業務の属人化の防止
年末調整のような専門性の高い業務は、「特定の担当者しかやり方が分からない」という属人化の状態に陥りがちです。
この担当者が急に休職したり退職したりすると、業務が滞ってしまうという大きなリスクがあります。
代行サービスを利用することで、業務は委託先の組織として、標準化されたプロセスで運用されます。
社内の担当者に依存しない、持続可能で安定した業務体制を構築することができます。
年末調整代行サービスを利用するデメリット
多くのメリットがある一方で、年末調整代行サービスの導入にはいくつかのデメリットや注意点も存在します。
デメリット1:外注費用がかかる
当然のことながら、外部のサービスを利用するには費用が発生します。
企業の従業員数や依頼内容によっては、数万円から数十万円のコストがかかります。
社内に専門知識を持つ担当者がおり、リソースに余裕がある場合には、自社で対応する方がコストを抑えられる可能性もあります。
自社で対応した場合にかかる人件費(残業代含む)や時間的コストを算出し、代行サービスの費用と比較して、費用対効果を慎重に検討する必要があります。
デメリット2:情報漏洩のリスク
年末調整業務を外部に委託するということは、全従業員の氏名、住所、マイナンバー、給与、扶養家族の情報といった、極めて機密性の高い個人情報を外部の業者に預けることを意味します。
委託先のセキュリティ管理体制が不十分な場合、これらの情報が外部に漏洩するリスクはゼロではありません。
情報漏洩は企業の信用問題に直結するため、依頼先のセキュリティ対策は厳しくチェックすることが不可欠です。
デメリット3:社内にノウハウが蓄積されにくい
年末調整のプロセスをすべて外部に委託してしまうと、その業務に関する詳細な知識や、イレギュラーなケースへの対応経験といったノウハウが社内に蓄積されにくくなります。
将来的に内製化を検討する際に、一から知識を習得し、業務フローを構築し直す必要が生じる可能性があります。
完全に任せきりにするのではなく、委託先から業務フローや計算根拠に関する報告を受けるなど、社内でも状況を把握しておくことが望ましいです。
デメリット4:コミュニケーションコストと情報伝達の遅延
外部の業者と連携するため、一定のコミュニケーションコストが発生します。
従業員からの問い合わせに対して、一度社内で受けてから業者に確認するといったプロセスが必要になる場合、回答までに時間がかかることがあります。
また、従業員情報の伝達にミスがあったり、追加で資料の提出が必要になったりと、社内であれば不要なやり取りが発生することもあります。
円滑な連携を図るための、明確な情報共有ルールの設定が必要です。
年末調整代行サービスの選び方
自社に最適な年末調整代行サービスを見つけるためには、どのような点に注目すれば良いのでしょうか。
ここでは、依頼先選定で失敗しないための5つのポイントを解説します。
ポイント1:依頼先の専門性と資格
年末調整は税務と労務の両方に関わる業務ですが、税務書類の作成や税務代理は税理士の独占業務です。
そのため、依頼先は税理士事務所、または税理士が提携している社会保険労務士事務所や代行会社であることが大前提となります。
自社の顧問税理士や顧問社労士がいれば、まずはそこに相談するのが最もスムーズです。
新規で探す場合は、依頼先が適切な資格を有しているかを必ず確認しましょう。
ポイント2:セキュリティ対策の信頼性
従業員の大切な個人情報を預けるため、セキュリティ体制の確認は最優先事項です。
信頼性を客観的に判断する指標として、プライバシーマーク(Pマーク)やISMS(ISO27001)認証の取得状況を確認します。
また、秘密保持契約(NDA)の締結はもちろんのこと、データの送受信方法が暗号化されているか、情報の管理体制がどのようになっているかなど、具体的な対策について明確に説明を求めましょう。
ポイント3:料金体系の明確さと費用対効果
料金の安さだけで判断せず、その費用にどこまでの業務が含まれているのか、内訳を詳細に確認することが重要です。
基本料金と単価だけでなく、住宅ローン控除などの追加料金、従業員からの問い合わせ対応が含まれるかなどをすべて把握した上で、総費用を試算しましょう。
その上で、自社で得られるメリット(人件費削減、品質向上など)と比較し、納得できる費用対効果かを見極めてください。
ポイント4:サポート体制とコミュニケーションの円滑さ
業務を円滑に進めるためには、委託先とのスムーズな連携が不可欠です。
従業員からの問い合わせに直接対応してくれる窓口を設置してくれるのか、あるいは社内の担当者を通じて対応するのか、サポートの範囲を確認しましょう。
また、進捗状況の報告方法や、連絡手段(電話、メール、チャットなど)が自社のスタイルに合っているかも、ストレスなく業務を進める上で大切なポイントです。
ポイント5:自社の給与計算システムとの連携
現在、社内で給与計算システムを利用している場合、そのシステムとスムーズに連携できるかは業務効率に大きく影響します。
年末調整の計算結果を、給与計算システムに手作業で再入力する必要があるのか、それともデータで簡単インポートできるのかを確認しましょう。
使用しているシステムに対応した実績が豊富な依頼先を選ぶことで、より円滑な連携が可能になります。
年末調整代行サービスを利用する際の注意点
自社に合った年末調整代行サービスを選んだとしても、依頼側の準備や認識が不足していると、期待した効果が得られない場合があります。
ここでは、代行依頼を成功させるための注意点を3つご紹介します。
注意点1:早めの依頼を心掛ける
年末調整代行サービスには、繁忙期があります。
多くの企業が依頼を検討する10月以降になると、優良な代行業者のスケジュールは埋まってしまい、新規の受付を締め切ってしまうことがあります。
また、期限ギリギリの依頼は、料金が割高になったり、十分な準備ができずサービスの品質が低下したりする原因にもなります。
理想的には、夏から秋口(8月~9月頃)までには依頼先を決定し、契約を済ませておくのが良いでしょう。
注意点2:依頼範囲と役割分担を明確にする
導入前に、どこからどこまでの業務を委託するのか、その範囲を委託先と明確にすり合わせることが重要です。
例えば、「従業員への書類配布は自社で行う」「不備があった際の修正依頼は委託先から直接従業員に行ってもらう」など、具体的な業務フローと役割分担を文書で確認しておきましょう。
このすり合わせが曖昧だと、後から「これはどちらの担当業務か」といった問題が発生し、業務が停滞する原因になります。
注意点3:「丸投げ」はできないと認識する
業務を外部に委託したからといって、自社が何もしなくて良いわけではありません。
年末調整の基礎となる、従業員の毎月の給与データや扶養家族の異動情報などを、正確に委託先に提供するのは依頼元である企業の責任です。
また、従業員から提出される申告書を期日までに集めるための社内アナウンスなど、従業員の協力なくして年末調整は進められません。
委託先をパートナーとして、自社も主体的に協力する姿勢を持つことが成功の鍵です。
年末調整の代行依頼なら『Chatwork 経理アシスタント』がおすすめ!
「税理士や専門の代行会社に依頼する前に、まずは煩雑な書類の回収やチェック作業だけでも誰かに手伝ってほしい」。
「年末調整だけでなく、年間を通じた経理業務の波を平準化したい」。
このように、年末調整業務の前段階や、より柔軟なサポートを求めている企業におすすめしたいのが、『Chatwork 経理アシスタント』です。
『Chatwork 経理アシスタント』は、国内利用者数No.1のビジネスチャット「Chatwork」が提供する、オンラインアシスタントサービスです。
このサービスは、年末調整の申告代行そのもの(税理士の独占業務)を行うわけではありません。
その手前にある、最も時間と手間がかかる「申告書の回収・チェック」「データ入力」「従業員からの問い合わせ一次対応」といった準備業務を、経験豊富なアシスタントがサポートします。
アシスタントが整理・準備した正確なデータを、最終的に顧問税理士などに渡すことで、税理士の作業負担も軽減され、年末調整プロセス全体がスムーズになります。
必要な時期に、必要な分だけ、専門的なサポートを受けられる、新しい形の業務効率化サービスです。
Chatwork 経理アシスタントを導入するメリット
『Chatwork 経理アシスタント』を活用することで、企業は具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか。
その独自の強みを3つのポイントに絞ってご紹介します。
メリット1:季節的な業務の繁閑に合わせて柔軟に依頼できる
年末調整は季節業務であるため、この時期だけ人員を増やすのは非効率です。
『Chatwork 経理アシスタント』は、月々の実働時間に応じた料金体系のため、繁忙期である年末だけ稼働時間を増やして集中的にサポートを依頼するといった、柔軟な活用が可能です。
閑散期には、給与計算や請求書業務など、他の経理業務を依頼することで、年間を通じて経理部門の業務量を平準化できます。
メリット2:従業員との円滑なコミュニケーション
アシスタントとのやり取りや、従業員からの書類提出は、すべて使い慣れたビジネスチャット「Chatwork」で完結します。
従業員は、申告書をスマートフォンで撮影し、チャットで送信するだけで提出が完了します。
書類の不備があった場合の修正依頼や、従業員からの簡単な質問への一次対応もチャットで行えるため、担当者のコミュニケーション負担を大幅に削減します。
記録が残るため、言った言わないのトラブルも防ぎます。
メリット3:コストを抑えてバックオフィスを強化できる
正社員を一人雇用すれば、月々数十万円の人件費がかかります。
『Chatwork 経理アシスタント』は、月額数万円からというリーズナブルな料金で、プロのアシスタントチームを活用できます。
採用や教育の手間とコストを一切かけることなく、質の高いサポートをすぐに受けられるため、特に人手が限られる中小企業にとって、費用対効果が非常に高い選択肢です。
まとめ
本記事では、年末調整代行サービスについて、依頼できる業務範囲や料金相場、メリット・デメリット、選び方などを解説しました。
年末調整は、年に一度の義務でありながら、非常に多くの時間と専門知識を要する、企業の担当者にとって大きな負担となる業務です。
自社が抱える課題を明確にしつつ、本記事でご紹介した選び方のポイントを参考に、相性の良いサービスを見つけてみてください。