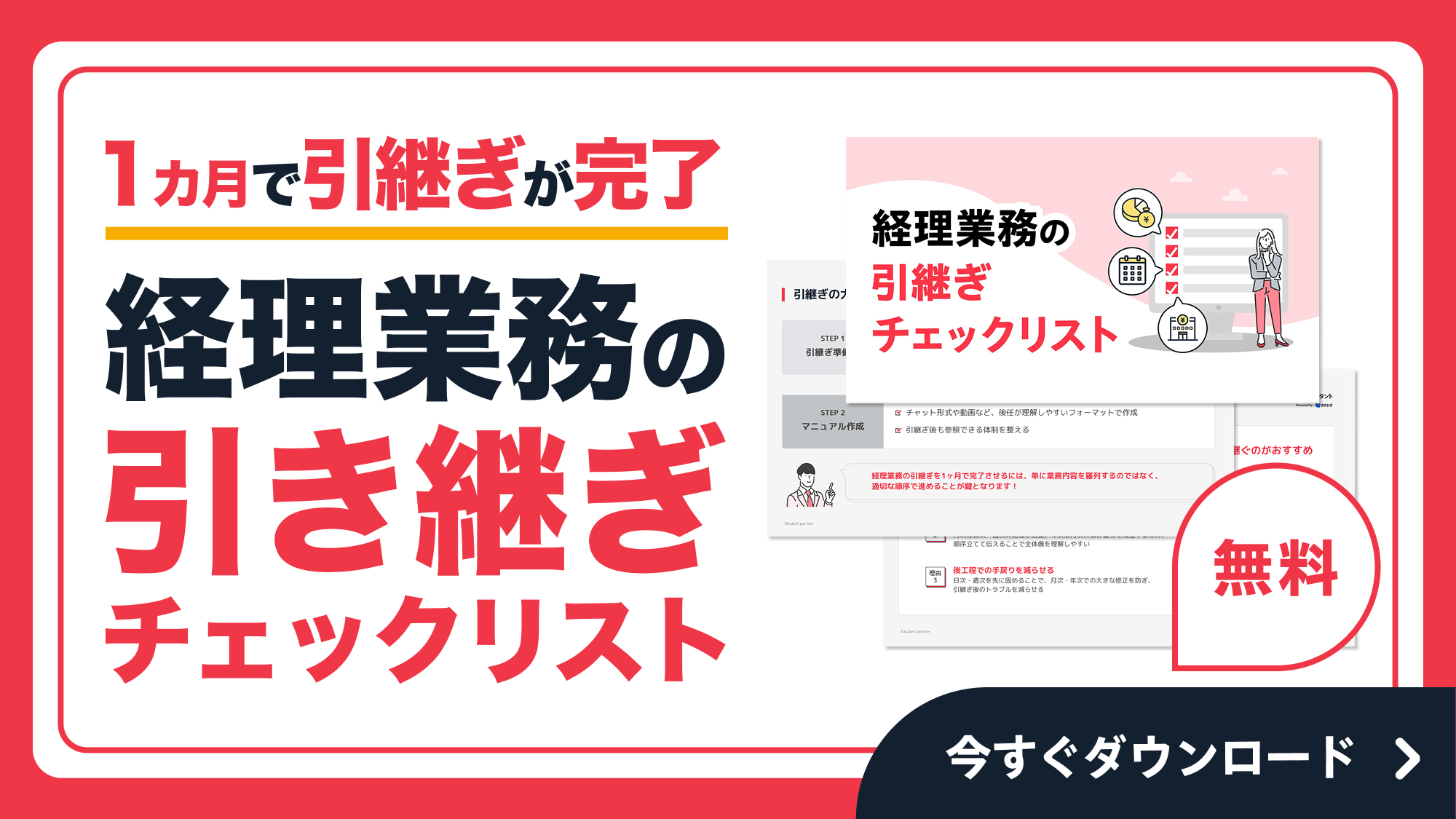請求書代行サービスとは?活用するメリット・デメリット、費用相場や選び方まで詳しく解説【2025年最新】
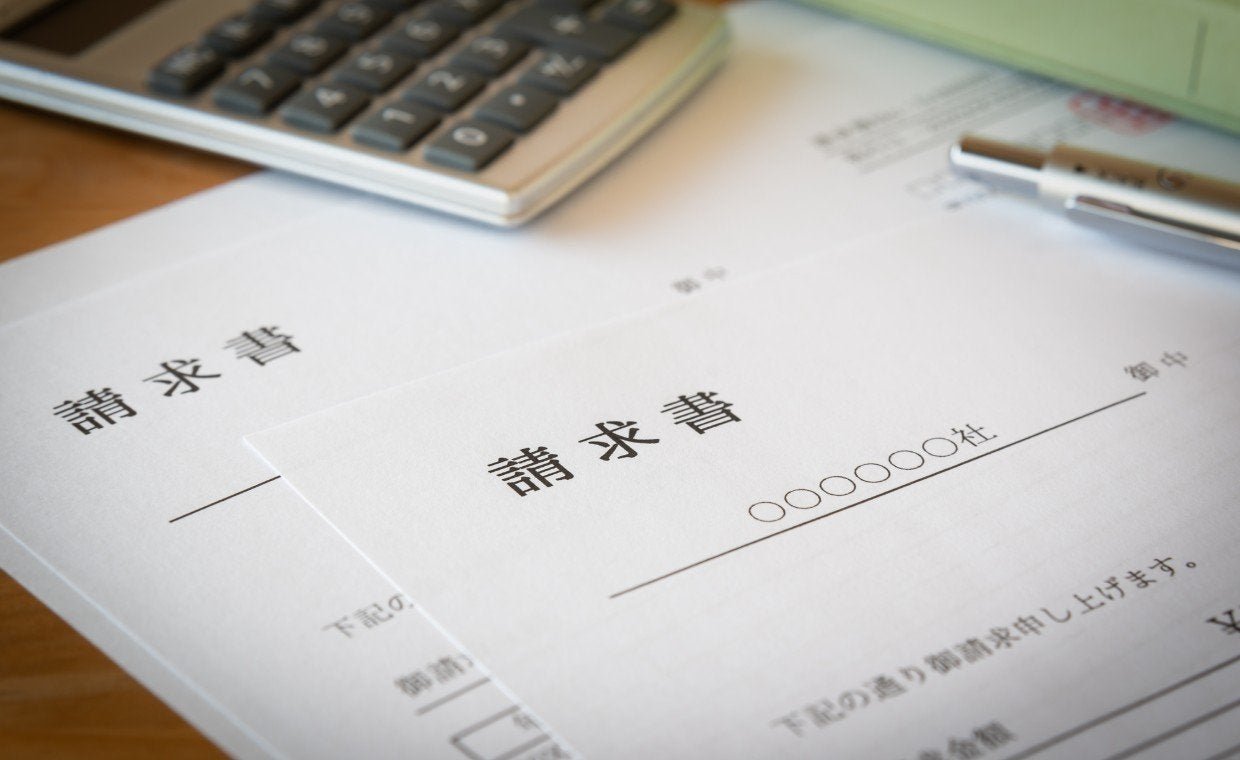
終わらない!

- リリースからわずか2年で
累計1000社以上が採用したサービス - 厳選された優秀なアシスタントが支援
- あらゆる経理業務を専門チームが代行
- 人手不足を解決し、安定した経理体制へ

目次
毎月発生する請求書の発行・送付業務は、企業の経理部門にとって重要な業務のひとつです。
請求書関連業務にさまざまな課題を抱え、代行サービスの利用を検討する企業も少なくありません。
請求書代行サービスは、煩雑な請求業務を専門家に任せることで、業務効率を飛躍的に向上させ、経理担当者をより付加価値の高い業務に集中させることを可能にします。
この記事では、請求書代行サービスの基本から、具体的な業務内容、導入のメリット・デメリット、気になる費用相場、そして自社に最適なサービスの選び方まで、詳しく解説します。
請求書代行サービスとは
請求書代行サービスとは、企業が行う請求関連業務、具体的には請求書の作成から発行、送付、そしてその後の入金管理や未入金時の督促に至るまでの一連のプロセスを、外部の専門業者が代わりに行うサービスのことです。
これは、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の一分野であり、企業のバックオフィス業務の効率化を目的として利用されます。
従来、これらの業務は社内の経理担当者が手作業や会計ソフトを用いて行うのが一般的でした。
しかし、事業の成長に伴い請求件数が増加すると、作業負担は飛躍的に増大し、ミスが発生するリスクも高まります。
また、2023年10月から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応など、法改正に伴う業務の複雑化も、経理担当者の負担を一層重くしています。
請求書代行サービスは、こうした課題を解決するために、請求業務に特化したシステムと専門のオペレーターを活用して、業務の自動化と標準化を実現します。
企業は、このサービスを利用することで、請求業務にかかる時間と人的リソースを大幅に削減し、より戦略的な財務・経理業務に集中することが可能になります。
請求書代行サービスに依頼できる業務
請求書代行サービスがカバーする業務範囲は非常に広く、企業のニーズに応じて必要な業務だけを選択して依頼することも可能です。
ここでは、請求業務のプロセスに沿って、一般的に依頼できる業務内容を具体的にご紹介します。
請求データの作成・取り込み
請求書を発行するための元となるデータの作成や、既存システムからのデータ取り込みを代行します。
企業は、販売管理システムから出力した売上データや、指定のフォーマットで作成したCSVファイルなどをサービス提供会社に渡すだけで、後の作業を任せることができます。
これにより、手作業での転記ミスなどを防ぎます。
請求書の発行
取り込んだデータをもとに、請求書を自動で作成・発行します。
インボイス制度の要件(適格請求書発行事業者の登録番号、適用税率、消費税額など)を満たしたフォーマットでの発行はもちろん、企業独自のロゴやレイアウトを反映させることも可能です。
発行方法は、従来の紙媒体だけでなく、PDF形式の電子請求書にも対応しています。
請求書の印刷・封入・発送
紙の請求書を発行する場合、最も手間がかかるのがこの物理的な作業です。
サービス提供会社が、請求書の印刷、三つ折り、封筒への封入、そして切手を貼って投函するまでの一連の作業をすべて代行します。
電子請求書の場合は、指定のメールアドレスへの自動送信や、Web上で請求書をダウンロードできる専用ポータルへのアップロードなどを代行します。
入金管理(入金消込)
取引先からの入金があった際に、どの請求に対する入金なのかを一つひとつ確認し、債権を消していく「入金消込」という作業を代行します。
多くのサービスでは、振込名義と請求情報を自動で照合するシステムや、各取引先に専用の仮想口座を割り当てる仕組みを用いて、この煩雑な作業を効率化・自動化します。
これにより、消込作業の負担とミスを大幅に削減できます。
未入金時の督促
支払期日を過ぎても入金が確認できない取引先に対して、電話やメール、ハガキなどで支払いを促す督促業務を代行します。
この業務は、取引先との関係性を損なわないよう配慮が必要なため、精神的な負担が大きい業務です。
専門のオペレーターが、企業の代わりに丁寧かつ効果的に督促を行うことで、担当者の負担を軽減し、未回収金の発生を防ぎます。
与信管理・決済代行・入金保証
より高度なサービスとして、これらの機能を提供しているものもあります。
与信管理:新規取引先の支払い能力を調査し、取引を開始して問題ないかを審査します。
決済代行:サービス提供会社が企業の代わりに代金を受け取り、後日まとめて企業に入金します。
入金保証:万が一、取引先が倒産などで支払い不能になった場合でも、サービス提供会社がその代金を100%保証してくれます。
これにより、貸し倒れリスクを完全に無くすことができます。
請求書代行サービスを活用するメリット
請求書代行サービスを導入することは、単に業務が楽になるだけでなく、経営全体に多くの好影響をもたらします。
ここでは、企業が享受できる4つの大きなメリットを解説します。
メリット1:業務効率化による生産性の向上
最大のメリットは、請求業務にかかっていた時間と労力を大幅に削減できることです。
請求書の作成、印刷、封入、発送、入金確認といった一連の定型作業から経理担当者が解放されることで、月次決算の早期化、資金繰り分析、経営資料の作成といった、より分析的で付加価値の高い「コア業務」に集中できるようになります。
これにより、経理部門全体の生産性が向上し、経営の意思決定をサポートする戦略的な役割を担うことが可能になります。
メリット2:ヒューマンエラーの防止と業務品質の向上
手作業による請求書作成や入金消込は、金額の入力ミスや宛先の間違い、消込漏れといったヒューマンエラーが発生しやすい業務です。
請求に関するミスは、取引先からの信用を損なうだけでなく、入金遅延の原因にもなります。
請求書代行サービスは、システム化・自動化されたプロセスで業務を遂行するため、人為的なミスを限りなくゼロに近づけることができます。
これにより、業務品質が安定し、取引先との円滑な関係を維持することに繋がります。
メリット3:コストの削減
一見、外部への委託費用がかかるように思えますが、総合的に見るとコスト削減につながるケースが多くあります。
請求業務を内製化する場合、担当者の人件費はもちろんのこと、請求書の用紙代、封筒代、郵送費、会計ソフトやシステムの維持費など、様々なコストが発生しています。
請求書代行サービスを利用すれば、これらのコストをまとめて削減できます。
とくに、請求件数の増加に伴って新たな人員を採用することを考えれば、アウトソーシングの方が費用を安く抑えられる可能性が高いです。
メリット4:キャッシュフローの改善と未回収リスクの低減
請求業務において重要なのが、発行した請求書代金を確実に回収することです。
入金遅延や貸し倒れは、企業のキャッシュフローを直接的に悪化させます。
請求書代行サービスは、体系化されたプロセスで遅延なく督促業務を行うため、入金遅延の発生を抑制します。
さらに、入金保証サービスが付帯しているものであれば、万が一取引先が倒産しても代金が100%保証されるため、未回収リスクを完全に排除し、安定した資金繰りを実現できます。
これは、経営の安定化に大きく貢献します。
>経費精算をアウトソーシングするメリットに関する記事はこちら
請求書代行サービスを活用するデメリット
多くのメリットがある一方で、請求書代行サービスの導入にはいくつかのデメリットや注意点も存在します。
これらを事前に理解し、対策を講じることが導入成功の鍵となります。
デメリット1:導入・運用コストが発生する
当然のことながら、サービスを利用するには費用がかかります。
料金体系はサービスによって異なりますが、一般的には初期費用や月額基本料金、請求書1件あたりの従量課金が発生します。
毎月の請求件数が非常に少ない企業の場合、内製化するよりも費用が高くついてしまう可能性があります。
自社の請求業務にかかっている人件費や経費を算出し、サービスの利用料金と比較して、費用対効果を慎重に検討する必要があります。
デメリット2:情報漏洩のリスク
請求業務を外部に委託するということは、取引先の企業名や担当者名、取引金額といった重要な情報を外部の業者に預けることを意味します。
委託先のセキュリティ対策が不十分な場合、これらの情報が外部に漏洩するリスクはゼロではありません。
情報漏洩は、自社だけでなく取引先にも多大な迷惑をかけ、企業の信用を著しく損ないます。
委託先を選定する際には、セキュリティ体制が万全であることを厳しく確認することが不可欠です。
デメリット3:社内に請求業務のノウハウが蓄積されない
請求業務のプロセスをすべて外部に委託してしまうと、その業務に関する詳細な知識や、トラブル対応の経験といったノウハウが社内に蓄積されにくくなります。
将来的に事業の方向転換などで内製化を検討する際に、一から業務フローを構築し直す必要が生じる可能性があります。
また、取引先から請求内容に関する特殊な問い合わせがあった場合に、社内で即座に回答できず、委託先への確認に時間がかかることも考えられます。
デメリット4:既存の業務フローの変更が必要になる
請求書代行サービスを導入するにあたり、多くの場合、サービス提供会社が指定するシステムや業務フローに自社のやり方を合わせる必要があります。
たとえば、請求データの受け渡し形式を統一したり、社内の承認プロセスを見直したりする必要が出てくるかもしれません。
経理部門だけでなく、営業部門など関連部署の協力も必要となるため、導入前に関係者への十分な説明と理解を得ることが重要です。
請求書代行サービスの活用が向いている企業
請求書代行サービスは、以下のような課題や特徴を持つ企業にとって、大きな効果が期待できます。
毎月の請求件数が多い企業
請求件数が多ければ多いほど、手作業による業務の負担とミスのリスクは増大します。
月に数十件、数百件以上の請求書を発行している企業であれば、アウトソーシングによる業務効率化とコスト削減のメリットを最大限に享受できるでしょう。
とくに、卸売業や小売業、人材派遣業など、取引先が多く請求業務が煩雑になりがちな業種に適しています。
経理担当者が不足している、または兼任している企業
専任の経理担当者を置くことが難しい中小企業や、経営者自身が経理を兼任しているスタートアップなど、バックオフィスに十分なリソースを割けない企業にとって、請求書代行サービスは強力な味方となります。
少ない人員でも、大企業と同等の正確で効率的な請求業務フローを構築することができ、従業員は本来のコア業務に専念することができます。
請求業務の属人化に課題を抱えている企業
「請求業務は特定のベテラン社員しか分からない」という属人化した状態は、その担当者の休職や退職によって業務が停止してしまうという経営上の大きなリスクを抱えています。
請求書代行サービスを導入し、業務を標準化・仕組化することで、このような属人化のリスクを解消し、持続可能で安定した業務体制を構築することができます。
未回収金が多く、督促業務に課題を感じている企業
支払いの遅延や貸し倒れが多く、キャッシュフローの悪化に悩んでいる企業にとって、督促業務や入金保証までをカバーする請求書代行サービスは非常に有効です。
専門家による適切な督促は回収率を高め、入金保証サービスを利用すれば未回収リスクをゼロにすることができます。
そのため、営業担当者が督促業務に時間を取られることなく、安心して新規顧客の開拓に集中できるというメリットも生まれます。
サブスクリプションモデルの事業を展開する企業
SaaSビジネスやコンテンツ配信、月謝制のスクールなど、毎月定額の請求が多数発生するサブスクリプション型のビジネスモデルを持つ企業にも、請求書代行サービスは最適です。
多くのサービスは、顧客管理システムと連携し、毎月の継続的な請求を自動化する機能を提供しているため、請求業務の手間を大幅に削減できます。
請求書代行サービスの料金相場
請求書代行サービスを導入する上で、最も重要な判断材料のひとつが料金です。
料金体系やその相場は、提供されるサービスの内容や範囲によって大きく異なります。
主な料金体系
多くの請求書代行サービスでは、以下の3つの要素を組み合わせた料金体系が採用されています。
料金 = 初期費用 + 月額基本料金 + 従量課金
初期費用:導入時にアカウント設定やシステム連携などの作業に対して発生する一度きりの費用です。
月額基本料金:システムの利用料や基本的なサポート費用として、毎月固定で発生する費用です。
請求件数が少なくても発生します。
従量課金:発行した請求書の件数に応じて発生する費用です。
「請求書1件あたり〇円」という形で計算されます。
料金相場の目安
具体的な料金はサービスによって様々ですが、一般的な相場は以下の通りです。
【初期費用】
相場:0円 ~ 10万円程度
キャンペーンなどで無料になる場合や、高機能なサービスでは20万円以上かかる場合もあります。
【月額基本料金】
相場:0円 ~ 5万円程度
請求書発行のみのシンプルなサービスでは無料のプランもありますが、多くの機能を利用する場合は月額1万円以上が目安となります。
【従量課金(請求書1件あたりの費用)】
発行方法によって費用が大きく異なります。
| 発行方法 | 1件あたりの費用相場 |
|---|---|
| 請求書の郵送代行 | 150円 ~ 300円 |
| 電子請求書の発行(メール送信・Web発行) | 0円 ~ 150円 |
郵送の場合は、用紙代、印刷代、封筒代、郵送料がすべて含まれています。
【オプション料金】
督促代行や決済代行、入金保証などの付加サービスを利用する場合は、別途オプション料金がかかります。
決済代行手数料:請求金額の1% ~ 5%程度
入金保証手数料:請求金額の1% ~ 4%程度
たとえば、月に100件の請求書を郵送代行する場合、「初期費用5万円+月額基本料金2万円+(従量課金200円×100件)=初月9万円、次月以降4万円」といった費用感になります。
自社の請求件数や必要な機能を洗い出し、複数のサービスから見積もりを取って比較検討することが重要です。
請求書代行サービスの選び方
数多くの請求書代行サービスの中から、自社に最適なサービスを見つけるためには、どのような点に注目すれば良いのでしょうか。
ここでは、選定で失敗しないためのポイントを解説します。
ポイント1:自社の業務範囲と課題に合っているか
まず、自社が請求業務のどの部分に最も課題を感じているのかを明確にしましょう。
「とにかく請求書の発行と発送の手間をなくしたい」のであれば、発行代行に特化したシンプルなサービスが適しています。
一方で、「未回収金の発生に悩んでいる」のであれば、督促業務や入金保証までをカバーするサービスを選ぶ必要があります。
自社の課題と、サービスが提供する機能の範囲が合致しているかを確認することが、最初のステップです。
ポイント2:セキュリティ対策は万全か
取引先の重要な情報を預けるため、セキュリティ対策の確認は必須です。
信頼性を客観的に判断する指標として、個人情報の適切な取り扱いを証明する「プライバシーマーク(Pマーク)」や、情報セキュリティ管理の国際規格である「ISMS(ISO27001)認証」を取得しているかを確認しましょう。
また、データの暗号化やサーバーの監視体制など、具体的なセキュリティ対策についてウェブサイトや資料で明記しているサービスは信頼性が高いと言えます。
ポイント3:料金体系は明確で費用対効果が見合っているか
料金の安さだけで選ぶのではなく、その料金にどこまでのサービスが含まれているのかを詳細に確認することが重要です。
初期費用、月額基本料金、従量課金の単価に加え、オプション料金の有無や最低利用期間などをすべて把握した上で、年間のトータルコストを試算しましょう。
その上で、削減できる人件費や郵送費などのコストと比較し、十分な費用対効果が得られるかを慎重に判断してください。
ポイント4:既存の会計システムなどと連携できるか
現在、社内で会計ソフトや販売管理システムを利用している場合、それらのシステムとスムーズに連携できるかは非常に重要なポイントです。
API連携やCSVファイルの取り込みに対応しているサービスであれば、請求データを手作業で二重入力する必要がなく、業務全体を効率化できます。
連携可能なシステムの種類や、連携のスムーズさについて、導入前に必ず確認しましょう。
ポイント5:サポート体制は充実しているか
導入時の初期設定や、運用開始後に不明な点やトラブルが発生した際に、迅速で丁寧なサポートを受けられるかどうかも重要な選定基準です。
電話やメール、チャットなど、問い合わせ手段が複数用意されているか、対応時間は自社の営業時間と合っているかなどを確認しましょう。
導入事例や利用者の評判を参考に、サポートの質を見極めるのも有効です。
【比較】請求書代行サービス10選
ここでは、実績が豊富で信頼性の高い請求書代行サービス(クラウドサービス、システムも含む)を10個厳選してご紹介します。
請求まるなげロボ(株式会社ROBOT PAYMENT):請求業務を文字通り「まるなげ」できるサービス。
与信から決済、督促まで一括代行し、100%の入金保証が特徴。
マネーフォワード 掛け払い(マネーフォワードケッサイ株式会社):与信審査から入金保証までをカバー。
大手マネーフォワードグループの安心感と、スタートアップにも導入しやすい柔軟性が魅力。
NP掛け払い(株式会社ネットプロテクションズ):未回収リスクを100%保証する企業間後払い決済サービス。
BtoB取引における決済周りの業務を幅広く代行。
Paid(株式会社ラクーンフィナンシャル):請求業務と未払い時の代金保証をセットで提供。
とくに中小企業や個人事業主向けの取引に強い。
BtoBプラットフォーム 請求書(株式会社インフォマート):電子請求書の発行・受取に特化した国内シェアNo.1クラスのサービス。
発行だけでなく、受け取り側の業務も効率化できる。
楽楽明細(株式会社ラクス):請求書や納品書、支払明細など、あらゆる帳票を電子化して発行できるクラウドサービス。
郵送代行にも対応し、発行業務の自動化に強み。
Misoca(弥生株式会社):小規模事業者や個人事業主に人気のクラウド請求書作成サービス。
作成から郵送代行、入金管理までをシンプルかつ低コストで実現。
請求管理ロボ(株式会社ROBOT PAYMENT):請求書の自動発行・自動送付から、カード決済や口座振替などの決済手段連携、自動消込、未収催促までを一元管理できる。
invox発行請求書(株式会社invox):請求データを取り込むだけで、請求書の発行、印刷、封入、投函、および入金消込、督促まで実施可能なシステム。
ビリングサービス(NTTファイナンス株式会社):NTTグループの法人向けサービス。
請求から回収、顧客管理まで、大規模な請求業務にも対応可能。
請求書関連業務の代行なら『Chatwork 経理アシスタント』がおすすめ!
「請求書の発行システムは導入したけれど、その元となる請求データの作成や、発行後の入金確認といった作業がまだ負担になっている」。
このように、システムだけでは解決しきれない、手作業の部分に課題を感じている企業も多いのではないでしょうか。
そんな企業におすすめしたいのが、日々の経理業務をオンラインで幅広くサポートしてくれる『Chatwork 経理アシスタント』です。
このサービスは、請求書の発行・送付そのものを専門に行うサービスとは少し異なります。
その前後の工程である、請求書発行に必要な売上データの集計や請求リストの作成、さらには発行後の入金確認や会計ソフトへの入力といった、人手を要する細かな業務を、専門のオンラインアシスタントが代行してくれるサービスです。
請求書発行システムと『Chatwork 経理アシスタント』を組み合わせることで、請求業務全体の自動化と効率化を、より高いレベルで実現することができます。
経理担当者を新たに採用することなく、必要な業務を必要な分だけ、低コストで依頼できるのが大きな特徴です。
Chatwork 経理アシスタントを導入するメリット
『Chatwork 経理アシスタント』を活用することで、請求業務の効率化はもちろん、経理部門全体の生産性を向上させることができます。
以下、具体的なメリットを3つご紹介します。
メリット1:システムだけでは自動化できない業務から解放される
請求書発行システムは、データがあれば自動で請求書を作成・送付してくれます。
しかし、その元となる「どの取引先に、いくらの請求を行うか」というデータを作成するのは、依然として人手が必要です。
『Chatwork 経理アシスタント』は、この最も手間のかかるデータ作成の部分を代行します。
また、発行後の入金確認といったシステム化しにくい業務も任せられるため、担当者は定型的な作業から完全に解放されます。
メリット2:月額数万円からの低コストで経理サポート体制を構築できる
経理担当者を一人採用すれば、月々数十万円の人件費がかかります。
『Chatwork 経理アシスタント』は、月額3万円台からというリーズナブルな料金で、プロの経理サポートを受けることができます。
月々の実働時間に応じたプランが用意されているため、事業規模や業務量に合わせて無駄なく利用を開始できます。
コストを抑えながら経理体制を強化したい企業にとって、費用対効果が非常に高い選択肢です。
メリット3:請求業務以外の経理業務も柔軟に依頼できる
『Chatwork 経理アシスタント』の強みは、その柔軟性です。
請求関連業務だけでなく、契約時間内であれば、領収書の整理や経費精算、記帳代行といった、他の経理業務も合わせて依頼することができます。
「今月は請求業務に加えて、溜まっている領収書の整理もお願いしたい」などのように、状況に応じた依頼が可能であるため、経理部門全体の業務を平準化し、特定の時期に業務が集中することを防げます。
まとめ
本記事では、請求書代行サービスについて、その業務範囲から料金相場、メリット・デメリット、そして成功のための選び方までを網羅的に解説しました。
請求書代行サービスの活用は、ヒューマンエラーを削減し、キャッシュフローを安定させ、社内の貴重なリソースをより創造的で付加価値の高い業務に再配分するために効果的です。
インボイス制度への対応など、経理業務がますます複雑化する状況下で、ぜひ自社に合うサービスを見つけてみてください。