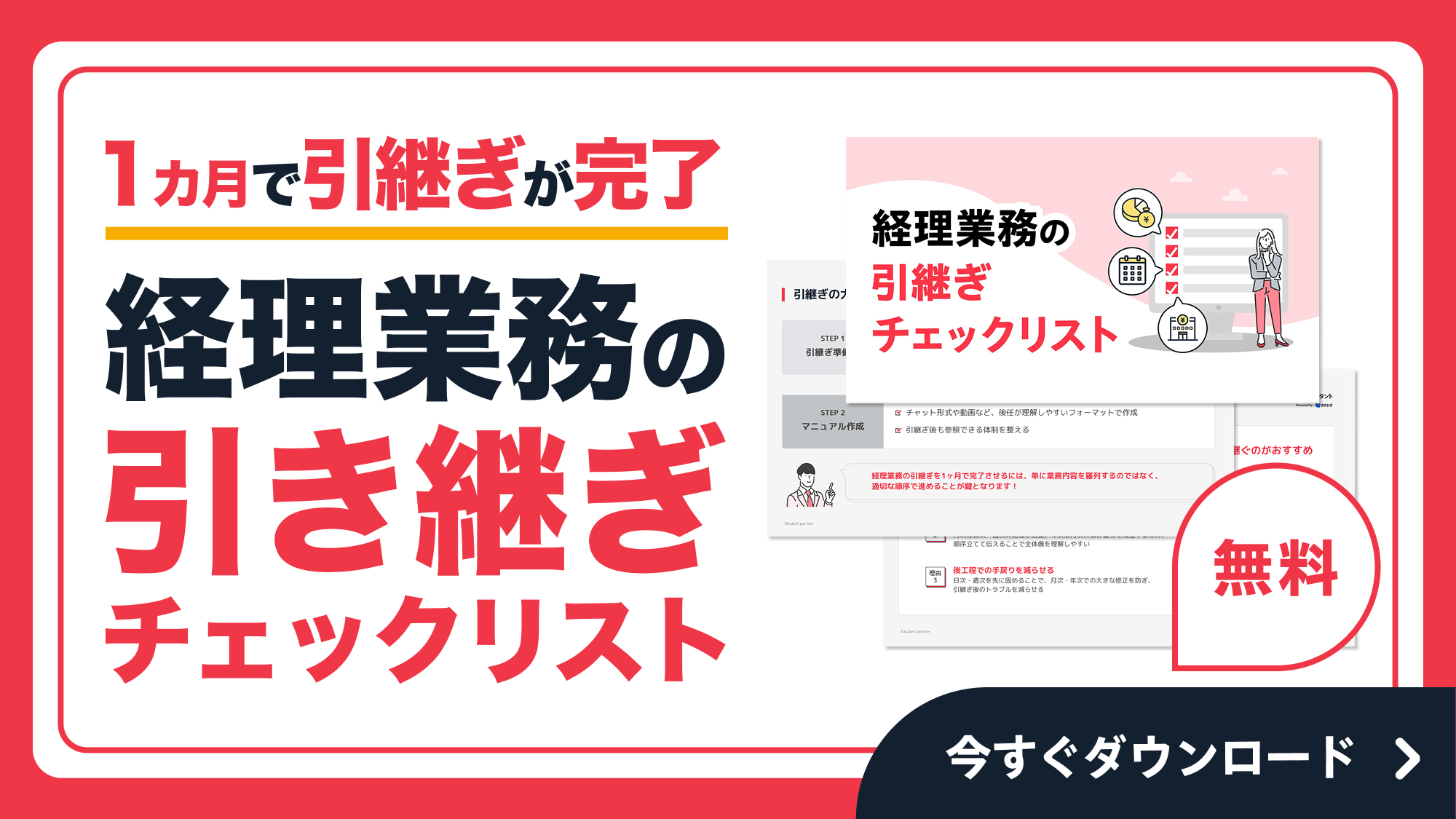領収書関連業務の代行サービスとは?費用相場や選び方、依頼が難しいケースなどを解説

終わらない!

- リリースからわずか2年で
累計1000社以上が採用したサービス - 厳選された優秀なアシスタントが支援
- あらゆる経理業務を専門チームが代行
- 人手不足を解決し、安定した経理体制へ

目次
企業活動においては、日々大量の領収書が発生します。
経費精算や会計処理のために不可欠な証憑ですが、領収書の管理業務は多くの企業にとって大きな負担となっています。
この記事では、領収書関連業務の代行に関する基本知識、依頼できる業務範囲、依頼先、気になる費用相場、そして自社に最適なサービスを選ぶためのポイントなどを詳しく解説します。
領収書関連業務の代行とは
領収書関連業務の代行とは、企業の日々の経済活動で発生する領収書の受け取り、整理、スキャニング、会計ソフトへのデータ入力、そして法律の要件に沿った保管などといった業務を、外部の専門業者が代わりに行うサービスのことです。
従来、これらの業務は社内の経理担当者が手動で行うことが一般的でした。
しかし、手作業は多くの時間と労力を要するだけでなく、入力ミスや紛失といったヒューマンエラーのリスクを伴います。
また、近年は、電子帳簿保存法の改正により、電子取引によって受け取った領収書は原則として電子データのまま保存することが義務付けられるなど、法的な要件も複雑化しています。
領収書関連業務の代行サービスでは、専門的な知識を持つスタッフがシステムを活用し、領収書に関わる業務を正確かつ迅速に処理します。
そのため、法改正への対応という課題をクリアしつつ、バックオフィス業務の生産性向上も期待できます。
代行を依頼できる領収書関連業務の種類
領収書関連業務の代行サービスがカバーする業務範囲は非常に広く、企業のニーズに応じて必要な部分だけを依頼することも可能です。
ここでは、一般的に依頼できる領収書関連業務の種類を、処理のプロセスに沿ってご紹介します。
1. 領収書の受領・回収
従業員が立て替えた経費の領収書や、取引先から送られてくる領収書を、受け取る業務です。
従業員がスマートフォンで撮影して提出したり、専用の封筒で郵送して提出したりする領収書を、代行業者が直接回収します。
2. 領収書の整理・スキャニング
回収した紙の領収書を日付や勘定科目ごとに整理し、スキャナで読み取って電子データ化する業務です。
電子帳簿保存法のスキャナ保存要件(解像度、タイムスタンプの付与など)を満たした形で、正確にデータ化を行います。
電子取引で受領した領収書データについても、同様に法要件に沿って整理・リネームなどを行います。
3. データ入力(記帳代行)
スキャンした領収書の内容(日付、支払先、金額、勘定科目など)を読み取り、会計ソフトや経費精算システムへ正確に入力する業務です。
AI-OCR(人工知能を用いた光学的文字認識)技術と、専門オペレーターによる目視確認を組み合わせることで、高速かつ高精度なデータ入力を実現します。
これは「記帳代行」の中核をなす業務といえます。
4. 経費精算業務の代行
従業員から提出された領収書と経費精算申請書の内容を照合し、社内規定と照らし合わせて内容をチェックする業務です。
承認された経費については、振込データを作成し、従業員の口座へ振り込むまでの処理を代行するサービスもあります。
5. 領収書の保管・管理
データ化した後の紙の領収書の原本や、電子領収書のデータを、法律で定められた期間(原則7年間)、適切な方法で保管・管理する業務です。
原本の保管については、セキュリティが確保された専門の倉庫で保管し、必要に応じて原本を取り寄せられるサービスもあります。
電子データについては、検索要件などを満たしたシステム上で安全に管理されます。
領収書関連業務の代行料金相場
領収書関連業務の代行を検討する上で、最も重要な判断材料の1つが費用です。
料金体系やその相場は、依頼する業務範囲や領収書の枚数、依頼先によって大きく異なります。
主な料金体系
料金体系は、主に以下の3つのタイプに分けられます。
1. 従量課金制(領収書1枚あたり)
処理した領収書の枚数に応じて料金が計算される、最も分かりやすい体系です。
「領収書1枚のデータ入力につき〇円」といった形で、使った分だけ支払います。
毎月の領収書枚数が変動する企業や、特定の繁忙期だけ依頼したい場合に適しています。
2. 月額固定制
「月間〇枚までの領収書処理で、月額〇円」といった形で、毎月一定の料金を支払う契約形態です。
毎月のコストが安定するため予算管理がしやすいですが、上限枚数を超えると追加料金が発生します。
月々の領収書枚数が、ある程度安定している企業に適しています。
3. 時間単価制(オンラインアシスタント型)
オンラインアシスタントサービスなどで見られる形態で、アシスタントの実働時間に基づいて料金が計算されます。
「月20時間で〇円」といったスタイルの契約で、決められた時間内であれば、領収書業務に限らず幅広い業務を柔軟に依頼できるのが特徴です。
料金相場の目安
具体的な料金はサービスによって様々ですが、一般的な相場は以下の通りです。
【従量課金制の場合】
領収書のデータ入力(1枚あたり):50円 ~ 100円程度
勘定科目の仕訳まで依頼する場合は、1仕訳あたり80円~150円程度が相場です。
【月額固定制の場合】
料金は月間の処理枚数によって変動します。
| 月間領収書枚数 | 月額費用の相場 |
|---|---|
| ~50枚 | 1万円 ~ 2万円 |
| ~100枚 | 2万円 ~ 3.5万円 |
| ~200枚 | 3.5万円 ~ 5万円 |
※上記はデータ入力(記帳代行)が中心の料金です。
経費精算の承認作業や原本保管などが含まれると、料金は加算されます。
【時間単価制の場合】
オンラインアシスタント(1時間あたり):2,500円 ~ 4,500円程度
月々の最低契約時間が定められていることが一般的です(例:月10時間~)。
これらに加えて、初期費用(0円~10万円程度)が必要となる場合があります。
自社の月間平均枚数や必要な業務範囲を基に、複数の依頼先から見積もりを取り、比較検討することが重要です。
【注意】代行依頼が難しいケースとは
多くの領収書関連業務は代行可能ですが、中には依頼が難しいケース、または、外注がかえって非効率になるケースも存在します。
領収書の状態が著しく悪い場合
破れている領収書や、印字が極端に薄くて判読不能な領収書は、正確なデータ化が困難なため、代行を断られたり、追加料金を請求されたりすることがあります。
また、感熱紙のレシートを長期間放置し、印字が消えてしまっているような場合も同様です。
日頃から領収書を丁寧に扱うことが、スムーズな代行依頼の前提となります。
社内ルールが複雑すぎる、または整備されていない場合
経費精算のルールが非常に複雑であったり、勘定科目の仕訳ルールが担当者の頭の中にしかなく、明文化されていなかったりする場合、外部の業者が正確に処理を行うことは困難です。
代行を依頼する前に、業務マニュアルの整備やルールの簡素化・標準化といった、社内での準備が必要不可欠です。
ルールが曖昧なまま依頼すると、業者からの問い合わせが頻発し、かえって業務が非効率になる可能性があります。
即時の判断や確認が必要な業務
領収書の内容について、「これはどのプロジェクトの経費か」「この交際費の参加者は誰か」といった、担当者でなければ分からない確認作業が頻繁に発生する場合、すべてを外部に委託するのは難しいでしょう。
データ入力は代行業者に任せ、最終的な内容確認や承認は社内で行うなど、業務の役割分担を明確にすることが求められます。
完全な丸投げはできないケースであると認識しておくことが重要です。
領収書関連業務の代行依頼先
領収書関連業務の代行を依頼できる先は、主に3つの種類に分けられます。
それぞれの特徴を理解し、自社の目的や予算に合った依頼先を選びましょう。
1. 税理士事務所・会計事務所
【サービス内容・範囲】
記帳代行の一環として、領収書のデータ入力や整理を行います。
最大の強みは、単なる入力作業に留まらず、税務の専門家として適切な勘定科目の仕訳や、消費税の区分判定(軽減税率など)を正確に行ってくれる点です。
最終的な確定申告や決算業務まで、一気通貫で依頼することができます。
【料金】
月々の顧問契約料(目安:月額2万円~)に含まれる形や、記帳代行料(目安:月額1万円~)として別途請求される形が一般的です。
他の依頼先に比べて料金は高くなる傾向がありますが、税務相談や節税アドバイスまで受けられるという付加価値があります。
【向いている企業】
専門的な税務判断が必要な企業や、税務顧問を探している企業、決算・申告までまとめて依頼したい企業に適しています。
2. 記帳代行・経理代行会社
【サービス内容・範囲】
領収書のデータ入力(記帳代行)を専門に請け負う会社です。
税理士事務所と異なり、税務相談や申告代行といった税理士の独占業務は行えません。
その分、データ入力作業に特化しており、大量の領収書を効率的かつ比較的安価に処理するノウハウを持っています。
経費精算代行までの範囲を依頼できる会社もあります。
【料金】
月額固定制(目安:月額1万円~)や、従量課金制(目安:1仕訳80円~)が中心です。
税理士事務所に依頼するよりも費用を抑えられることが多いです。
【向いている企業】
「すでに顧問税理士はいるが、日々の入力作業の負担を軽減したい」という企業や、とにかく大量のデータ入力を効率化したい企業に適しています。
3. オンラインアシスタントサービス
【サービス内容・範囲】
オンライン上で、経理を含む様々なバックオフィス業務をサポートしてくれるサービスです。
領収書のデータ入力や経費精算チェックはもちろん、契約時間内であれば、請求書発行や支払い業務、総務・人事関連の雑務まで、幅広い業務を柔軟に依頼できるのが最大の特徴です。
【料金】
時間単価制(目安:1時間2,000円~)で、月々の実働時間に応じた月額料金(目安:月額5万円~)を支払うのが一般的です。
【向いている企業】
専任の経理担当者を置くほどではないが、幅広いバックオフィス業務をサポートしてほしいスタートアップや中小企業に最適です。
業務量の変動に合わせて、柔軟に依頼内容を変えたい企業にも適しています。
領収書関連業務の代行を依頼するメリット
領収書関連の煩雑な業務を外部に委託することは、企業に多くのメリットをもたらします。
メリット1:コア業務への集中と生産性向上
最大のメリットは、経理担当者や経営者を、時間のかかる単純作業から解放することです。
領収書の整理や入力に費やしていた時間を、資金繰りの計画、財務分析、経営戦略の立案といった、企業の成長に直結する、より付加価値の高いコア業務に振り分けることができます。
結果として、経理部門が経営を支える戦略的部門へと進化し、企業全体の生産性向上が期待できます。
メリット2:業務の正確性向上とミスの削減
手作業でデータ入力を行う場合、どれだけ注意していても入力ミスや計上漏れといったヒューマンエラーを完全になくすことは困難です。
代行サービスでは、AI-OCRと専門オペレーターによる二重チェック体制など、ミスを防止するための仕組みが構築されています。
プロに任せることで、業務の正確性が飛躍的に向上し、月次決算の早期化や、税務調査の際にも信頼性の高いデータを提供できるという安心感につながります。
メリット3:コスト削減
経理担当者を新たに1人雇用する場合、給与や社会保険料だけでなく、採用コストや教育コスト、福利厚生費など、多くの費用が発生します。
代行サービスを利用すれば、これらの費用をかけずに、必要な分だけ業務を委託できます。
特に、業務量に波がある場合や、専任者を置くほどの業務量がない企業にとっては、人件費を固定費から変動費に変えることができ、トータルコストを大幅に削減できる可能性があります。
メリット4:法改正への迅速な対応
近年、電子帳簿保存法やインボイス制度など、経理業務に関連する法改正が頻繁に行われています。
これらの最新情報を自社だけで収集し、正しく対応していくのは大きな負担です。
専門の代行サービスは、常に最新の法令に準拠した形で業務を遂行します。
サービスを利用することで、法改正対応の負担や、対応漏れのリスクから解放され、コンプライアンスを遵守した適切な経理体制を維持することができます。
領収書関連業務の代行を依頼するデメリット
多くのメリットがある一方で、代行サービスの導入にはいくつかのデメリットや注意点も存在します。
デメリット1:導入・運用費用がかかる
当然のことながら、外部のサービスを利用するには費用が発生します。
毎月の領収書枚数が極端に少ない場合や、社内に十分なリソースがある場合には、自社で処理する方がコストを抑えられる可能性もあります。
自社の業務にかかる人件費や時間を算出し、代行サービスの費用と比較して、費用対効果を慎重に見極める必要があります。
デメリット2:情報漏洩のリスク
領収書には、取引先の情報や交際費の内容など、社外秘の情報が含まれている場合があります。
これらの情報を外部に預けることになるため、委託先のセキュリティ管理体制が不十分な場合、情報漏洩のリスクはゼロではありません。
企業の信用問題に関わるため、依頼先のセキュリティ対策は厳しくチェックすることが不可欠です。
デメリット3:社内にノウハウが蓄積されにくい
領収書処理の業務プロセスをすべて外部に委託してしまうと、その業務に関する詳細な知識や、イレギュラーな事態への対応経験といったノウハウが社内に蓄積されにくくなります。
将来的に内製化を検討する際に、一から体制を構築し直す必要が生じる可能性があります。
完全に任せきりにするのではなく、定期的に業務フローの報告を受けるなど、社内でも状況を把握しておくことが望ましいです。
デメリット4:コミュニケーションコストの発生
外部の業者と連携するため、一定のコミュニケーションコストが発生します。
領収書の受け渡し方法の確認や、内容に関する問い合わせへの回答など、社内であれば不要なやり取りが生じます。
また、イレギュラーな処理を依頼したい場合に、すぐに対応してもらえないなど、柔軟性に欠ける場合もあります。
円滑な連携を図るための、明確なコミュニケーションルールの設定が必要です。
領収書関連業務の代行依頼先の選び方
自社に最適な代行サービスを見つけるためには、どのような点に注目すれば良いのでしょうか。
ここでは、依頼先選定で失敗しないための5つのポイントを解説します。
ポイント1:電子帳簿保存法への対応
現在の経理業務において、これは最も重要なチェックポイントの1つです。
依頼先が、改正された電子帳簿保存法の要件(特にスキャナ保存と電子取引)に完全に対応したシステムと業務フローを持っているか、必ず確認しましょう。
法要件を満たさない方法で処理されてしまうと、税務上のリスクを負うことになります。
JIIMA認証(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会による認証)を取得しているシステムを利用しているサービスは、信頼性が高いといえます。
ポイント2:セキュリティ対策の信頼性
情報漏洩のリスクを回避するため、依頼先のセキュリティ体制は厳しくチェックしましょう。
客観的な指標として、プライバシーマーク(Pマーク)やISMS(ISO27001)認証の取得状況を確認します。
また、秘密保持契約(NDA)の締結はもちろんのこと、データの暗号化やアクセス管理、物理的な書類の保管方法など、具体的な対策について明確に説明を求めましょう。
ポイント3:自社の会計ソフトとの連携
現在利用している、または将来的に利用したい会計ソフトと、代行サービスがスムーズに連携できるかは、業務効率を大きく左右します。
データ入力後の仕訳データを、API連携やCSVファイルのインポート機能で、簡単に会計ソフトに取り込めるかを確認しましょう。
二重入力の手間が発生しない、シームレスな連携が可能なサービスを選ぶことが重要です。
ポイント4:料金体系の明確さと費用対効果
料金の安さだけで判断せず、その料金にどこまでの業務が含まれているのか、内訳を詳細に確認することが重要です。
初期費用、月額基本料金、従量課金の単価に加え、最低利用期間や追加料金が発生するケースなどをすべて把握した上で、年間の総費用を試算しましょう。
その上で、自社で得られるメリットと比較し、納得できる費用対効果かを見極めてください。
ポイント5:サポート体制と柔軟性
導入時の設定サポートや、運用開始後の問い合わせに、迅速かつ丁寧に対応してくれるサポート体制が整っているかを確認しましょう。
また、自社の成長や状況の変化に応じて、依頼する業務量や内容を柔軟に変更できるかも大切なポイントです。
トライアル期間などを活用して、実際の対応品質を確認するのも有効な手段です。
領収書関連業務の代行を依頼する際の注意点
最適なサービスを選んだとしても、依頼する側の準備や認識が不足していると、期待した効果が得られない場合があります。
代行依頼を成功させるための注意点を3つご紹介します。
注意点1:社内ルールを整備し、明確に伝える
代行サービスは、依頼元の企業のルールに基づいて業務を遂行します。
そのため、経費精算規定や勘定科目の仕訳ルールなどを事前に整備し、マニュアルとして明文化しておくことが不可欠です。
ルールが曖昧なまま依頼すると、業者からの問い合わせが頻発したり、意図しない形で処理されたりして、かえって業務が混乱する原因になります。
誰が見ても判断に迷わない、明確なルール作りを心がけましょう。
注意点2:社内への周知と協力を徹底する
領収書の提出方法や経費精算の申請フローが変更になる場合、その内容を全従業員に事前に周知し、協力を求めることが重要です。
なぜ変更するのかという目的から、具体的な手順の変更点までを丁寧に説明し、問い合わせ窓口を設けるなどして、従業員の混乱を最小限に抑える工夫をしましょう。
従業員の協力なくして、スムーズな運用は実現できません。
注意点3:「丸投げ」にせず、管理体制を維持する
業務を外部に委託した後も、すべてを任せきりにするのは危険です。
代行業者から提出されるデータやレポートの内容を定期的にチェックし、業務が正しく遂行されているかを確認する、社内の管理体制は維持する必要があります。
また、定期的に業者とコミュニケーションを取り、業務上の課題や改善点について協議する場を設けることで、サービスの品質をさらに高めていくことができます。
領収書関連業務の代行依頼なら『Chatwork 経理アシスタント』がおすすめ!
数ある代行サービスの中でも、特に「領収書業務だけでなく、経理全般の細かな業務を柔軟にサポートしてほしい」と考える中小企業やスタートアップにおすすめしたいのが、『Chatwork 経理アシスタント』です。
『Chatwork 経理アシスタント』は、国内利用者数No.1のビジネスチャット「Chatwork」が提供する、オンラインアシスタントサービスです。
領収書の整理やデータ入力、経費精算といった業務はもちろんのこと、請求書発行、支払い管理、記帳代行など、経理に関する幅広い業務を、経験豊富なアシスタントがチームでサポートします。
最大の特徴は、月々の実働時間に応じた料金体系で、必要な時に必要な分だけ、様々な業務を柔軟に依頼できる点です。
「今月は溜まった領収書の整理を集中的にお願いしたい」「来月は請求書発行と入金確認を手伝ってほしい」といった、企業の状況に応じた依頼が可能です。
経理担当者を新たに採用することなく、低コストで質の高い経理サポート体制を構築できます。
Chatwork 経理アシスタントを導入するメリット
『Chatwork 経理アシスタント』を活用することで、企業は具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか。
その独自の強みを3つのポイントに絞ってご紹介します。
メリット1:スマートフォンでの簡単な証憑提出
従業員は、手元の領収書をスマートフォンで撮影し、使い慣れたChatworkアプリで送信するだけで提出が完了します。
アシスタントがその画像を基にデータ入力や経費精算処理を行うため、紙の領収書を会社に持ち帰って提出するという手間がなくなります。
これにより、経費精算の申請漏れを防ぎ、業務のペーパーレス化を促進します。
メリット2:柔軟な業務対応力
『Chatwork 経理アシスタント』の強みは、その対応範囲の広さです。
領収書業務に限定されず、契約した時間内であれば、請求書発行、支払いデータの作成、売掛金・買掛金の管理、さらには月次決算の補助業務まで、経理に関するあらゆる業務を依頼することができます。
1人の担当者に業務が集中しがちな中小企業の経理部門にとって、業務の繁閑に合わせて柔軟にサポートを得られることは大きな利点です。
メリット3:Chatworkによる円滑なコミュニケーション
アシスタントとの業務連絡やデータ共有は、すべてビジネスチャット「Chatwork」で完結します。
領収書の内容について不明な点があれば、アシスタントからチャットで迅速に質問が届き、担当者はすぐに回答できます。
メールのように形式的な文章を作成する手間がなく、タスク管理機能で依頼内容の進捗も可視化できるため、ストレスのない円滑なコミュニケーションが、業務全体のスピードと正確性を高めます。
まとめ
本記事では、領収書関連業務の代行について、その業務範囲から料金相場、メリット・デメリット、そして成功のための選び方などを解説しました。
自社が抱える経理業務の課題を明確にしつつ、ぜひ依頼先探しに役立ててみてください。