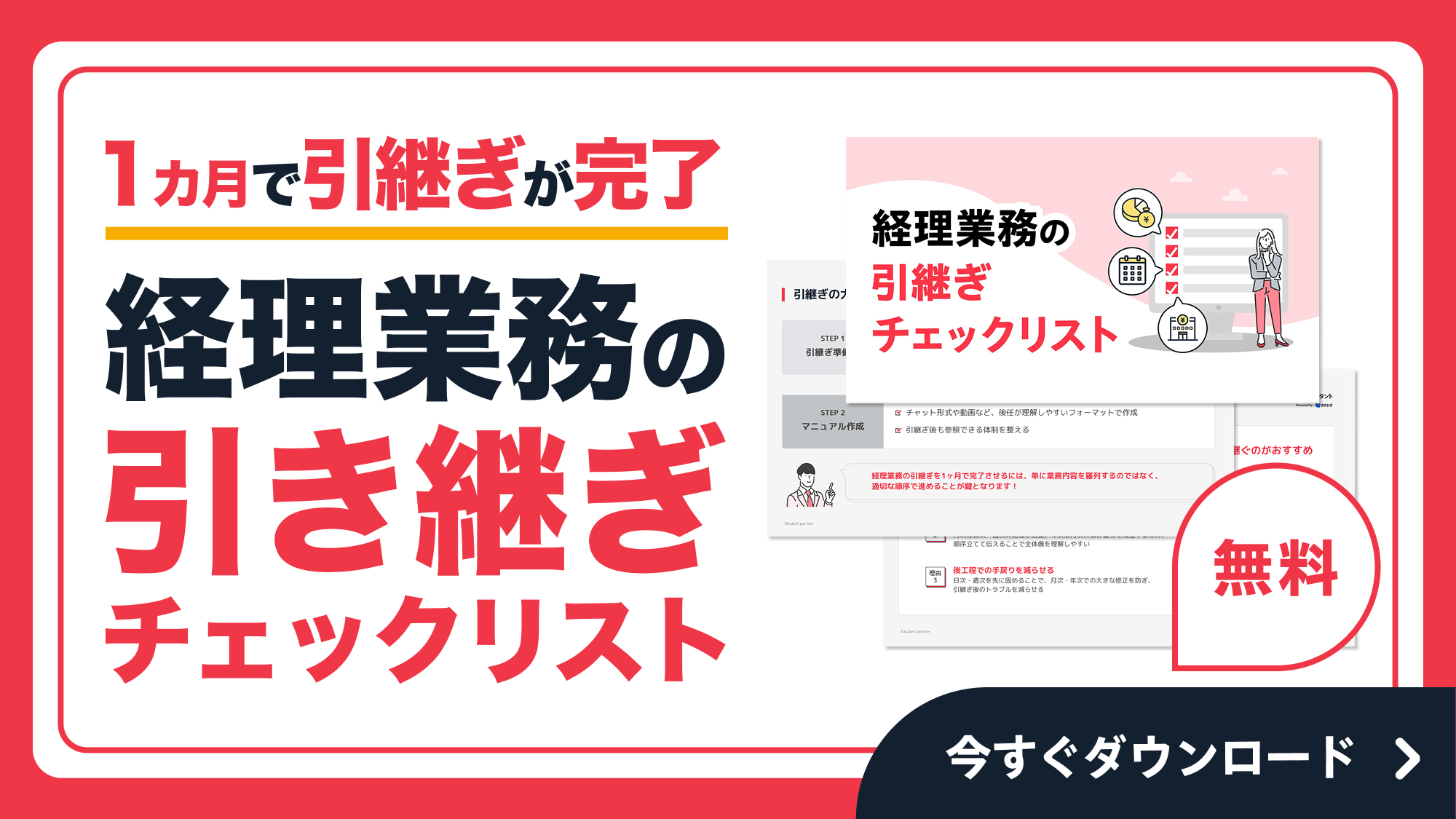【作成例あり】収支決算書の書き方とは?記載項目やチェックポイント、注意点などをわかりやすく解説

終わらない!

- リリースからわずか2年で
累計1000社以上が採用したサービス - 厳選された優秀なアシスタントが支援
- あらゆる経理業務を専門チームが代行
- 人手不足を解決し、安定した経理体制へ

目次
自治会や町内会、PTA、サークル、非営利団体などの運営に携わっている方にとって、年に一度作成が必要となるのが「収支決算書」です。
また、個人事業主が白色申告を行う際に作成する「収支内訳書」も、性質としては収支決算書に近いものと言えます。
これらの書類は、お金の流れを明確にし、関係者へ報告するために作成する必要がありますが、「書き方がよくわからない」「作成が面倒だ」と感じている方も少なくないのではないでしょうか。
この記事では、収支決算書の基本知識や作成する目的、具体的な書き方の手順などを初心者の方にもわかりやすいように解説します。
損益計算書や決算報告書との違い、作成時の注意点なども紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
収支決算書とは
収支決算書とは、特定の期間(通常は1年間)における、組織や個人の「収入」と「支出」をまとめ、最終的に手元に残ったお金(現金および預金)がいくらなのかを示す書類です。
主に、営利を主目的としない団体・組織(町内会、自治会、PTA、マンション管理組合、サークル、同窓会、NPO法人など)において、活動内容や会計状況を会員・関係者へ報告するために作成されます。
収支決算書の大きな特徴は、「現金主義」という考え方に基づいて作成される点です。
現金主義とは、実際にお金が入ってきた時点(収入)と、実際にお金が出ていった時点(支出)の取引を記録・集計する考え方です。
例えば、商品を掛け販売(掛け売り)した場合、発生主義の企業会計では、商品を引き渡した時点で「売上」として計上します。
一方、現金主義の収支決算書では、商品の代金が現金や預金として実際に入金された時点で「収入」として記録します。
個人事業主が白色申告の際に提出する「収支内訳書」も、現金主義に近い考え方で収入と経費を集計するため、広義の収支決算書と捉えることができます。
収支決算書を作成する目的
収支決算書の作成は、単にお金の出入りを記録するだけでなく、組織運営においていくつかの重要な目的を持っています。
1. 活動報告と透明性の確保
収支決算書を作成し、会員や関係者に公開することで、その期間にどのような活動を行い、そのためにいくらのお金(会費や寄付金など)が集まり、何にいくら使ったのかを明確に示すことができます。
お金の流れを透明化することは、組織運営の信頼性を高め、不正行為を防止する上でも重要です。
2. 予算との比較と評価
多くの団体では、年度当初に活動計画と共に予算を策定します。
収支決算書を作成することで、実際に得られた収入と発生した支出が、当初の予算と比べてどうだったのかを比較・評価することができます。
予算通りに活動が進んだのか、あるいは計画外の支出がなかったかなどを検証し、次年度以降の活動計画や予算策定に活かすことができます。
3. 次年度の予算策定の基礎資料
収支決算書は、過去一年間の実績を示す重要なデータです。
この実績データを基に、「来年度はこの活動にこれくらいの費用がかかりそうだ」「会費収入はこれくらい見込めそうだ」といった、現実的な予測を立てることができます。
収支決算書は、次年度の予算をより精度高く策定するための、不可欠な基礎資料となります。
4. 関係者への説明責任
会員から預かった会費や、外部から受けた寄付金などが、どのように使われたのかを明確に示すことは、組織が関係者に対して果たすべき重要な説明責任です。
収支決算書を通じて、資金が適切に、かつ有効に活用されていることを報告することで、関係者からの理解と継続的な支援を得ることにつながります。
収支決算書と損益計算書の違い
企業の決算書で中心的な役割を果たす「損益計算書」と「収支決算書」は、似ているようで性質が異なります。
以下、主な違いを紹介します。
計算の基礎となる考え方(会計原則)の違い
大きな違いは、計算の基礎となる考え方です。
収支決算書は、前述の通り「現金主義」に基づいて作成されます。
つまり、「現金の実際の入出金」があった時点で、収入や支出として記録します。
一方、損益計算書は、「発生主義」という考え方に基づいて作成されます。
発生主義では、現金の入出金に関わらず、「取引や経済活動が発生した時点」で収益や費用を認識します。
例えば、商品を掛けで販売した場合、発生主義では商品を引き渡した時点で「売上(収益)」を計上しますが、現金主義では代金が入金されるまで収入とは認識しません。
目的の違い
収支決算書の主な目的は、「一定期間における現金の増減」を明らかにすることです。
手元のお金がどれだけ増えたか、あるいは減ったかを示します。
一方、損益計算書の目的は、「一定期間における企業の経営成績(儲け)」を明らかにすることです。
収益から費用を差し引いて、利益(または損失)がどれだけ出たかを示します。
どちらが実態に近いか
企業の正確な経営成績を示すという観点では、「発生主義」に基づく損益計算書の方が、より実態に近いと言えます。
なぜなら、掛け取引や減価償却費(現金の支出を伴わない費用)などを考慮しない現金主義では、一時的に現金が多くても、実際には将来支払うべき負債が多いといった状況が見えにくいためです。
収支決算書は、お金の出入りをシンプルに把握するには便利ですが、企業の正確な収益性を測るには限界がある点を理解しておく必要があります。
収支決算書と決算報告書の違い
「収支決算書」と「決算報告書」も、しばしば混同されやすい言葉です。
これらの違いについても整理しておきましょう。
決算報告書とは
決算報告書とは、企業が決算の内容を株主や債権者などの利害関係者に報告するために作成する、一連の書類の総称です。
会社法で作成が義務付けられている「計算書類」(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)や、事業報告書などが含まれます。
つまり、決算報告書は、複数の書類で構成される「報告書のセット」全体を指す言葉です。
収支決算書の位置づけ
収支決算書は、前述の通り、主に非営利団体などで用いられる、現金の収入と支出をまとめた書類です。
NPO法人などの非営利組織では、決算報告書の中に「活動計算書(損益計算書に相当)」や「貸借対照表」と並んで、「収支計算書(収支決算書)」が含まれる場合があります。
この場合の収支計算書は、その団体の資金繰りの状況を示す重要な書類として位置づけられます。
また、個人事業主が白色申告で提出する「収支内訳書」は、確定申告書という報告書の一部であり、収支決算書と同様の役割を果たします。
一方で、株式会社などの一般的な営利企業が作成する決算報告書(計算書類)には、通常、「収支決算書」という名称の独立した書類は含まれません。
現金の動きは「キャッシュフロー計算書」で示されます。
つまり、収支決算書は、特定の組織(非営利団体など)においては決算報告書の一部として重要な役割を担いますが、一般的な企業の決算報告書とは異なる場合が多い、と理解しておくと良いでしょう。
収支決算書の記載項目
収支決算書のフォーマットは、作成する団体によって多少異なりますが、一般的に含まれる基本的な記載項目は共通しています。
表題・基本情報
表題:「収支決算書」「会計報告書」など。
対象期間:いつからいつまでの期間の収支をまとめたものか(例:令和〇年4月1日~令和×年3月31日)。
作成日:書類を作成した日付。
作成者(または報告者):会計担当者の氏名や役職など。
収入の部
その期間中に、どのような理由で、いくらのお金が入ってきたかを記載します。
勘定科目ごとに分けて記載するのが一般的です。
勘定科目:収入の内容を示す項目名(例:会費収入、寄付金収入、事業収入、助成金収入、受取利息、雑収入など)。
摘要(内容):具体的な収入の内容や取引先など(任意で記載)。
金額:科目ごとの収入額。
収入合計:すべての収入科目の合計額。
支出の部
その期間中に、どのような目的で、いくらのお金が出ていったかを記載します。
こちらも勘定科目ごとに分けて記載します。
勘定科目:支出の内容を示す項目名(例:事業費(〇〇事業費)、管理費、人件費、消耗品費、通信費、交通費、支払手数料、会議費、雑費など)。
摘要(内容):具体的な支出の内容や支払先など(任意で記載)。
金額:科目ごとの支出額。
支出合計:すべての支出科目の合計額。
収支差引
当期収支差額:「収入合計」から「支出合計」を差し引いた金額。
その期間の活動の結果、手元のお金がいくら増減したかを示します。
(当期収支差額 = 収入合計 - 支出合計)
繰越金の計算
前期繰越金:前の期間から繰り越された手元資金の残高。
前期の収支決算書の「次期繰越金」の額と一致します。
次期繰越金:当期末に残った手元資金の残高で、次の期間へ繰り越される金額。
「前期繰越金」に「当期収支差額」を加えて計算します。
(次期繰越金 = 前期繰越金 + 当期収支差額)
これらの項目を、表形式などでわかりやすいようにまとめます。
【作成例付き】収支決算書の書き方
ここでは、架空の町内会「さくら町町内会」の収支決算書を作成する例を挙げながら、具体的な書き方の手順をわかりやすく説明します。
前提:
会計期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日
前期からの繰越金:50,000円
期間中の収入・支出は、会計帳簿(現金出納帳や預金出納帳)に記録済み。
ステップ1:会計期間とタイトルを記入する
まず、書類のタイトル(例:「令和6年度 さくら町町内会 収支決算書」)と、対象となる会計期間(例:「自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日」)を明確に記入します。
ステップ2:収入の部の集計と記入
会計帳簿から、期間中のすべての収入を勘定科目別に集計します。
(例)
会費収入:200,000円 (会員100名 × 2,000円)
寄付金収入:30,000円 (さくら商店より)
助成金収入:50,000円 (市からの環境美化助成金)
雑収入:5,000円 (廃品回収収益金)
これらの科目と金額を「収入の部」に記入し、最後に収入合計額を計算します。
収入合計 = 200,000 + 30,000 + 50,000 + 5,000 = 285,000円
ステップ3:支出の部の集計と記入
同様に、会計帳簿から、期間中のすべての支出を勘定科目別に集計します。
(例)
事業費 - 夏祭り費:80,000円 (会場設営、景品代など)
事業費 - 清掃活動費:15,000円 (ゴミ袋、軍手代など)
管理費 - 印刷費:10,000円 (広報誌印刷代)
管理費 - 通信費:5,000円 (連絡用切手代、電話代)
管理費 - 消耗品費:8,000円 (文房具、コピー用紙代)
管理費 - 会議費:12,000円 (役員会お茶代など)
雑費:3,000円 (振込手数料など)
これらの科目と金額を「支出の部」に記入し、最後に支出合計額を計算します。
支出合計 = 80,000 + 15,000 + 10,000 + 5,000 + 8,000 + 12,000 + 3,000 = 133,000円
ステップ4:当期収支差額の計算と記入
「収入合計」から「支出合計」を差し引いて、当期収支差額を計算します。
当期収支差額 = 285,000円 - 133,000円 = 152,000円
この金額を記入します。
ステップ5:繰越金の計算と記入
まず、「前期繰越金」として、前期から引き継いだ残高(50,000円)を記入します。
次に、「次期繰越金」を計算します。
次期繰越金は、「前期繰越金」と「当期収支差額」を合計した金額です。
次期繰越金 = 50,000円 + 152,000円 = 202,000円
この金額を記入します。
ステップ6:最終確認
すべての計算が正しいか、合計額などが一致しているかを確認します。
特に、「次期繰越金」が、実際の期末時点での現金残高と預金残高の合計額と一致しているかを必ず確認します。
以下に、上記例を簡単な表形式で示します。
令和6年度 さくら町町内会 収支決算書
(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
【収入の部】
| 勘定科目 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 会費収入 | 200,000円 | 会員100名分 |
| 寄付金収入 | 30,000円 | さくら商店様 |
| 助成金収入 | 50,000円 | 市 環境美化助成金 |
| 雑収入 | 5,000円 | 廃品回収収益金 |
| 収入合計 (A) | 285,000円 |
【支出の部】
| 勘定科目 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 事業費 - 夏祭り費 | 80,000円 | 会場設営、景品代他 |
| 事業費 - 清掃活動費 | 15,000円 | ゴミ袋、軍手代他 |
| 管理費 - 印刷費 | 10,000円 | 広報誌印刷代 |
| 管理費 - 通信費 | 5,000円 | 切手代、電話代 |
| 管理費 - 消耗品費 | 8,000円 | 文房具、コピー用紙 |
| 管理費 - 会議費 | 12,000円 | 役員会お茶代他 |
| 雑費 | 3,000円 | 振込手数料他 |
| 支出合計 (B) | 133,000円 |
【収支差引】
| 当期収支差額 (C=A-B) | 152,000円 | |
| 前期繰越金 (D) | 50,000円 | |
| 次期繰越金 (E=D+C) | 202,000円 | (現金 XXX円、預金 XXX円) |
収支決算書のチェックポイント5点
収支決算書を作成したら、提出や報告の前に、必ず以下の5点をチェックしましょう。
正確性を担保するために重要なポイントですので、忘れずに確認するようにしてください。
1. 数字の正確性(計算ミスはないか)
収入合計、支出合計、当期収支差額、次期繰越金の計算がすべて正しく行われているか、電卓やエクセルの関数を使って再計算し、確認します。
単純な足し算、引き算のミスがないか、注意深くチェックしましょう。
2. 帳簿との整合性
収支決算書に記載されている各勘定科目の金額が、基となった会計帳簿(現金出納帳、預金出納帳、総勘定元帳など)の合計額と一致しているかを確認します。
転記ミスや集計漏れがないかをチェックします。
3. 証憑との整合性
帳簿に記録されている収入や支出の根拠となる、領収書や請求書、銀行の取引明細などの証憑書類が、すべて揃っており、帳簿の内容と金額が一致しているかを確認します。
証憑のない取引が計上されていないか、逆に証憑はあるのに記帳漏れしている取引はないかをチェックします。
4. 繰越金の一致
「前期繰越金」の金額が、前期(前年度)の収支決算書に記載されている「次期繰越金」の金額と、完全に一致しているかを確認します。
ここが一致していないと、期首の残高がずれていることになり、全体の計算が狂ってしまいます。
5. 次期繰越金と実際の残高の一致
計算上の「次期繰越金」の金額が、会計期間の最終日時点での、実際の現金の手元残高と、すべての預金口座の残高の合計額と、完全に一致しているかを確認します。
これが一致しない場合は、記帳漏れや計算ミス、現金の過不足など、どこかに必ず原因があります。
一致するまで、原因を徹底的に調査する必要があります。
収支決算書を作成する際の注意点
収支決算書を正確に、そしてわかりやすく作成するためには、以下のような点に注意しましょう。
1. 会計期間を明確にする
収支決算書が、いつからいつまでの期間の収支をまとめたものであるかを、必ず明記します。
通常は1年間(例:4月1日から翌年3月31日まで)ですが、団体の規約などによって異なる場合もあります。
2. 勘定科目を統一し、わかりやすく設定する
収入や支出の内容を示す勘定科目は、一度決めたら期間中は変更せず、一貫して使用します。
また、「雑費」などの科目を多用せず、できるだけ具体的な科目名(例:「会議費」「消耗品費」)を設定することで、お金の使い道がより明確になり、わかりやすい決算書になります。
3. すべての取引に証憑を残す
収入・支出を問わず、すべての取引について、その根拠となる領収書や請求書、レシート、銀行の取引明細などの証憑書類を必ず保管しておきましょう。
証憑は、決算書の信頼性を担保する上で不可欠です。
紛失しないよう、日頃から整理しておく習慣が大切です。
4. 予算書と比較できるように作成する
予算を策定している場合は、収支決算書のフォーマットを予算書とできるだけ合わせるように作成すると、予算と実績の比較がしやすくなります。
勘定科目を揃えたり、予算額と実績額、差異を併記したりするなどの工夫が有効です。
5. 第三者にもわかるように作成する
収支決算書は、会計担当者だけでなく、会員や役員など、会計に詳しくない人も見る書類です。
専門用語を使いすぎず、摘要欄を活用して具体的な内容を補足するなど、誰が見てもお金の流れが理解できるよう、わかりやすい記述を心がけましょう。
収支決算書の作成サポートは『Chatwork 経理アシスタント』におまかせ!
日々の記帳作業が追いつかない、領収書の整理が溜まってしまうなど、収支決算書を作成するための前段階で頭を悩ませている団体や個人事業主の方におすすめしたいのが、『Chatwork 経理アシスタント』です。
『Chatwork 経理アシスタント』は、国内利用者数No.1のビジネスチャット「Chatwork」が提供する、オンライン完結型の経理アウトソーシングサービスです。
収支決算書の作成そのものではなく、その基礎となる日々の領収書の整理やデータ入力、記帳代行といった経理事務を、経験豊富な専門のアシスタントがチームでサポートします。
月々の実働時間に応じた料金体系で、必要な時に必要な分だけ柔軟に業務を依頼できます。
『Chatwork 経理アシスタント』に日々の経理処理を任せれば、収支決算書を作成する際に必要なデータが常に整理された状態で手元に保管できるようになるため、決算作業の負担を大幅に軽減することができます。
Chatwork 経理アシスタントを導入するメリット
『Chatwork 経理アシスタント』を活用することで、収支決算書の作成準備を効率化し、組織運営全体の生産性を向上させることができます。
1. 記帳作業から解放され、有意義な活動へ集中できる
日々の領収書の整理や会計ソフトへの入力といった、時間のかかる記帳業務から解放されます。
担当者は、イベントの企画・運営や、会員とのコミュニケーションといった、組織の活動目的そのものに関わる、より重要な業務に時間とエネルギーを集中させることができます。
2. 低コストで質の高いサポートを受けられる
会計担当者を専任で雇用する場合と比較して、月額数万円からというリーズナブルな料金で、プロの経理サポートを受けることができます。
採用や教育の手間とコストをかけることなく、質の高いサポート体制をスピーディーに構築できます。
特に、ボランティアで運営されている団体など、コストを抑えたい場合に有効です。
まとめ
本記事では、収支決算書の書き方について具体的な手順や注意点などをわかりやすく解説しました。
収支決算書は、町内会やPTA、非営利団体などの組織運営において、お金の流れを透明化し、関係者への説明責任を果たすための重要な書類です。
作成にあたっては、現金主義の考え方を理解し、日々の正確な記帳と証憑の保管を徹底することが重要です。
本記事で紹介した書き方の手順やチェックポイントを参考に、正確でわかりやすい収支決算書の作成を目指してみてください。
もし、収支決算書の作成や前準備の負担が大きいと感じる場合は、オンラインアシスタントサービスなどの外部サポートの活用も、有効な解決策となるでしょう。