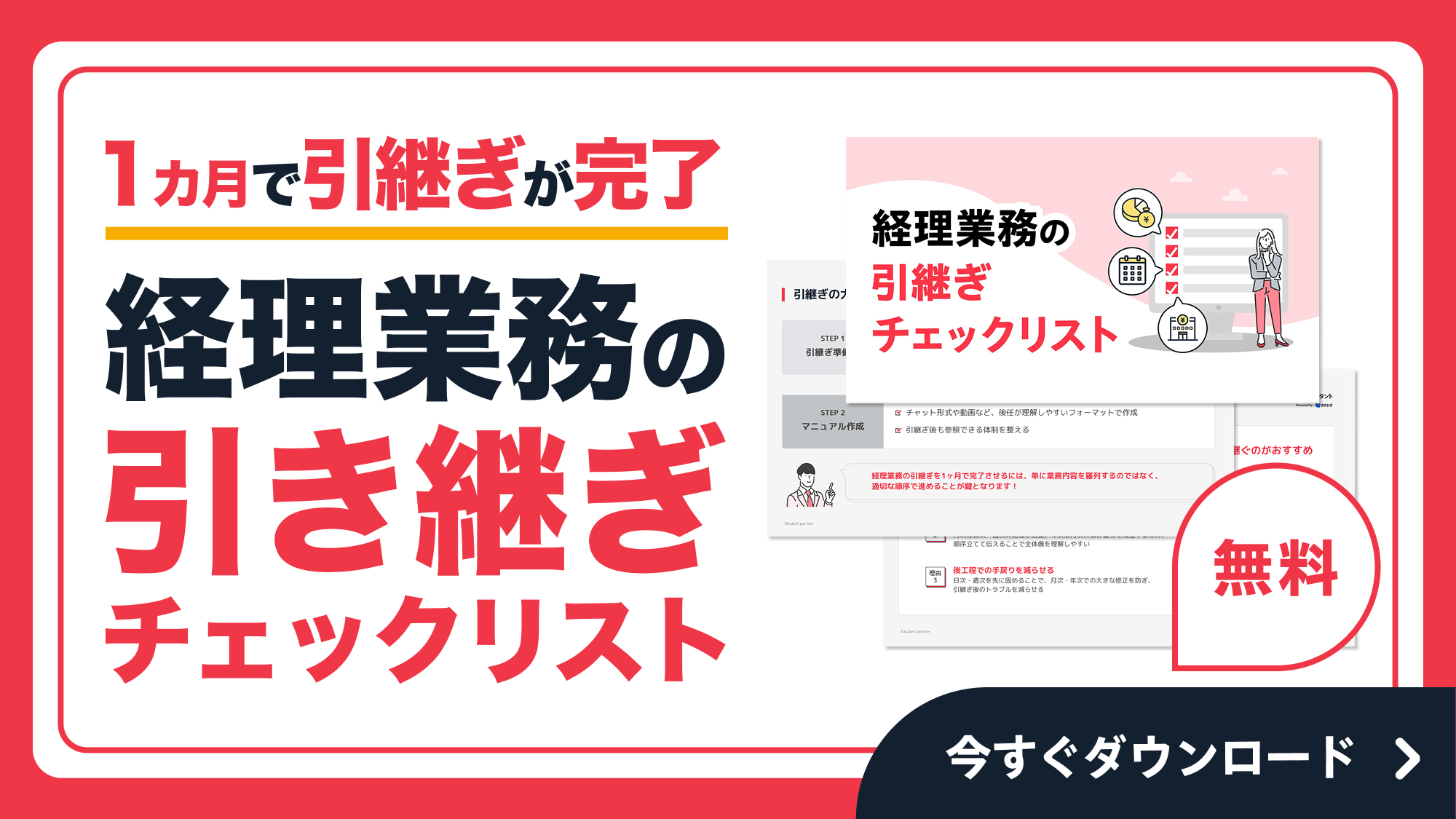【初心者さん必見】月次決算をやさしく解説!ステップ別のチェックリストや業務効率化のポイントをわかりやすくお届け

終わらない!

- リリースからわずか2年で
累計1000社以上が採用したサービス - 厳選された優秀なアシスタントが支援
- あらゆる経理業務を専門チームが代行
- 人手不足を解決し、安定した経理体制へ

目次
今回は、初心者の方にもわかりやすいように月次決算の基本を説明します。
目的や業務内容のほか、年次決算との違いや業務効率化の方法、チェックリストや注意点、初心者の方が月次決算を行うメリットも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
月次決算とは(概要・目的・必要資格など)
月次決算(げつじけっさん)とは、企業が毎月行う簡易的な決算作業のことです。
年に一度行う正式な決算(年次決算)とは異なり、法律で義務付けられているものではありません。
しかし、多くの企業が自主的に月次決算を行っています。
その主な目的は、「会社の経営状況をリアルタイムで把握すること」です。
毎月、その月の売上や費用、利益がどうだったのか、会社の財産はどのような状態なのかを月次決算で明らかにします。
作成された月次決算のデータ(試算表など)を見ることで、経営者は「今月は利益が出ているか」「資金繰りは大丈夫か」「計画通りに進んでいるか」といった会社の状況をリアルタイムで把握でき、もし問題が見つかれば、早期に対策を打つことが可能です。
月次決算は、経理担当者が担当したり、場合によっては経営者自身が行ったりするケースもあります。
月次決算を行うために特別な資格は必要ありませんが、正確な月次決算を行うためには、簿記の基本的な知識があるとスムーズです。
月次決算と年次決算の違い
月次決算と年次決算は、どちらも会社の成績や財政状態をまとめる作業ですが、その目的や性質にはいくつかの違いがあります。
| 項目 | 月次決算 | 年次決算 |
|---|---|---|
| 目的 | 社内向け 経営状況の早期把握、経営管理、迅速な意思決定 |
社外向け 税務申告、株主・債権者への報告 |
| 法的義務 | なし(任意) | あり(会社法、法人税法など) |
| 実施頻度 | 毎月 | 年に1回 |
| 作成書類 (例) | 月次試算表、月次損益計算書、月次貸借対照表、資金繰り表など | 貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表など (計算書類) |
| 正確性・厳密性 | 早期把握を重視するため、一部概算での処理も可 | 外部報告のため、会計基準に則った厳密な処理が必要 |
わかりやすい違いとしては、月次決算が主に「社内の経営管理」を目的としているのに対し、年次決算は「税務署や株主など社外への報告」を主目的としている点が挙げられます。
そのため、年次決算は法律で定められた厳密なルールに基づいて作成する必要がありますが、月次決算はある程度、自社の管理しやすい方法で行うことが可能です。
毎月正確な月次決算を行っていれば、年に一度の年次決算の作業負担を大幅に軽減できるというメリットがあります。
月次決算の流れとスケジュール
月次決算をスムーズに進めるためには、毎月決まった流れ(手順)とスケジュールで行うことが重要です。
ここでは、一般的な月次決算業務の流れと、各ステップの目安となるスケジュール(いつまでに何をすべきか)をご紹介します。
【月次決算の基本的な流れとスケジュール(例:月末締めの場合)】
ステップ1:日々の記帳と証憑整理(当月中~翌月1日)
月次決算の基礎となるのは、日々の正確な記帳です。
当月中に発生したすべての取引(売上、仕入、経費など)を、領収書や請求書などの証憑に基づいて、遅滞なく会計ソフトなどに入力します。
証憑書類も整理しておきます。
いつまで:理想は毎日ですが、遅くとも翌月1日には当月分の入力を完了させます。
ステップ2:現金・預金の残高確認(翌月1日~2日)
当月末時点での、手元現金の実際残高と、銀行口座の残高証明書(または通帳)の残高を確認します。
会計ソフト上の帳簿残高と一致しているかを照合します。
差異があれば原因を調査し、修正します。
いつまで:翌月のできるだけ早い段階(1~2日目)で行います。
ステップ3:売掛金・買掛金などの残高確認(翌月2日~4日)
当月末時点での、得意先ごとの売掛金残高と、仕入先ごとの買掛金残高を確定させます。
請求書や支払明細書と照合し、帳簿残高と一致しているかを確認します。
在庫がある場合は、在庫の数量と金額(棚卸高)も確定させます(帳簿棚卸が一般的)。
いつまで:翌月4日目頃までを目安に行います。
ステップ4:月次決算整理仕訳の入力(翌月4日~6日)
年次決算ほど厳密ではありませんが、月次でもいくつかの決算整理仕訳を行います。
主なものとしては、減価償却費の月割計上、未払費用(月末締め翌月払いの給与など)や前払費用(年払いの保険料の月割分など)の計上、仮払金・仮受金の精算などです。
いつまで:翌月6日目頃までに入力を完了させます。
ステップ5:月次試算表の作成とチェック(翌月6日~8日)
すべての仕訳入力が完了したら、「月次試算表」を作成します。
試算表の借方合計と貸方合計が一致しているかを確認します。
各勘定科目の残高に異常な数値がないか、前月や予算と比較して内容をチェックし、必要に応じて修正します。
いつまで:翌月8日目頃までに試算表を確定させます。
ステップ6:経営報告資料の作成と報告(翌月8日~10日)
確定した試算表をもとに、経営陣向けの報告資料(月次損益計算書、月次貸借対照表、資金繰り表、予実対比表など)を作成します。
作成した資料を用いて、経営会議などで業績を報告し、課題や今後の対策について議論します。
いつまで:翌月10日目(10営業日以内が理想)までに経営報告を完了させます。
このスケジュールはあくまで目安です。
自社の状況に合わせて無理のない計画を立て、毎月継続することが重要です。
【ステップ別】月次決算のチェックリスト
月次決算の各ステップで確認すべき項目をチェックリストにまとめました。
初心者の方でも、このリストに沿って進めることで、月次決算の抜け漏れを防ぎ、正確性を高めることができます。
【ステップ1:データ収集・記帳段階】
□ 当月分の売上に関する請求書・納品書はすべて揃っているか?
□ 当月分の仕入・経費に関する請求書・領収書はすべて揃っているか?
□ 預金通帳の記帳(またはWeb明細の取得)は完了しているか?
□ 小口現金の精算は完了しているか?
□ すべての取引の仕訳入力は完了しているか?
【ステップ2:現金・預金の残高確認段階】
□ 現金出納帳の残高と、実際の現金有高は一致しているか?
□ 預金出納帳(または会計ソフト)の残高と、銀行口座の残高証明書(または通帳)の残高は一致しているか?
□ 差異がある場合、原因は特定・修正されたか?
【ステップ3:売掛金・買掛金などの残高確認段階】
□ 売掛金の残高は、得意先元帳や請求控えと一致しているか?
□ 買掛金の残高は、仕入先元帳や請求書と一致しているか?
□ 在庫(棚卸資産)の残高は適切に計上されているか?
□ 仮払金・仮受金の内容は確認され、適切な科目に振り替えられたか?
【ステップ4:月次決算整理仕訳の入力段階】
□ 減価償却費は適切に計上されているか?
□ 未払費用(給与、社会保険料、家賃など)は計上されているか?
□ 前払費用(保険料、家賃など)は適切に期間按分されているか?
□ その他、月次で計上すべき費用(引当金など、必要に応じて)は計上されているか?
【ステップ5:試算表の作成とチェック段階】
□ 作成した月次試算表の借方合計と貸方合計は一致しているか?
□ 各勘定科目の残高に異常な数値(マイナス残高など)はないか?
□ 前月の試算表と比較して、不自然な変動をしている科目はないか?
□ 予算(計画値)と比較して、大きな差異が出ている科目はないか?
□ 疑問点や異常値について、原因は特定・修正されたか?
【ステップ6:経営報告資料の作成と報告段階】
□ 月次損益計算書、月次貸借対照表などの数値は、確定した試算表と一致しているか?
□ 各報告資料の体裁は整っており、わかりやすい形式になっているか?
□ 経営会議などで報告・議論され、必要なアクションは決定されたか?
月次決算を効率化するには
毎月継続する必要がある月次決算は、できるだけ効率的に行うことが望ましいでしょう。
ここでは、月次決算業務を効率化するための具体的な方法を4つご紹介します。
1. 会計ソフト・ITツールの導入・活用
クラウド型の会計ソフトを導入することは、効率化の第一歩です。
銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込み、AIが仕訳を提案してくれる機能を使えば、日々の記帳業務の手間と時間を大幅に削減できます。
また、減価償却費の計算や試算表の作成も自動で行われます。
経費精算システムや請求書発行システムと連携させれば、さらに効率化が進みます。
2. 業務の標準化とマニュアル化
月次決算の各業務プロセス(データの収集方法、仕訳のルール、チェックの手順など)を明確に定義し、誰が担当しても同じ手順で作業できるようにマニュアル化します。
業務が標準化されることで、作業の迷いがなくなり、スピードが向上します。
また、担当者の引き継ぎもスムーズになり、属人化を防ぐことができます。
3. ペーパーレス化の推進
紙の請求書や領収書を扱う業務は、ファイリングや検索に時間がかかり、非効率です。
請求書は電子で発行・受領する、経費精算はシステム上で完結させるといったペーパーレス化を進めることで、書類を探す手間や保管スペースを削減できます。
会計ソフトへの入力も、データ連携によって自動化しやすくなります。
4. アウトソーシング(外部委託)の活用
日々の記帳代行や、月次決算業務そのものを、税理士事務所や経理代行会社、オンラインアシスタントサービスなどにアウトソーシングする方法です。
社内のリソースが不足している場合や、より専門性の高い分析を求める場合に有効です。
担当者は、コア業務や経営分析といった、より付加価値の高い業務に集中することができます。
初心者が月次決算を行うメリット
経理初心者の方にとって、月次決算は難しく感じるかもしれませんが、挑戦することには大きなメリットがあります。
1. 経営状況を数字で理解できるようになる
毎月、自社の売上や費用、利益といった数字に触れることで、会社の経営状況を具体的に理解できるようになります。
「どの経費が多いのか」「利益率はどのくらいか」といった数字の感覚が養われ、経営者と同じ視点でビジネスを見られるようになります。
2. 簿記・会計の知識が実践的に身につく
日々の記帳から試算表の作成まで、一連のプロセスを毎月繰り返すことで、簿記や会計の知識が机上の空論ではなく、実践的なスキルとして定着します。
年次決算に向けての理解も深まり、経理担当者としてのスキルアップに直結します。
3. 年次決算の負担が大幅に軽減される
毎月データを締め、残高を確認しておくことで、年に一度の年次決算の際に、一年分の膨大なデータと格闘する必要がなくなります。
月次決算は、年次決算をスムーズに進めるための重要な準備作業となります。
4. 早期に問題を発見し、改善に貢献できる
月次決算を行う中で、「売掛金の回収が遅れている」「特定の経費が予算を超過している」といった問題点を早期に発見することができます。
その情報を経営陣に報告し、改善策の検討につなげることで、会社の業績改善へ直接的に貢献でき、経理担当者としての大きなやりがいにつながります。
初心者が月次決算を行う際の注意点
初心者が月次決算に取り組む際には、いくつか注意すべき点があります。
無理なく、確実に進めるためのポイントを押さえておきましょう。
1. 最初から完璧を目指さない
月次決算は年次決算ほど厳密な処理が求められるわけではありません。
最初は、すべての決算整理仕訳を完璧に行うことにこだわりすぎず、まずは日々の記帳を正確に行い、試算表を作成して大まかな経営状況を把握することから始めましょう。
慣れてきたら、徐々に計上する費用の範囲を広げていくなど、段階的に精度を高めていくのが簡単な進め方です。
2. 正確性を重視する
早期化も重要ですが、それ以上にデータの正確性が重要です。
間違ったデータに基づいて経営判断を下してしまうと、かえってマイナスの影響が出かねません。
入力ミスがないか、残高が合っているかなど、基本的なチェックは必ず丁寧に行いましょう。
3. 無理せず専門家(税理士など)に相談する
勘定科目の選択や、特殊な取引の処理方法など、判断に迷うことが出てくるはずです。
わからないことをそのままにせず、顧問税理士などの専門家に相談しましょう。
税理士は、月次決算の導入支援や、作成された試算表のレビュー、経営へのアドバイスなども行ってくれます。
4. 継続することが重要
月次決算は、毎月継続して行うことで、業績の推移や傾向が見えてきます。
最初のうちは負担に感じるかもしれませんが、無理のない範囲で、まずは1年間継続することを目指しましょう。
継続することで業務にも慣れ、月次決算から得られる気づきも増えていきます。
月次決算業務にお困りなら『Chatwork 経理アシスタント』がおすすめ!
月次決算に関する課題を抱える企業におすすめしたいのが、『Chatwork 経理アシスタント』です。
『Chatwork 経理アシスタント』は、国内利用者数No.1のビジネスチャット「Chatwork」が提供する、オンライン完結型の経理アウトソーシングサービスです。
月次決算の基礎となる日々の記帳代行はもちろん、売掛金・買掛金の管理、経費精算、月次試算表の作成サポートまで、幅広い経理業務を経験豊富なアシスタントがチームで遂行します。
月々の実働時間に応じた料金体系で、必要な時に必要な分だけ、柔軟に業務を依頼できます。
また、社内の経理担当者が初心者である場合のサポートも可能です。
Chatwork 経理アシスタントを導入するメリット
『Chatwork 経理アシスタント』を導入することで、企業は月次決算に関する課題を解決し、さらに多くのメリットを得ることができます。
1. 月次決算の早期化を実現
日々の記帳業務をアシスタントに任せることで、月初の段階で前月分の会計データがほぼ確定した状態になります。
その後の残高確認や月次処理もスムーズに進むため、月次決算にかかる時間を大幅に短縮できます。
経営者は、より早いタイミングで経営状況を把握し、迅速な意思決定を下せるようになります。
2. コストを抑えて専門人材を確保
月次決算を正確に行える経理担当者を採用・育成するには、多くのコストと時間がかかります。
『Chatwork 経理アシスタント』は、月額数万円からというリーズナブルな料金で、プロの経理サポートを受けることができます。
採用や教育の手間とコストをかけることなく、質の高い月次決算体制をスピーディーに構築できます。
3. 業務の標準化と属人化の解消
アシスタントは、企業のルールに基づき、標準化された手順で業務を遂行します。
業務プロセスが可視化され、特定の担当者に依存しない体制が構築されるため、属人化のリスクを解消できます。
担当者の急な退職などがあっても、業務が滞る心配がありません。
4. Chatworkによる円滑な連携
アシスタントとの業務連絡や、証憑書類の共有は、すべてビジネスチャット「Chatwork」で完結します。
月次決算の進捗確認や不明点の問い合わせなどもチャットで迅速に行えるため、月次決算プロセス全体のスピードと効率が高まります。
まとめ
本記事では、月次決算の目的や業務の流れ、効率化のポイントやチェックリストなどを初心者の方にもわかりやすいように解説しました。
月次決算は法律で義務付けられてはいませんが、企業の経営状況をタイムリーに把握し、迅速な意思決定を行う上で、非常に有効です。
初心者の方が月次決算を行う際は、業務のポイントを押さえ、適宜システムや外部サービスなども活用しながら進めてみると良いでしょう。