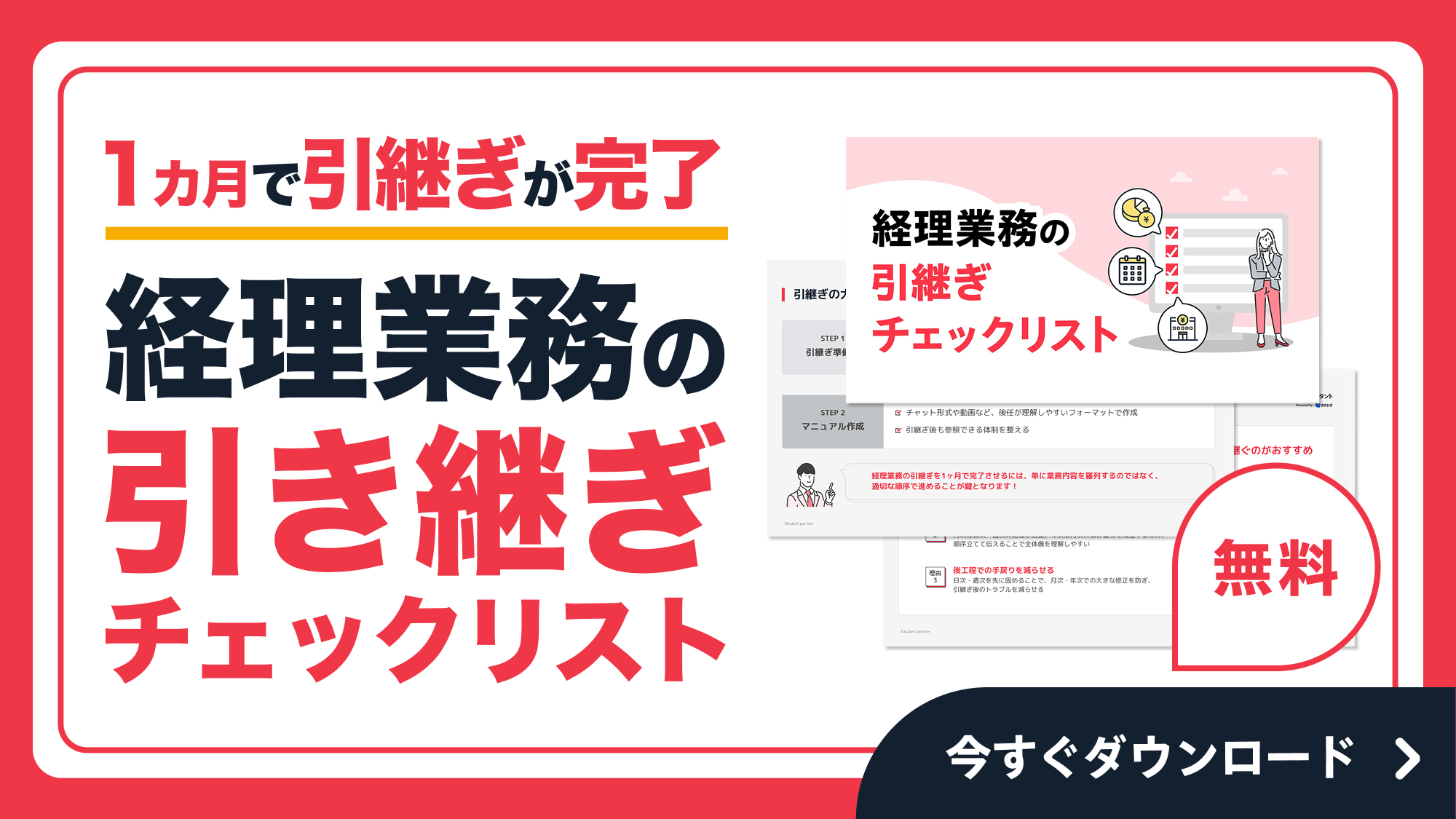【具体例多数】経理の必須業務・仕訳とは?考え方・書き方の基本や勘定科目の分類、効率化のコツを丁寧に解説

終わらない!

- リリースからわずか2年で
累計1000社以上が採用したサービス - 厳選された優秀なアシスタントが支援
- あらゆる経理業務を専門チームが代行
- 人手不足を解決し、安定した経理体制へ

目次
経理の仕事において、「仕訳」は避けて通れない業務です。
しかし、簿記の専門用語や覚えるべき知識が多く、初心者にとっては難解に感じられるかもしれません。
この記事では、仕訳の基本的な考え方や書き方、勘定科目などについて、初心者の方にもわかりやすい例を挙げながら丁寧に解説します。
あわせて、仕訳業務を効率化する方法も紹介しますので、日々の経理業務にお悩みの方はぜひ参考にしてください。
経理の必須業務「仕訳」とは?
経理の仕事における「仕訳(しわけ)」とは、会社や個人事業主の日々の取引(お金やモノの動き)を、会計ルールに則って記録する作業のことです。
具体的には、「いつ」「何が」「どれだけ」動いたのかを、複式簿記という方法で帳簿に記録します。
日々の仕訳作業の積み重ねが決算書を作成するための基礎データとなるため、仕訳を正確に行うことは会社の財産状況や経営成績を正しく把握し、適正な税務申告を行うための非常に重要な業務と言えます。
以下では、仕訳を理解するために知っておくべき基本的な用語を紹介します。
借方(かりかた)と貸方(かしかた)
複式簿記では、すべての取引を「原因」と「結果」の2つの側面から捉え、帳簿の左側と右側に分けて記録します。
この帳簿の左側を「借方(かりかた)」、右側を「貸方(かしかた)」と呼びます。
なぜ左右に分けるのか、最初は難しく感じるかもしれませんが、まずは「取引には必ず2つの側面があり、それを左右に振り分けるルールになっているから」と捉えておきましょう。
仕訳の簡単な覚え方として、お金やモノが「入ってきた(増えた)原因」や「使った(増えた)もの」を左側の借方に、お金やモノが「出ていった(減った)原因」や「調達した(増えた)もの」を右側の貸方に記録する、とイメージするとわかりやすい場合があります。
勘定科目(かんじょうかもく)
勘定科目とは、取引の内容をわかりやすく分類するために使う「ラベル」や「見出し」のようなものです。
例えば、お金が入ってきた場合でも、それが「商品を売った代金」なのか、「銀行から借りたお金」なのかで、会社にとっての意味は全く異なります。
「商品を売った代金」であれば「売上高」、「銀行から借りたお金」であれば「借入金」といった勘定科目を使って仕訳を行います。
どのような勘定科目があるかは、後ほど詳しく解説します。
貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)
貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)は、決算日時点での「会社の財産状況」を示す決算書です。
日々の仕訳データのうち、「資産」「負債」「純資産」に分類される勘定科目が集計され、作成されます。
左側(借方)に「資産(会社が持つ財産)」、右側(貸方)に「負債(将来返すべきお金)」と「純資産(返済不要の自分のお金)」が記載され、左右の合計金額は必ず一致します。
損益計算書(そんえきけいさんしょ)
損益計算書(そんえきけいさんしょ)は、一定期間(通常は1年間)の「会社の経営成績」を示す決算書です。
日々の仕訳データのうち、「収益」と「費用」に分類される勘定科目を集計して作成します。
会社がどれだけ売上(収益)を上げ、そのためにどれだけの経費(費用)を使い、最終的にいくら儲かったのか(利益)がわかります。
仕訳の基本的な考え方・書き方と記載例
仕訳には、いくつかの基本的なルールがあります。
このルールさえ押さえれば、初心者の方でも基本的な書き方がわかるようになります。
1. 取引の二面性
前述の通り、すべての取引には必ず「原因」と「結果」の2つの側面があります。
例えば、「現金100円でペンを買った」という取引は、「ペンという資産が増えた(結果)」と同時に、「現金という資産が100円減った(原因)」という2つの動きが発生しています。
仕訳は、この2つの側面を必ず借方と貸方の両方に記録します。
2. 借方と貸方の金額は必ず一致する
1つの取引を借方と貸方に分けて記録するため、借方に記録した金額の合計と、貸方に記録した金額の合計は、必ず一致します。
この原則を「貸借平均の原理」と呼びます。
計算が合わない場合は、どこかの仕訳が間違っているということになります。
3. 勘定科目の5つのグループ
勘定科目は、その性質によって「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」の5つのグループに分類されます。
この5つのグループが、借方と貸方のどちらに記録されるかで、「増えた」のか「減った」のかが決まります。
(詳細は後述しますが、例えば「資産」は、借方に書くと「増加」、貸方に書くと「減少」を意味します。)
仕訳の基本的な書き方と記載例
仕訳は、一般的に以下のような形式で記録します。
(借方勘定科目) 金額 / (貸方勘定科目) 金額
日付や取引内容(摘要)もあわせて記録します。
【例1】10月1日、文房具店でペン110円(うち消費税10円)を現金で買った。
・(結果)「消耗品費」という費用が100円発生し、「仮払消費税」という資産が10円発生した(借方)
・(原因)「現金」という資産が110円減った(貸方)
(借方)消耗品費 100円 / (貸方)現金 110円
(借方)仮払消費税 10円
※経理処理の方法によっては、消費税を分けずに「消耗品費 110円」と処理する場合もあります。
【例2】10月5日、取引先A社に商品55,000円を掛けで販売した(代金は後日受け取り)。
・(結果)「売掛金」という資産が55,000円増えた(借方)
・(原因)「売上高」という収益が55,000円発生した(貸方)
(借方)売掛金 55,000円 / (貸方)売上高 55,000円
【例3】10月31日、A社から売掛金55,000円が普通預金口座に入金された。
・(結果)「普通預金」という資産が55,000円増えた(借方)
・(原因)「売掛金」という資産が55,000円減った(貸方)
(借方)普通預金 55,000円 / (貸方)売掛金 55,000円
このように、一つひとつの取引を借方と貸方に分類していくのが、仕訳の基本的な作業です。
最初は難しく感じるかもしれませんが、練習を重ねることでパターンが見えてきます。
経理で行う仕訳業務の流れ
実際の経理業務では、どのような流れで仕訳が行われるのでしょうか。
ここでは、日々の仕訳業務の一般的な流れをご紹介します。
ステップ1:証憑(しょうひょう)の受領と整理
まず、取引の証拠となる書類(証憑)を集めます。
例えば、従業員が立て替えた経費の領収書、取引先から郵送されてくる請求書、銀行の通帳や入出金明細、自社で発行した請求書の控えなどです。
これらの書類を日付順や取引先ごとに整理します。
ステップ2:取引内容の把握と勘定科目の決定
収集した証憑をもとに、一つひとつの取引の内容を正確に把握します。
「いつ、誰と、何のために、いくらのお金が動いたのか(または動く予定なのか)」を確認します。
その内容に最も適した勘定科目を決定します。
ここで勘定科目の選択を誤ると、後々の決算書の内容が不正確になってしまいます。
ステップ3:仕訳の起票(会計ソフトへの入力)
決定した勘定科目と金額を、借方と貸方に振り分け、会計ソフトや帳簿に記録します。
この作業を「起票」または「仕訳入力」と呼びます。
取引日、金額、勘定科目、摘要(取引内容のメモ)などを正確に入力していきます。
ステップ4:試算表でのチェック
一定期間(毎日、毎週、または毎月)の仕訳入力が終わったら、「試算表」という集計表を作成します。
試算表では、すべての勘定科目の残高が一覧表示され、借方合計と貸方合計が必ず一致するようになっています。
この合計金額が一致しない場合は、どこかの仕訳入力が間違っているか、入力漏れがあることを示しています。
合計が一致していても、勘定科目の使い方が間違っている場合もあるため、各科目の残高に不自然な点がないかをチェックします。
ステップ5:証憑の保管
入力が完了した領収書や請求書などの証憑は、法律で定められた期間(通常7年~10年)、税務調査などでいつでも確認できるように、適切にファイリングして保管します。
経理の仕訳業務は、上記のステップ1から5までを日々あるいは毎月、正確に繰り返していく作業となります。
仕訳入力の主な方法とメリット・デメリット
仕訳を入力(起票)する方法には、主に3つの方法があります。
それぞれのメリットとデメリットを理解し、自社に合った方法を選びましょう。
1. 振替伝票(手書き)
【概要】
「振替伝票」という専用の紙に、日付、勘定科目、金額、摘要を手書きで記入していく、昔ながらの方法です。
記入した伝票をもとに、総勘定元帳へ転記していきます。
【メリット】
導入コストが(紙代のみで)ほとんどかからない。
手で書くことで、簿記の仕組みや仕訳の感覚が身につきやすい。
【デメリット】
非常に手間と時間がかかる。
書き間違いや、元帳への転記ミス、集計ミスといったヒューマンエラーが発生しやすい。
試算表や決算書の作成にも、すべての科目を手作業で集計する必要があり、膨大な時間がかかる。
データの検索や修正が困難。
2. エクセル(Excel)
【概要】
エクセルで仕訳帳のフォーマット(日付、借方科目、借方金額、貸方科目、貸方金額、摘要)を作成し、入力していく方法です。
関数(SUMIFなど)やピボットテーブルを活用すれば、総勘定元帳や試算表を自動で集計することも可能です。
【メリット】
多くの企業で既に導入されており、追加のコストがほとんどかからない。
会計ソフトに比べて、自社の管理しやすいようにフォーマットを自由にカスタマイズできる。
【デメリット】
正確な集計表を作成するには、エクセルの高度な関数や簿記の知識が必要。
数式の入力ミスや、入力行のズレなどで、集計が合わなくなるリスクがある。
法改正(消費税率の変更など)があった場合、自分で計算式や設定をすべて修正する必要がある。
特定の人が作成したファイルは、他の人が修正・管理できなくなり、「属人化」しやすい。
3. 会計ソフト(クラウド型・インストール型)
【概要】
経理処理専用に開発されたソフトウェアを利用する方法です。
日々の仕訳を入力するだけで、総勘定元帳や試算表、決算書までを自動で作成してくれます。
近年は、インターネット経由で利用できるクラウド型の会計ソフトが主流です。
【メリット】
仕訳入力の効率が格段に向上する。
(銀行明細やクレジットカードの自動取り込み、AIによる勘定科目の自動提案など)
転記や集計が自動で行われるため、計算ミスや転記ミスが原理的に発生しない。
試算表や決算書がリアルタイムで作成され、経営状況をいつでも把握できる。
法改正や税制改正にも、ソフトのアップデートで自動対応してくれる。
【デメリット】
導入費用や、月額・年額の利用料といったコストが発生する。
ソフトの操作方法を覚える必要がある。
取引量が少ない個人事業主などを除き、現代の経理業務において、会計ソフトの利用は、正確性と効率性の両面から見て、ほぼ必須の選択肢と言えます。
勘定科目の5分類と代表的な勘定科目
仕訳を行う上で、「勘定科目」の理解は不可欠です。
膨大な数があるように見える勘定科目ですが、その性質によって以下の5グループのいずれかに分類されます。
この5分類の役割を理解することが、簿記の基本です。
| 分類 | 概要(何を示すか) | 借方(左)で増加 | 貸方(右)で増加 | 代表的な勘定科目(例) |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | 会社が保有する財産(プラスの財産) | 増加 | 減少 | 現金、普通預金、売掛金、商品、建物、土地、車両運搬具 |
| 負債 | 会社が将来支払う義務(マイナスの財産) | 減少 | 増加 | 買掛金、借入金、未払金、預り金 |
| 純資産 | 会社の純粋な元手(資産 - 負債) | 減少 | 増加 | 資本金、利益剰余金(繰越利益剰余金) |
| 収益 | 会社の儲けの源泉 | 減少 | 増加 | 売上高、受取利息、雑収入 |
| 費用 | 儲けを得るために使ったお金や労力 | 増加 | 減少 | 仕入高、給与手当、地代家賃、消耗品費、旅費交通費、通信費 |
仕訳を行う際は、まず取引が5グループのうちどのグループの「増加」または「減少」にあたるのかを考えます。
例えば、「資産の増加」「費用の増加」は借方(左側)に、「負債の増加」「純資産の増加」「収益の増加」は貸方(右側)に記録するのが基本です。
このルールに当てはめていくことで、仕訳の書き方がわかるようになります。
仕訳がわかりにくい勘定科目
続いて、初心者の方が仕訳で迷いやすい・わかりにくい勘定科目やシチュエーションをいくつかピックアップして解説します。
「消耗品費」と「事務用品費」の違い
どちらも、文房具やコピー用紙など、使ったらなくなるものを購入した際に使う費用の勘定科目です。
基本的な意味は同じです。
会社によっては、事務作業で使うものを「事務用品費」、それ以外(トイレットペーパーや洗剤など)を「消耗品費」と使い分ける場合や、どちらか一方の「消耗品費」に統一してしまう場合などがあります。
重要なのは、一度社内で決めたルールを継続して使用することです。
「雑費」の適切な使い方
どの勘定科目にも当てはまらない支出、少額で発生頻度の低い支出に使われるのが「雑費」です。
便利な勘定科目ですが、多用は禁物です。
雑費が多すぎると、何にお金を使っているのかがわからなくなり、経営分析や税務調査の際に問題となります。
支出内容が明確なものは、できるだけ具体的な勘定科目(例:新聞図書費、会議費など)で処理し、雑費の割合は費用全体の5%~10%程度に抑えるのが望ましいでしょう。
「仮払金」と「仮受金」
これらは、一時的に使用する勘定科目です。
仮払金(かりばらいきん):出張費の前渡しなど、支出の目的や金額が確定していない段階で、先に現金を支払った場合に使用する「資産」の勘定科目です。
後日、従業員からの精算報告(領収書の提出など)があった時点で、正式な勘定科目(例:旅費交通費)に振り替えます。
仮受金(かりうけきん):内容が不明な入金があった場合など、収入の理由が確定していない段階で、先に現金や預金を受け取った場合に使用する「負債」の勘定科目です。
後日、内容が判明した時点(例:売掛金の入金だった)で、正式な勘定科目(例:売掛金)に振り替えます。
どちらの科目も、決算までには必ず内容を精査し、残高がゼロになるように処理する必要があります。
「預り金」
従業員の給与から天引きした、所得税や住民税、社会保険料などを、会社が一時的に預かる場合に使用する「負債」の勘定科目です。
預かったお金は、後日、会社が従業員に代わって国や自治体、年金事務所へ納付します。
経理の仕訳業務に役立つルール5選
次に、日々の仕訳業務を正確かつ効率的に行うために、社内で設定しておくと良いルールを5つご紹介します。
1. 勘定科目の一覧表(マニュアル)を作成する
自社で使用する勘定科目を一覧にし、それぞれの科目の定義や、どのような取引の場合に使用するのかを明記した「勘定科目マニュアル」を作成します。
担当者によって勘定科目の使い方が異なると、正確な経営分析ができなくなってしまうためです。
ルールを統一することで、誰が処理しても同じ仕訳ができるようになり、属人化の防止にも役立ちます。
2. 「雑費」の上限ルールを設ける
前述の通り、「雑費」の多用は好ましくありません。
例えば、「5,000円以上の支出は原則として雑費で処理しない」「雑費の内容は必ず摘要欄に具体的に記載する」といったルールを設けることで、安易な雑費の使用を防ぎます。
3. 証憑(領収書など)の提出期限を厳守する
従業員からの経費精算や、取引先からの請求書の提出が遅れると、月次決算の遅延に直結します。
「経費精算は翌月3営業日までに申請する」など、社内での証憑提出期限を明確に定め、全社で徹底することが重要です。
4. 現金の取り扱いを最小限にする
小口現金での支払いは、記帳漏れや紛失、盗難のリスクを伴い、管理の手間もかかります。
可能な限り、法人クレジットカードや銀行振込での支払いに切り替えることで、取引履歴がデータとして残り、会計ソフトとの連携も容易になるため、仕訳業務が大幅に効率化されます。
5. わからないことは放置せず、すぐに確認する
内容が不明な取引や、どの勘定科目を使えばよいかわからない仕訳を、曖昧なまま処理してしまうと、後で大きな手戻りが発生します。
不明な点があれば、その都度、上司や顧問税理士に確認するルールを徹底しましょう。
早期の解決が、結果として業務効率化につながります。
経理でよく使う勘定科目の仕訳例8選
ここでは、経理で頻繁に登場する取引について、仕訳の具体的な書き方の例を8つご紹介します。
簿記の練習としても参考にしてください。
(※消費税は、簡略化のために税込経理(費用に含める)で記載する例と、税抜経理(仮払消費税などを使う)の例を示します。)
例1:現金でコピー用紙5,500円(税込)を購入した。
(借方)消耗品費 5,500円 / (貸方)現金 5,500円
(※税抜経理の場合: (借方)消耗品費 5,000円、仮払消費税 500円 / (貸方)現金 5,500円)
例2:取引先に従業員が出向き、交通費(電車代)2,000円を現金で立て替えた。後日精算する。
・従業員が立て替えた時点では、会社のお金は動いていないため、仕訳は不要です(または「未払金」として計上する方法もあります)。
・後日、従業員が経費精算を申請し、現金で支払った場合:
(借方)旅費交通費 2,000円 / (貸方)現金 2,000円
例3:商品を110,000円(税込)で販売し、代金は掛けとした。
(借方)売掛金 110,000円 / (貸方)売上高 110,000円
(※税抜経理の場合: (借方)売掛金 110,000円 / (貸方)売上高 100,000円、仮受消費税 10,000円)
例4:例3の売掛金110,000円が、普通預金口座に入金された。
(借方)普通預金 110,000円 / (貸方)売掛金 110,000円
例5:事務所の家賃77,000円(税込)が、普通預金口座から引き落とされた。
(借方)地代家賃 77,000円 / (貸方)普通預金 77,000円
(※税抜経理の場合: (借方)地代家賃 70,000円、仮払消費税 7,000円 / (貸方)普通預金 77,000円)
例6:従業員の給与300,000円から、源泉所得税10,000円、社会保険料40,000円を天引きし、差額を普通預金から振り込んだ。
(借方)給与手当 300,000円 / (貸方)普通預金 250,000円
/ (貸方)預り金(所得税) 10,000円
/ (貸方)預り金(社会保険料) 40,000円
例7:銀行から運転資金として1,000,000円を借り入れ、普通預金に入金された。
(借方)普通預金 1,000,000円 / (貸方)長期借入金 1,000,000円
例8:借入金の返済として、元金50,000円と利息5,000円の合計55,000円が普通預金から引き落とされた。
(借方)長期借入金 50,000円 / (貸方)普通預金 55,000円
(借方)支払利息 5,000円
経理の仕訳業務を効率化するには?
日々の仕訳業務は、企業の経理担当者にとって大きな負担です。
この業務を効率化することは、経理部門全体の生産性向上に直結します。
1. クラウド会計ソフトの導入
仕訳業務の効率化に効果的な方法が、クラウド会計ソフトの導入です。
銀行口座やクレジットカードの取引明細を自動で取り込み、AIが過去の履歴から勘定科目を推測して仕訳候補を自動で作成してくれます。
担当者は、その内容を確認・承認するだけで入力が完了するため、手入力の手間を大幅に削減できます。
2. 経費精算システムや請求書発行システムの連携
経費精算システムや請求書発行システムを導入し、それらを会計ソフトと連携させることも有効です。
経費精算システムで承認されたデータは、自動で会計ソフトに仕訳として取り込まれます。
請求書発行システムで作成した売上データも同様です。
二重入力の手間がなくなり、ミスも防げます。
3. ペーパーレス化の推進
紙の領収書や請求書をスキャンして電子データで管理(電子帳簿保存法に対応)することで、書類の整理や検索にかかる時間を削減できます。
AI-OCR(光学文字認識)機能を使えば、スキャンした画像から文字情報を読み取り、仕訳データを自動生成することも可能です。
4. アウトソーシング(外部委託)の活用
仕訳業務そのものを、専門の外部業者に委託(アウトソーシング)する方法です。
記帳代行サービスやオンラインアシスタントサービスなどを活用し、領収書や請求書のデータを渡すだけで、面倒な仕訳入力をすべて任せることができます。
社内にリソースがない場合や、担当者がコア業務に集中したい場合に有効です。
仕訳業務の効率化には『Chatwork 経理アシスタント』がおすすめ!
仕訳業務の負担軽減と効率化に課題を抱えている企業におすすめしたいのが『Chatwork 経理アシスタント』です。
『Chatwork 経理アシスタント』は、国内利用者数No.1のビジネスチャット「Chatwork」が提供する、オンライン完結型の経理アウトソーシングサービスです。
日々の記帳代行(仕訳入力)はもちろん、請求書発行、経費精算、支払い管理まで、幅広い経理事務の業務を専門のアシスタントチームがサポートします。
経理担当者を新たに採用することなく、月額数万円からという低コストで質の高い経理体制を構築することができます。
Chatwork 経理アシスタントを導入するメリット
『Chatwork 経理アシスタント』を導入することで、企業は仕訳業務に関する課題を解決し、以下のようなメリットを得ることができます。
1. 煩雑な仕訳入力業務からの解放
従業員が手元の領収書をスマートフォンで撮影し、Chatworkアプリで送信すると、アシスタントがその画像を基に勘定科目を判断し、会計ソフトへの入力(仕訳)を代行します。
日々の面倒なデータ入力作業から解放され、担当者は、作成された試算表のチェックや、経営分析といった、より付加価値の高い業務に集中できます。
2. コストを抑えて専門人材を確保できる
経理の実務経験者を一人直接雇用すれば、月々数十万円の人件費がかかります。
『Chatwork 経理アシスタント』は、月額数万円からというリーズナブルな料金で、簿記の知識や実務経験を持つプロのアシスタントチームを活用できます。
採用や教育の手間とコストをかけることなく、質の高い経理機能をスピーディーに立ち上げることが可能です。
3. 業務の標準化と属人化の解消
アシスタントは、企業のルールに基づき、標準化された手順で業務を遂行します。
勘定科目の使い方などが統一され、業務プロセスが可視化されます。
特定の担当者にしかわからないという「属人化」のリスクを解消し、担当者の急な退職などがあっても業務が滞る心配がありません。
4. Chatworkによる円滑な連携
アシスタントとの業務連絡や証憑書類の共有は、すべてビジネスチャット「Chatwork」で完結します。
仕訳内容について不明な点があれば、アシスタントからチャットで質問が届き、担当者がすぐに回答できます。
スムーズな連携によって、仕訳業務全体のスピードと正確性が高まります。
まとめ
本記事では、経理の必須業務である「仕訳」について、基本的な考え方・書き方の例、効率化の方法などを解説しました。
仕訳は簿記のルールに基づいた専門的な作業であるため、初心者にとってはわからないことが多く、難しく感じられるかもしれません。
しかし、借方・貸方の関係や、勘定科目の5つの分類といった基本的なルールを理解し、具体的な例を通じて練習を重ねれば身につけることができます。
また、仕訳業務は、会計ソフトの導入やアウトソーシングサービスの活用によって大幅に効率化できる領域でもあります。
自社の状況に合わせて、経理業務の負担軽減と高精度化を目指しましょう。