バックオフィス業務とは?仕事内容・課題・効率化の方法を徹底解説
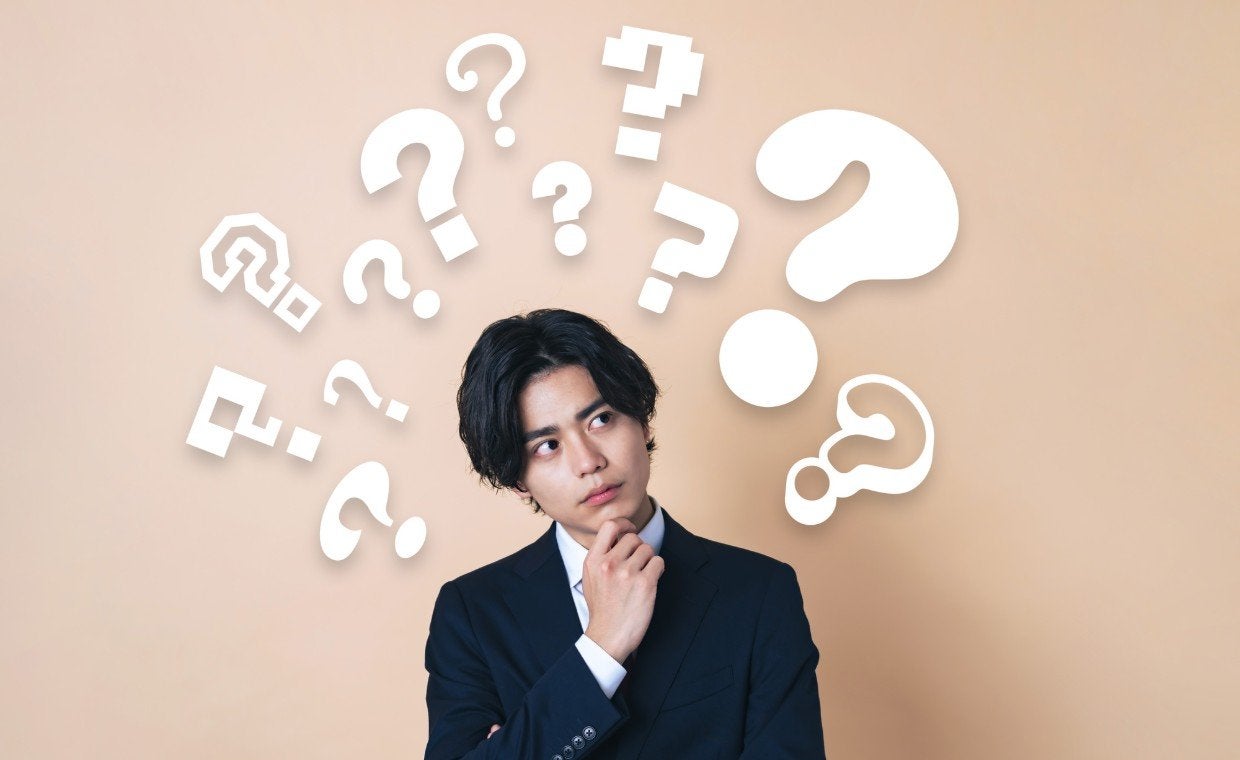
目次
「バックオフィス」と聞くと、どのような仕事をイメージしますか?経理や人事、総務など、一見すると地味な印象があるかもしれません。しかし、バックオフィスは企業の根幹を支え、円滑な事業運営に欠かせない、まさに「縁の下の力持ち」です。
本記事では、バックオフィス業務の具体的な仕事内容から、多くの企業が抱える課題、そしてその解決策までを、ITツールに詳しくない方にもわかりやすく解説します。あなたの会社のバックオフィスがより強く、生産性の高いチームへと変わるヒントがここにあります。
バックオフィス業務とは?企業の成長を支える重要な役割
バックオフィス業務とは、顧客と直接やり取りをしない、企業内部の管理業務全般を指します。企業の活動を後方から支援するという意味で、「後方支援」とも呼ばれます。これらの業務は、直接的に利益を生み出すわけではありませんが、会社全体の生産性を高め、従業員が働きやすい環境を整える上で、極めて重要な役割を担っています。
バックオフィス業務の基本的な役割と「縁の下の力持ち」としての重要性
バックオフィスの基本的な役割は、フロントオフィス(営業や販売など、顧客と直接関わる部門)の活動を円滑に進めるためのサポートです。例えば、営業担当者が顧客との商談に集中できるのは、経理担当者が見積書や請求書を正確に作成し、総務担当者が必要な備品を整えてくれているおかげです。
このように、バックオフィスは目立つ存在ではないかもしれませんが、その働きがなければ企業活動は成り立ちません。従業員の給与計算、社会保険の手続き、オフィスの環境整備、契約書の管理など、その業務は多岐にわたります。まさに、企業の成長と安定を陰で支える「縁の下の力持ち」といえるでしょう。
フロントオフィス・ミドルオフィスとの違いは?
企業の業務は、その役割によって大きく3つに分類されます。それぞれの違いを理解することで、バックオフィスの立ち位置がより明確になります。
| 部門 | 主な役割 | 具体例 |
|---|---|---|
| フロントオフィス | 顧客と直接関わり、収益を生み出す部門 | 営業、マーケティング、販売、カスタマーサポート |
| ミドルオフィス | フロントオフィスとバックオフィスの間に立ち、業務の橋渡しや管理をおこなう部門 | 営業企画、経営企画、コンプライアンス管理 |
| バックオフィス | 顧客と直接関わらず、企業活動を後方から支援する部門 | 経理、人事、総務、法務、情報システム |
フロントオフィスが「攻め」の部門だとすれば、バックオフィスは「守り」の部門です。そして、ミドルオフィスはその両者をつなぐ司令塔のような役割を果たします。これら3つの部門が連携し、それぞれの役割を果たすことで、企業は健全な成長を遂げることができます。
混同されがちな「事務」との違いと業務範囲
「バックオフィス業務」と「事務」は、しばしば同じ意味で使われがちですが。
厳密にはその範囲が異なります。「事務」は、書類作成やデータ入力、電話応対といった、比較的定型的な作業を指すことが多いです。
これに対して、「バックオフィス業務」は、事務作業を含みつつも、経理、人事、法務といった、より専門的な知識やスキルを必要とする広範な業務を包含します。
つまり、「事務」はバックオフィス業務の一部と考えることができます。
バックオフィスは、単なる作業にとどまらず、企業の経営戦略に関わるような重要な意思決定をサポートする役割も担っているのです。
【職種一覧】バックオフィス業務の主な仕事内容
バックオフィス業務と一口にいっても、その内容は多岐にわたります。
ここでは、代表的な職種とその仕事内容を紹介します。
自分の会社にどの部署があり、どのような役割を担っているか、改めて確認してみましょう。
経理・財務:企業のお金の流れを管理する
経理・財務は、企業のお金に関するあらゆる業務を担当する部門です。
日々の売上や経費の管理から、月次・年次の決算業務、資金繰りの管理、予算策定、さらには資産運用に至るまで、その業務は企業の経営に直結します。
- 日常業務:伝票の起票、経費精算、売掛金・買掛金の管理、請求書発行
- 決算業務:月次・四半期・年次決算、貸借対照表(B/S)・損益計算書(P/L)の作成
- 財務業務:資金調達、予算管理、資産運用、IR(投資家向け広報)活動
正確性が第一に求められることはもちろん。
経営陣に対して財務状況を的確に報告し、経営判断をサポートする重要な役割も担っています。
人事・労務:企業の「人」に関する業務を担う
人事・労務は、企業の最も重要な資産である「人」に関する業務全般を担当します。
従業員の採用から育成、評価、配置、退職に至るまで、従業員のライフサイクルすべてに関わります。
- 採用活動:採用計画の立案、求人広告の出稿、応募者対応、面接、内定者フォロー
- 人材育成:新入社員研修、階層別研修、スキルアップ研修の企画・実施
- 人事制度:人事評価制度や報酬制度の設計・運用、人員配置の検討
- 労務管理:給与計算、勤怠管理、社会保険・労働保険の手続き、福利厚生の管理、安全衛生管理
従業員が安心して、やりがいを持って働ける環境を整えることで、組織全体の活性化と生産性向上に貢献します。
総務・法務:円滑な企業運営と法的リスク管理を担う
総務・法務は、他の部門が担当しない、企業運営に必要なあらゆる業務を引き受ける「何でも屋」のような存在です。
その業務範囲は非常に広く、会社全体の土台を支えています。
- 総務業務:オフィス環境の整備(レイアウト変更、備品管理、清掃)、社内規程の管理、株主総会・取締役会の運営、社内イベントの企画・運営、受付業務、代表電話対応、文書管理
- 法務業務:契約書の作成・レビュー、コンプライアンス(法令遵守)体制の構築・推進、知的財産(特許、商標など)の管理、訴訟・紛争対応、顧問弁護士との連携
総務は従業員が快適に働ける環境づくりを。
法務は企業を法的なリスクから守るという、それぞれに重要なミッションを持っています。
その他:情報システム、経営企画、営業事務など
上記以外にも、バックオフィスにはさまざまな職種が存在します。
- 情報システム:社内ネットワークやサーバーの構築・運用・保守、業務システムの開発・導入支援、PCやIT機器の管理、セキュリティ対策、従業員からのITに関する問い合わせ対応(ヘルプデスク)
- 経営企画:中長期的な経営戦略の立案、市場調査・分析、新規事業の企画・推進、M&Aの検討、経営会議の運営
- 営業事務:営業担当者のサポート業務全般(見積書・請求書の作成、受発注管理、納期調整、顧客データ管理、電話・メール対応など)
これらの部門も、それぞれの専門性を活かして、企業の成長と円滑な運営に貢献しています。
バックオフィスが抱えがちな3つの課題|あなたの悩みは?
企業の根幹を支えるバックオフィスですが。
多くの企業で共通の課題を抱えています。
ここでは、代表的な3つの課題について掘り下げていきます。
あなたの会社にも当てはまるものがないか、チェックしてみてください。
課題1:慢性的な人手不足と業務の属人化
バックオフィス部門の課題として最も多く聞かれるのが、人手不足です。
特に中小企業では、一人の担当者が複数の業務を兼任しているケースも少なくありません。
経理と総務を一人で担当している、といった話も珍しくないでしょう。
このような状況は、業務の「属人化」を招きます。
属人化とは、特定の業務が特定の人にしかできなくなり、その人でなければ仕事が進まない状態のことです。
マニュアルが整備されておらず、長年の経験と勘に頼って業務をおこなっていると。
担当者が急に休んだり、退職してしまったりした場合に、業務が完全にストップしてしまうリスクがあります。
引継ぎも困難になり、新しい人材の育成にも時間がかかってしまいます。
課題2:なくならない紙文化と非効率なアナログ業務
多くの企業で、請求書や契約書、各種申請書など、いまだに多くの書類が「紙」でやり取りされています。
これらの書類を印刷し、ハンコを押し、ファイリングして保管する...といった一連の作業は、非常に手間と時間がかかります。
- 書類の印刷、封入、郵送作業に時間がかかる
- 承認を得るために、複数の部署を書類がたらい回しにされる(ハンコリレー)
- 過去の書類を探し出すのに時間がかかる
- 保管スペースがオフィスを圧迫する
- テレワークの導入を阻害する要因になる
こうしたアナログな業務は、従業員の生産性を低下させるだけでなく。
印刷代や郵送費、保管コストといった物理的なコストも発生させます。
また、人的なミスも起こりやすくなります。
課題3:評価されにくい?「減点方式」と「名もなき仕事」の心理的負担
バックオフィス業務は、ミスなくできて当たり前。
何か問題が起きたときだけ注目される「減点方式」で評価されがちな側面があります。
直接的な利益を生み出す部門ではないため、その貢献度が可視化しにくく。
正当な評価を得られていると感じにくい人もいるかもしれません。
また、マニュアルには書かれていないような細々とした「名もなき仕事」が多いのも特徴です。
「誰かがやらなければいけないけれど、担当が明確でない仕事」が、自然とバックオフィスの担当者に集まってくるのです。
こうした業務は、やっても感謝されることは少なく。
かといってやらなければ業務が滞ってしまうため、担当者の心理的な負担につながりやすいといえます。
バックオフィス業務を効率化する4つの基本ステップ
バックオフィスが抱える課題を解決し、生産性を向上させるためには、業務効率化への取り組みが不可欠です。
ここでは、誰でも始められる業務効率化の基本的な4つのステップを紹介します。
Step1. 業務内容の可視化(棚卸し)で現状を把握する
まずは、バックオフィス部門でおこなっている全ての業務を洗い出し、「見える化」することから始めます。
誰が、いつ、何を、どのように、どのくらいの時間をかけておこなっているのかを、一つひとつリストアップしていきましょう。
- 担当者ごとの業務内容と作業時間を書き出す
- 業務の流れ(プロセス)をフローチャートなどで図式化する
- 業務の発生頻度(毎日、毎週、毎月など)を記録する
この作業を通じて、「実はこんなに時間がかかっていたのか」「この業務は重複しているのではないか」といった、これまで気づかなかった課題や問題点が見えてきます。
現状を正確に把握することが、効率化の第一歩です。
Step2. 業務プロセスの標準化とマニュアル作成で属人化を防ぐ
次に、洗い出した業務の進め方やルールを統一し、「標準化」します。
担当者によってやり方がバラバラだと、品質にムラが出たり、業務の引継ぎがスムーズにいかなかったりする原因になります。
誰が担当しても同じ品質で業務を遂行できるよう、手順を標準化しましょう。
そして、標準化した業務プロセスを「マニュアル」に落とし込みます。
マニュアルがあれば、担当者が不在のときでも他の人が代わりに対応できますし、新入社員の教育にも役立ちます。
これにより、課題であった「属人化」を解消することができます。
マニュアルは一度作って終わりではなく、業務内容の変更に合わせて定期的に見直すことが重要です。
Step3. 不要な業務の削減とコア業務への集中
業務の可視化と標準化を進める中で、「この業務は本当に必要なのか?」と疑問に思う作業が出てくるはずです。
例えば、長年の慣習で続けているだけの報告書作成や、誰も見ていない資料のファイリングなど、やめても支障のない業務は思い切って廃止しましょう。
不要な業務をなくすことで、従業員は本来注力すべき「コア業務」(企業の利益に直結する付加価値の高い業務)に、より多くの時間とエネルギーを割くことができるようになります。
業務を「やめる」「減らす」「変える」という視点で、一つひとつの作業を見直してみましょう。
Step4. 課題に合わせた解決策(ツール導入・外注)を検討する
業務の整理が終わったら、残った業務をいかに効率的に進めるかを考えます。
ここで有効なのが、ITツールの導入やアウトソーシング(外注)の活用です。
- 単純な繰り返し作業が多いなら、自動化ツールを検討する
- 紙の書類が多いなら、ペーパーレス化できるシステムを探す
- 専門的な知識が必要な業務は、専門家に外注する
自社の課題や業務内容に合わせて、最適な解決策を選択することが重要です。
次の章で、具体的な解決策について詳しく解説します。
課題解決の具体策|DXツールとアウトソーシングの賢い活用法
業務の可視化と整理ができたら、いよいよ具体的な解決策の実行です。
ここでは、バックオフィス業務の効率化に大きく貢献する「DXツール」と「アウトソーシング」について、その活用法を詳しく解説します。
定型業務を自動化するRPA・AIなどのDXツール
DX(デジタルトランスフォーメーション)ツールとは、デジタル技術を活用して業務プロセスを変革し、生産性を向上させるためのツールの総称です。
特にバックオフィス業務と相性が良いのが、RPAやAIといった自動化ツールです。
- RPA(Robotic Process Automation):これまで人間がおこなってきたパソコン上の定型作業(データ入力、情報収集、ファイルの移動など)を、ソフトウェアのロボットが代行して自動化する技術です。24時間365日、ミスなく働き続けてくれるため、業務時間の大幅な短縮と品質向上が期待できます。
- AI(人工知能):請求書の読み取りと自動仕訳、問い合わせへの自動応答(チャットボット)など、RPAよりも高度な判断を伴う業務を自動化できます。AI-OCR(光学的文字認識)を使えば、紙の請求書をスキャンするだけで、内容をデータ化し、会計システムに自動で入力することも可能です。
その他にも、会計ソフト、給与計算ソフト、勤怠管理システム、ワークフローシステム(電子稟議)など、特定の業務に特化したクラウドサービスも数多く存在します。
これらを導入することで、アナログな業務を劇的に効率化し、ペーパーレス化を推進できます。
ノンコア業務を委託して生産性を向上させるアウトソーシング
アウトソーシングとは、自社の業務の一部を外部の専門業者に委託することです。
BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)とも呼ばれます。
特に、専門性は低いものの、手間のかかる「ノンコア業務」をアウトソーシングすることで、従業員はより付加価値の高い「コア業務」に集中できるようになります。
【アウトソーシングに適した業務の例】
- 経理:記帳代行、請求書発行、経費精算
- 人事・労務:給与計算、社会保険手続き、年末調整
- 総務:データ入力、文字起こし、スケジュール調整、リサーチ業務
アウトソーシングを活用すれば、人手不足を解消できるだけでなく、専門家のノウハウを活用することで、業務品質の向上も期待できます。
自社で新たに従業員を採用・育成するコストや手間を削減できる点も大きなメリットです。
【課題解決の近道】専門スキルを柔軟に活用できるオンラインアシスタントとは
「アウトソーシングしたいけど、どこに頼めばいいかわからない」「一部の業務だけ、少しだけ手伝ってほしい」そんなニーズに応えるのが、「オンラインアシスタント」というサービスです。
オンラインアシスタントは、経理、人事、総務、秘書、Webサイト運用など、さまざまなスキルを持つアシスタントに、必要な業務を必要な時間だけオンラインで依頼できるサービスです。
一人の従業員を雇用するよりもコストを抑えながら、まるで自社の従業員のように、柔軟に業務をサポートしてくれます。
- 月々の定額料金で、幅広い業務を依頼できる
- 採用や教育の手間なく、即戦力の人材を確保できる
- 業務量の増減に合わせて、柔軟に依頼内容を変更できる
人手不足や属人化といったバックオフィスが抱える課題を、スピーディーかつ低コストで解決する有効な手段として、近年注目を集めています。
守りから攻めへ!企業成長を加速させる「戦略的バックオフィス」の作り方
バックオフィス業務の効率化は、単なるコスト削減や負担軽減にとどまりません。
その先には、企業の成長を積極的に後押しする「攻めのバックオフィス」への変革があります。
コストセンターから企業の価値を創造するバリューセンターへ
従来、バックオフィスは利益を生まない「コストセンター」と見なされがちでした。
しかし、業務効率化によって定型業務から解放されたバックオフィスは、その専門知識やスキルを活かして、企業の価値創造に貢献する「バリューセンター」へと進化することができます。
例えば、経理部門が単に数値をまとめるだけでなく、蓄積された財務データを分析し、経営陣に収益改善のための具体的な提案をおこなう。
人事部門が従業員データを分析し、最適な人材配置や育成プランを立案する。
このように、バックオフィスが持つ専門性とデータを活用することで、経営戦略の精度を高めることができるのです。
データ活用と業務改善で経営に貢献するバックオフィスの未来像
これからのバックオフィスに求められるのは、日々の業務を正確にこなすだけでなく、常に改善意識を持ち、積極的に経営に関与していく姿勢です。
業務プロセスを常に見直し、より効率的な方法を模索する。
社内の各部門と連携し、業務上の課題を吸い上げて解決策を提案する。
そして、ITツールを積極的に活用し、収集したデータを分析して、経営判断に役立つインサイトを提供する。
こうした「攻めの姿勢」を持つバックオフィスは、もはや「後方支援」部隊ではありません。
フロントオフィスと両輪で企業の成長を牽引する、重要なビジネスパートナーとなるのです。
バックオフィス業務の変革は、企業全体の競争力を高めるための重要な経営課題といえるでしょう。
まとめ:バックオフィス業務の課題解決で、企業の成長を実現しよう
本記事では、バックオフィス業務の役割や仕事内容、多くの企業が抱える課題、そして業務効率化を実現するための具体的なステップと解決策について解説しました。
バックオフィスは、企業の土台を支える重要な存在です。
しかし、人手不足やアナログ業務といった課題を抱え、そのポテンシャルを十分に発揮できていないケースも少なくありません。
これらの課題を解決し、従業員がコア業務に集中できる環境を整えることは、企業全体の生産性向上と持続的な成長に不可欠です。
業務の可視化から始め、ITツールの導入やアウトソーシングを賢く活用することで、あなたの会社のバックオフィスは、コストセンターから企業の価値を創造する「戦略的バックオフィス」へと生まれ変わることができます。
もし、日々のノンコア業務に追われ、何から手をつけて良いかわからないと感じているなら、「Chatwork アシスタント」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
Chatwork アシスタントは、経理や人事、総務、秘書業務など、バックオフィス業務をオンラインでサポートします。
採用や教育の手間なく、必要なスキルを持つ人材に、必要な業務を、必要な時間だけ依頼できます。
まずは月10時間から、ノンコア業務をプロに任せて、あなたの会社を次のステージへと進めましょう。
バックオフィス業務の効率化は、未来への投資です。
この記事をきっかけに、ぜひ第一歩を踏み出してください。







