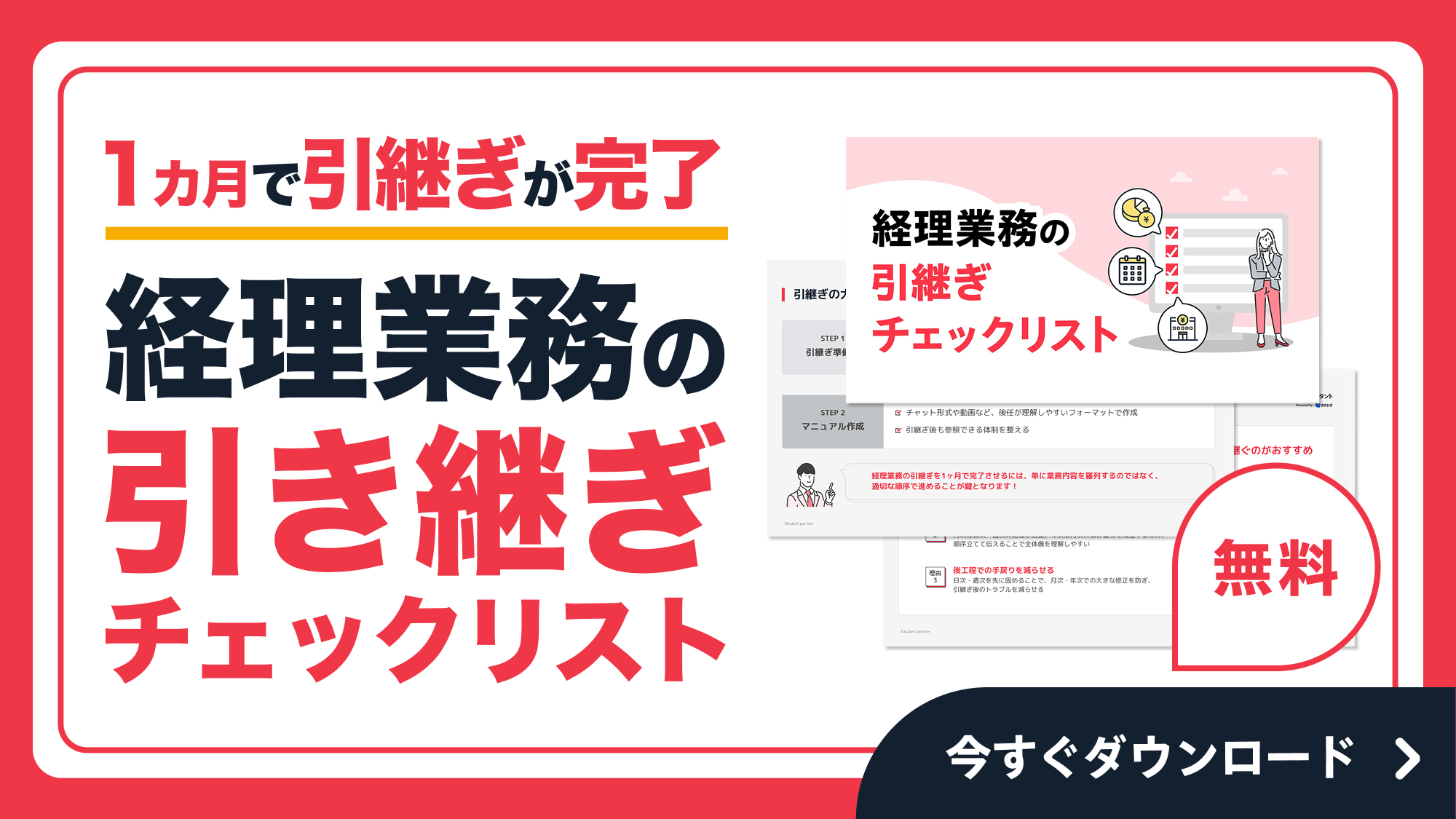決算代行とは?依頼先別の料金相場や必ず把握しておくべきこと、格安サービスの注意点も紹介

終わらない!

- リリースからわずか2年で
累計1000社以上が採用したサービス - 厳選された優秀なアシスタントが支援
- あらゆる経理業務を専門チームが代行
- 人手不足を解決し、安定した経理体制へ

目次
年に一度訪れる企業の重要業務が「決算」です。
決算のプロセスは、日々の記帳内容の確認から、膨大な量の書類作成、そして複雑な税金の計算まで多岐にわたり、専門的な知識と多くの時間を要するものです。
本記事では、決算の代行を外部に依頼するケースについて、概要や依頼できること、料金相場などを詳しく解説します。
決算代行(決算申告代行)とは
決算代行とは、企業が事業年度の終わりに必ず行わなければならない「決算」および「税務申告」に関する一連の業務を、外部の専門家へ依頼して実施してもらうことです。
企業の決算業務の中心となるのは、年間の取引を集計し、貸借対照表や損益計算書といった「決算書(財務諸表)」を作成する作業です。
作成した決算書をもとに、法人税や消費税などの納税額を計算し、税務署へ申告書を提出する「税務申告」を行います。
決算業務には、会計や税務に関する高度な専門知識が求められ、1つでも誤りがあれば追徴課税などのペナルティにつながるおそれもあります。
決算代行を依頼すると、主に税理士などの専門家が決算業務を正確かつ迅速に遂行してくれます。
そのため、決算の専門知識を持つ担当者が社内にいなくても、法律に準拠した適正な決算と税務申告を行うことが可能になります。
決算代行で依頼できる業務範囲
決算代行がカバーする業務範囲は非常に広く、企業のニーズに応じて依頼内容を調整することが可能です。
一般的に、決算日から税務申告完了までの、以下のような一連の業務を依頼できます。
1. 記帳内容の確認・監査
年間を通じて記帳されてきた会計帳簿(総勘定元帳など)の内容を、専門家の視点でチェックします。
勘定科目の誤りがないか、証憑(領収書や請求書)と帳簿の内容が一致しているかなどを確認し、決算書作成の前提となるデータの正確性を担保します。
2. 決算整理仕訳の作成
決算日時点での正確な財政状態と経営成績を反映させるため、「決算整理仕訳」という特殊な会計処理を行います。
具体的には、減価償却費の計上、売掛金や買掛金の残高確認、棚卸資産の評価、経過勘定(未払費用や前払費用など)の計上といった作業が含まれます。
3. 決算書(財務諸表)の作成
すべての会計処理が完了した後、決算書を作成します。
決算書には、主に以下の書類が含まれます。
貸借対照表(B/S):決算日時点での企業の財産状況を示す書類。
損益計算書(P/L):一事業年度の経営成績(儲け)を示す書類。
キャッシュフロー計算書(C/F):一事業年度のお金の流れを示す書類。
株主資本等変動計算書:純資産の変動状況を示す書類。
4. 法人税・消費税などの税務申告書の作成
作成した決算書をもとに、税法に基づいた調整(税務調整)を行い、法人税や法人住民税、法人事業税、消費税の納税額を算出します。
このとき、各税額の計算過程と結果を記載した「税務申告書」を作成します。
なお、このプロセスの業務は税理士の独占業務です。
5. 税務申告書の提出(電子申告)
納税者である企業に代わり、作成した税務申告書を税務署や都道府県、市区町村へ提出します。
現在では、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用した電子申告が主流です。
この申告代理も、税理士の独占業務となります。
6. 納税額の通知と納付書の作成
最後に、確定した税金の納税額を企業へ通知し、納税を行うための納付書を作成します。
決算代行の依頼先、依頼方法
決算代行の依頼先は、主に3種類に分けられます。
それぞれの特徴、特に法律上の業務範囲の違いを理解することが極めて重要です。
1. 税理士事務所・会計事務所
【特徴】
決算および税務申告の専門家である税理士が所属する事務所です。
最大の強みは、税理士の独占業務である「税務申告書の作成」と「税務代理(申告書の提出)」を含めた一連の決算プロセスをワンストップで依頼できる点です。
また、節税に関するアドバイスや、税務調査の際の対応など、税務に関する包括的なサポートを受けることもできます。
【依頼方法・プラン】
年に一度の決算・申告のみを単発で依頼する「スポット契約」と、月々の記帳代行や税務相談を含む「顧問契約」の2種類が主な依頼方法です。
2. 経理代行会社・記帳代行会社
【特徴】
日々の記帳業務や、決算書作成までの経理実務を専門に行う会社です。
税理士事務所と比較して、記帳や書類作成などの料金は比較的安価な傾向があります。
ただし、税理士資格を持たない人に依頼する場合、税務申告書の作成や税務代理を行ってもらうことは法律で禁じられています。
そのため、最終的な税務申告は、依頼先と提携している税理士に依頼するか、自社で別途税理士を探して依頼する必要があります。
【依頼方法・プラン】
決算書作成までを依頼するスポット契約や、月々の記帳代行契約が中心となります。
3. オンラインアシスタントサービス
【特徴】
オンライン上で、経理を含む様々なバックオフィス業務をサポートするサービスです。
主に、領収書の整理やデータ入力、決算に必要な資料の準備といった、決算業務の「前段階」の作業を、時間単位の契約で柔軟に依頼できるのが特徴です。
経理代行会社と同様、税理士資格を持たない人に依頼する場合は、税務申告そのものを代行してもらうことはできません。
【依頼方法・プラン】
月々の実働時間に応じた月額料金を支払うケースが一般的です。
多くは、サービスごとに何種類かのプランが用意されています。
【依頼先別】決算代行の依頼費用相場
決算代行を依頼する際の費用は、依頼先や企業の売上規模、記帳の状況によって大きく変動します。
ここでは、依頼先別の料金相場を紹介します。
税理士事務所に依頼する場合の費用相場
税理士事務所への依頼費用は、「決算申告料」として年に一度支払うのが基本です。
日々の記帳を自社で行っているか(記帳代行を依頼しないか)どうかによって、料金は大きく変わります。
【記帳代行なし・決算申告のみの料金相場】
一年間の会計帳簿は自社で作成し、そのチェックと決算・申告作業のみを依頼するケースです。
| 年間売上高 | 料金相場 |
|---|---|
| ~1,000万円 | 10万円 ~ 20万円 |
| 1,000万円 ~ 3,000万円 | 15万円 ~ 25万円 |
| 3,000万円 ~ 5,000万円 | 20万円 ~ 30万円 |
| 5,000万円 ~ 1億円 | 25万円 ~ 40万円 |
【記帳代行あり(丸投げ)の場合】
領収書や通帳のコピーなどをすべて渡し、一年分の記帳から決算・申告までをまとめて依頼するケースです。
上記の決算申告料に、年間の記帳代行料(月額1~3万円×12ヶ月分など)が追加され、総額は30万円~60万円以上になることが一般的です。
経理代行会社などに依頼する場合
経理代行会社に決算書作成までを依頼する場合、上記の税理士事務所の相場から、税務申告に関する部分を差し引いた料金(おおむね税理士事務所の7割~8割程度)が目安となります。
税務申告を税理士へ別途依頼する費用(5万円~10万円程度)が追加で発生するため、トータルの費用を比較検討する必要があります。
「格安」の決算代行サービスについて
インターネット上では、「決算申告料5万円~」などのように、格安をうたう決算代行サービスも見られます。
このような格安サービスは、記帳が完璧に完了していることが前提であったり、最低限の申告書を作成するだけで一切の相談やレビューが含まれなかったりするケースがほとんどです。
そのため、節税の検討や、将来の経営を見据えたアドバイスは期待できません。
料金の安さだけで選ぶと、後から追加料金を請求されたり、税務上のリスクを見逃したりする可能性があるため、サービス内容を十分に確認することが重要です。
決算代行を依頼するメリット
ここでは、決算代行を外部へ依頼するメリットを紹介します。
メリット1:正確な決算と適正な税務申告
会計と税務のプロフェッショナルである税理士へ依頼する場合、法律に準拠した正確な決算書と税務申告書を作成してもらえることが最大のメリットです。
専門的な知識が必要な税務調整や、複雑な控除・優遇税制の適用などを的確に行ってもらえる結果、申告ミスによる追徴課税や延滞税といった税務リスクを回避し、コンプライアンスを遵守した健全な経営を実現できます。
メリット2:担当者の業務負担軽減とコア業務への集中
決算・申告業務は、非常に多くの時間と精神的な労力を要する作業です。
経理担当者がこの煩雑な業務から解放されることで、本来注力すべき事業戦略の立案、営業活動、人材育成といった、企業の成長に直結する業務にリソースを集中させることができます。
メリット3:適切な節税対策
税理士は申告書を作成するだけではなく、企業の状況を分析し、法律の範囲内で納税額を適正に抑えるための様々な節税対策を提案してくれます。
役員報酬の最適な設定、設備投資に関する優遇税制の活用、消費税の有利な計算方法の選択など、専門家ならではの視点から節税のアドバイスを受けられます。
そのため、代行料金以上のコストパフォーマンスを期待できるケースも少なくありません。
メリット4:社会的信用の向上と資金調達の円滑化
税理士が作成し、署名・捺印した決算書や申告書は、金融機関や取引先からの社会的信用が高まります。
特に、金融機関から融資を受ける際には、信頼性の高い決算書は審査において非常に重要な要素となります。
税理士が関与しているという事実は、企業の経理体制がしっかりしていることの証明となり、融資の審査を有利に進める効果が期待できます。
決算代行を依頼するデメリット
多くのメリットがある一方で、決算代行の依頼にはいくつかのデメリットや注意点も存在します。
デメリット1:代行費用がかかる
当然のことながら、専門家に依頼するには一定の料金が必要です。
企業の規模や状況によっては、数十万円の費用が発生します。
事業を始めたばかりで資金的に余裕がない場合や、取引が非常にシンプルで自力で申告できる場合には、この費用が負担に感じられる可能性があります。
ただし、申告ミスによるペナルティのリスクや、専門家による節税効果を考慮すると、費用対効果は高いと判断できる場合が多いでしょう。
デメリット2:社内に経理・税務のノウハウが蓄積されにくい
決算・申告業務をすべて外部に委託してしまうと、その業務に関する詳細な知識や、税法改正への対応経験といったノウハウが社内に蓄積されにくくなります。
将来的に経理部門を内製化したいと考えた際に、一から人材を育成する必要が生じる可能性があります。
完全に任せきりにするのではなく、税理士から決算内容について詳細な説明を受けるなど、自社の財務状況を理解しようとする姿勢が重要です。
デメリット3:会計資料の準備に手間がかかる
決算代行は「丸投げ」できるわけではありません。
税理士が決算業務を行うためには、一年分の領収書、請求書、通帳のコピー、総勘定元帳といった、会計に関するあらゆる資料を、依頼者である企業側が整理して準備する必要があります。
日々の記帳を自社で行っていない場合は、この資料準備の作業が大きな負担となることがあります。
決算代行を依頼するかどうかの判断基準
自社で決算を行うべきか、それとも代行を依頼すべきか。迷った際には、以下の基準で判断することをおすすめします。
1. 経理・税務に関する専門知識を持つ人材が社内にいるか
法人税の申告は、簿記の知識だけでなく、複雑な税法の知識が不可欠です。
もし社内に、決算から法人税申告までを一人で完結できるレベルの専門知識を持つ人材がいないのであれば、無理に自社で行うことは大きなリスクを伴います。
このような場合は、迷わず専門家である税理士への依頼を検討すべきでしょう。
2. 経営者や従業員の時間をコア業務に集中させたいか
たとえ自社で対応できる知識があったとしても、決算・申告業務には多くの時間がかかります。
その時間を、経営者や従業員が、売上を上げるための活動や、事業を成長させるための戦略策定に費やした方が、企業全体にとっての利益が大きくなる場合があります。
「時は金なり」の観点から、決算業務にかかる時間の人件費と、代行料金を比較して、どちらが合理的かを判断しましょう。
3. 税務調査や資金調達への備えをしたいか
決算代行を税理士に依頼することは、単なる事務作業のアウトソーシング以上の意味を持ちます。
税理士との関与は、税務調査の際に心強い味方となってくれるだけでなく、金融機関からの信用を高め、資金調達を有利に進める効果も期待できます。
事業の安定と将来の成長を見据え、専門家とのパートナーシップを築きたいと考えるのであれば、代行依頼は有効な投資といえます。
決算代行依頼に必要な書類
税理士に決算代行をスムーズに進めてもらうためには、事前の書類準備が欠かせません。
依頼する際には、一般的に以下のような書類の提出を求められます。
会社の基本情報に関する書類
定款のコピー
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のコピー
過去3期分の法人税申告書の控え
税務署や都道府県、市区町村から送付された届出書類の控え
会計帳簿・取引記録に関する書類
総勘定元帳、仕訳帳(会計ソフトで作成している場合はそのデータ)
一年分の領収書、請求書、契約書などの証憑書類
すべての事業用預金通帳のコピー(期末までの記帳が済んだもの)
クレジットカードの利用明細
借入金の返済予定表
資産・負債・在庫に関する書類
固定資産台帳(PC、車両、機械などの一覧)
期末時点での売掛金と買掛金の一覧
期末時点での在庫の一覧(棚卸表)
従業員・労務に関する書類
従業員名簿
賃金台帳
源泉徴収簿
日々の記帳を自社で行っていない場合は、一年分の証憑書類をすべて整理して提出する必要があります。
決算代行依頼の注意点
決算代行の依頼を成功させ、トラブルを避けるために注意すべき点を3つご紹介します。
注意点1:依頼先が税理士(事務所)であるかを確認する
繰り返しになりますが、税務申告書の作成と税務代理は、法律で定められた税理士の独占業務です。
「格安」をうたう経理代行会社の中には、この法律を無視して税務申告まで請け負う違法な業者が存在する可能性があります。
そのような業者に依頼してしまうと、申告内容の品質が低いだけでなく、企業側も税務上のリスクを負うことになります。
必ず、依頼先が正規の税理士または税理士法人であることを確認してください。
注意点2:期限ギリギリの依頼は避ける
企業の決算申告期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。
この期限直前になってから依頼しても、税理士のスケジュールが埋まっていて断られてしまったり、通常よりも高額な「特急料金」を請求されたりする可能性があります。
また、短い期間では十分なレビューや節税対策の検討ができず、質の高いサービスを受けられないかもしれません。
決算月が終わったら、できるだけ速やかに相談を開始するのが理想です。
注意点3:料金に含まれるサービス範囲を明確にする
契約前には、見積もり金額にどこまでの業務が含まれているのかを、書面で詳細に確認することが重要です。
例えば、記帳代行、年末調整、償却資産税の申告、税務調査の立ち会いなどは、基本の決算申告料とは別料金になっていることが一般的です。
後から「これは追加料金です」と言われるようなトラブルを避けるため、料金とサービス範囲に関する認識を、依頼先と完全に一致させておきましょう。
決算代行依頼なら『Chatwork 経理アシスタント』がおすすめ!
「顧問税理士はいるけれど、決算のために一年分の領収書を整理したり、帳簿をチェックしたりする準備作業が大変」。
「税理士に丸投げで依頼すると費用が高くなるので、日々の記帳だけでも安価に、でも正確にやっておきたい」。
このように、決算申告そのものではなく、その「前段階」の経理業務に課題を抱えている企業に最適なサービスが、『Chatwork 経理アシスタント』です。
『Chatwork 経理アシスタント』は、税理士の独占業務である税務申告を行うサービスではありません。
日々の領収書の整理やデータ入力、記帳代行、月次試算表の作成といった、決算の土台となる日常の経理業務を、経験豊富なオンラインアシスタントがサポートするサービスです。
このサービスを活用して日々の経理を正確に処理しておくことで、決算期には、整理された信頼性の高いデータを、スムーズに顧問税理士へ引き継ぐことができます。
結果として、税理士の作業負担が軽減され、決算申告料を安く抑えられる可能性もあります。
Chatwork 経理アシスタントを導入するメリット
『Chatwork 経理アシスタント』を活用することで、決算業務の準備を効率化し、経理部門全体の生産性を向上させることができます。
メリット1:決算準備の負担を大幅に削減
決算期に慌てて一年分の領収書を整理する必要がなくなります。
日々発生する領収書をスマートフォンで撮影して送るだけで、アシスタントが整理・データ入力を行ってくれます。
月次で試算表を作成してもらうことで、年間を通じて自社の経営状況をリアルタイムに把握し、決算期の予測も立てやすくなります。
決算直前の膨大な準備作業から解放されます。
メリット2:低コストで経理体制を構築できる
経理担当者を一人雇用する場合と比較して、月額数万円からというリーズナブルな料金で、プロの経理サポートを受けることができます。
採用や教育の手間とコストをかけることなく、質の高い経理体制をスピーディーに構築できます。
コストを抑えながら、正確な月次決算の体制を整えたい企業にとって、費用対効果が非常に高い選択肢です。
メリット3:税理士との円滑な連携
Chatwork上で、自社の担当者、経理アシスタント、そして顧問税理士が同じグループチャットに入り、シームレスに情報共有を行うことも可能です。
アシスタントが作成したデータを税理士が直接確認し、不明点をチャットで質問するといった、効率的な連携が実現します。
この透明性の高いコミュニケーションが、決算業務全体のスピードと正確性を高めます。
まとめ
本記事では、決算代行について、依頼できる業務範囲や料金相場、メリット・デメリットなどを解説しました。
決算と税務申告は、すべての企業に課された義務であり、企業の経営成績と財政状態を内外に示す、年に一度の総仕上げとなる重要な業務です。
この専門性が高く責任の重い業務を、信頼できる専門家、すなわち税理士に委託することは、多くの企業にとって合理的な経営判断です。
自社が抱える課題と外部に求めたい範囲とを明確にし、適切な代行依頼先を見つけてください。