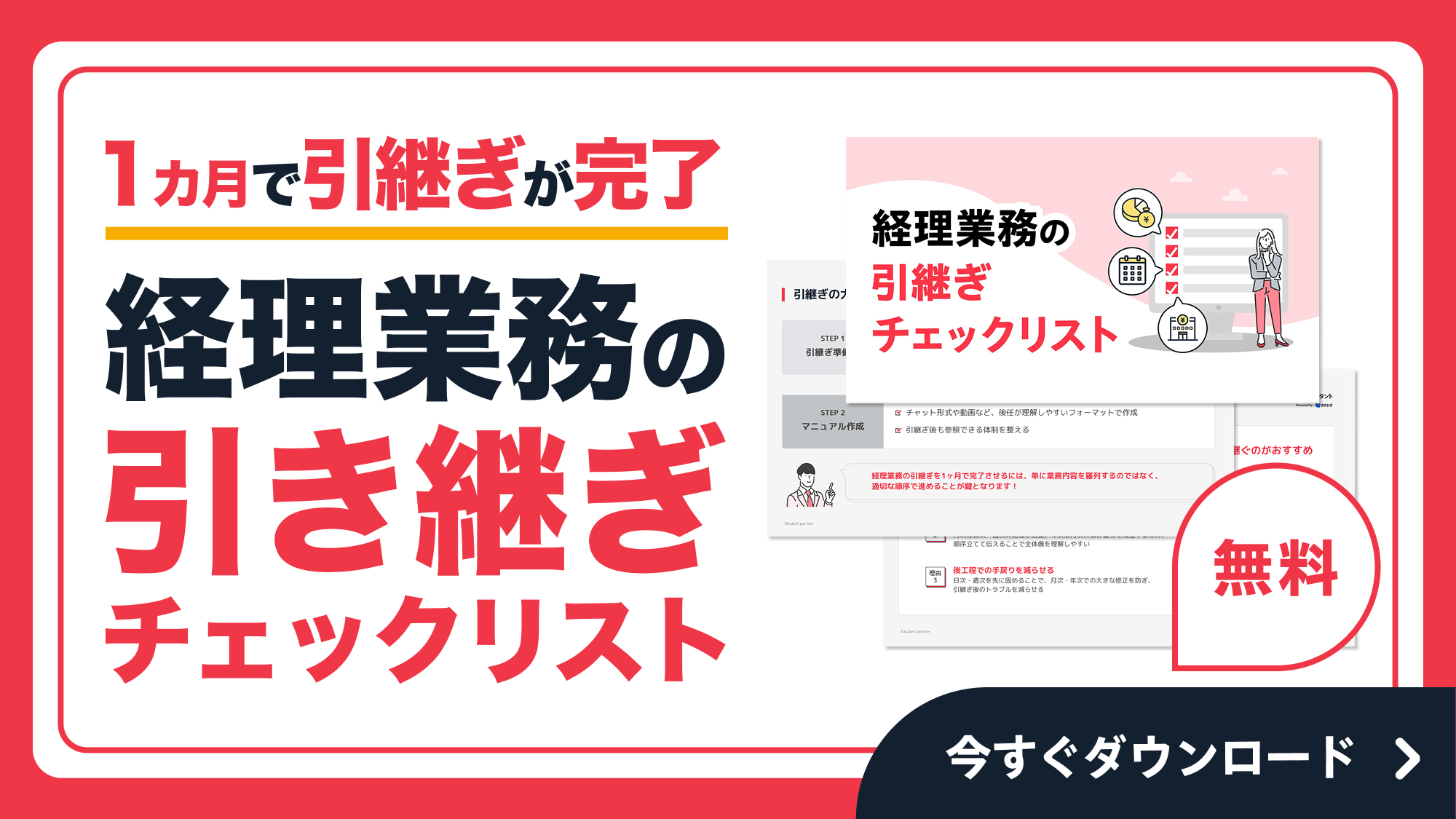経費精算代行とは?メリット・デメリット、費用相場や選び方を徹底解説
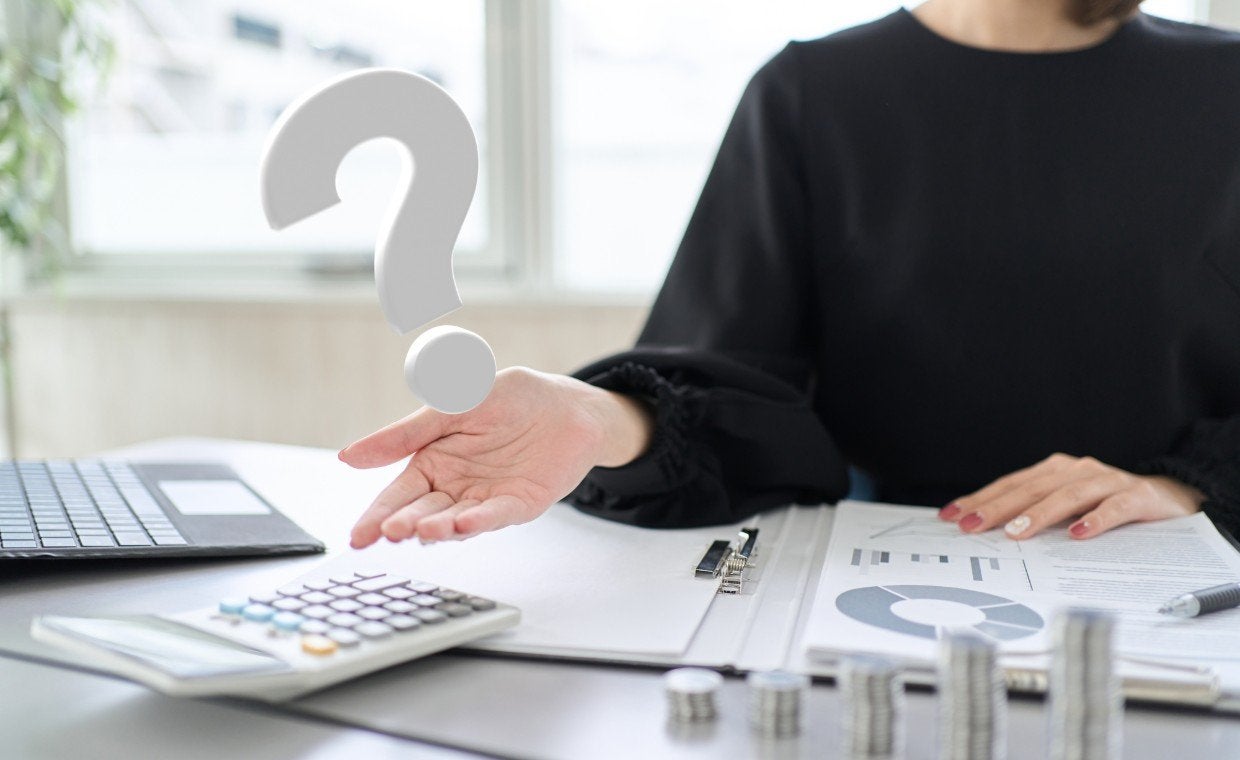
終わらない!

- リリースからわずか2年で
累計1000社以上が採用したサービス - 厳選された優秀なアシスタントが支援
- あらゆる経理業務を専門チームが代行
- 人手不足を解決し、安定した経理体制へ

目次
「毎月の経費精算業務に追われて、本来やるべき仕事に集中できない...」そんな悩みを抱えていませんか?
経費精算は、企業にとって不可欠な業務ですが、申請内容の確認や入力作業など、手間のかかる作業が多いのも事実です。
これらの業務を外部の専門家に委託する「経費精算代行」は、経理担当者の負担を軽減し、生産性を向上させる有効な手段として注目されています。
この記事では、経費精算代行の基本的な知識から、具体的なメリット・デメリット、費用相場、そして自社に最適なサービスを選ぶためのポイントまで、網羅的に解説します。
この記事を読めば、あなたの会社の経理業務を効率化し、事業をさらに成長させるためのヒントが見つかるはずです。
経費精算代行とは?面倒な業務から解放されよう
経費精算代行とは、社内で行っている経費精算に関する一連の業務を、外部の専門業者に委託することです。
領収書のチェックやデータ入力、振込処理といったノンコア業務を専門家に任せることで、経理担当者はより付加価値の高いコア業務に集中できるようになります。
人手不足が深刻化する現代において、限られたリソースを最大限に活用し、企業全体の生産性を向上させるための有効な選択肢として、多くの企業で導入が進んでいます。
経費精算代行が注目される背景
近年、経費精算代行サービスが注目を集めている背景には、いくつかの要因があります。
第一に、働き方改革の推進により、業務効率化への意識が高まっていることが挙げられます。
単純作業でありながら時間のかかる経費精算業務をアウトソーシングすることで、従業員はより創造的で重要な業務に時間を使うことができます。
第二に、電子帳簿保存法やインボイス制度といった法改正への対応が複雑化している点です。
専門知識を持つ代行業者に委託すれば、法改正にも迅速かつ正確に対応でき、コンプライアンス遵守の観点からも安心です。
さらに、深刻な人手不足も大きな要因です。
特に中小企業では、経理担当者の採用や育成が難しく、一人の担当者に業務が集中しがちです。
アウトソーシングを活用することで、採用コストを抑えつつ、安定した業務運用が可能になります。
▷経費精算はアウトソーシングで手間削減!メリットや注意点・業者の選び方は?
経費精算代行の主なサービス提供形態
経費精算代行サービスは、大きく分けて2つの提供形態があります。
一つは、経理業務全般を請け負うBPO(「Business Process Outsourcing」の略:業務の外注化)事業者が提供するサービスです。
経費精算だけでなく、記帳代行や給与計算、決算業務まで幅広い経理業務をまとめて委託でき、経理部門全体をスリム化したい企業に適しています。
もう一つは、オンラインアシスタントサービスです。
必要な業務を必要な分だけ、柔軟に依頼できるのが特徴です。
経費精算業務の一部だけを委託したい、繁忙期だけ人手を増やしたいといったニーズに細かく対応できます。
また、スモールスタートでアウトソーシングを試してみたい企業にもおすすめです。
経費精算システムとの違い
経費精算の効率化を考えるうえで、代行サービスとよく比較されるのが「経費精算システム」の導入です。
経費精算システムは、申請から承認、精算までの一連の流れをデジタル化し、効率化を図るツールです。
申請者はスマートフォンアプリから領収書を撮影して申請でき、承認者もオンラインで完結できます。
このように、手入力や紙のやり取りをなくすことで、業務時間を大幅に削減できるのが魅力です。
一方、経費精算代行は、システム化された業務も含め、「人」が対応する業務そのものを外部に委託するサービスです。
最終的なチェックや仕訳作業、イレギュラーな対応など、システムだけではカバーしきれない部分を専門スタッフが代行します。
どちらか一方を選ぶだけでなく、経費精算システムを導入したうえで、一部の業務を代行サービスに委託するという「ハイブリッド型」も有効な選択肢です。
経費精算代行で委託できる業務範囲はどこまで?
経費精算代行サービスに委託できる業務は、非常に多岐にわたります。
自社の課題に合わせて、必要な業務を柔軟に組み合わせることが可能です。
ここでは、一般的な委託可能業務の範囲を紹介します。
基本的な経費精算業務
まずは、経費精算の基本的なフローに関する業務です。
これらの定型的な作業を委託するだけでも、経理担当者の負担は大きく軽減されます。
- 申請内容のチェック(領収書と申請書の突合、規定違反の確認)
- 会計ソフトへの仕訳データ入力
- 従業員への立替経費の振込・支払い処理
- 未精算者への督促連絡
- 経費精算に関する問い合わせ対応
経費精算に付随する経理業務
経費精算だけでなく、それに関連する経理業務もまとめて委託できる場合があります。
これにより、経理部門全体の業務効率化が期待できます。
- 請求書の支払い代行
- 売掛金・買掛金の管理
- 月次決算のサポート
- 経費精算システムの導入・運用サポート
- 業務フローの改善コンサルティング
注意:税理士の独占業務は委託できない
アウトソーシングする際に注意が必要なのは、税理士法で定められた「独占業務」です。
具体的には、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つは、税理士の資格を持つ人でなければ行うことができません。
経費精算代行業者は、これらの税務判断を伴わない範囲での業務を請け負います。
もし税務申告や専門的な税務相談まで依頼したい場合は、税理士事務所や税理士法人が提供する経理代行サービスを選ぶ必要があります。
自社がどこまでの業務を委託したいのかを明確にし、適切な依頼先を選定することが重要です。
経費精算代行のメリット4つとデメリット3つ
経費精算代行は多くのメリットをもたらしますが、一方で注意すべきデメリットも存在します。
導入を成功させるためには、双方を正しく理解し、自社の状況と照らし合わせて検討することが不可欠です。
経費精算代行を活用する4つのメリット
まずは、経費精算代行を導入することで得られる主なメリットを4つ紹介します。
メリット1:コア業務への集中と生産性向上
最大のメリットは、経理担当者をノンコア業務から解放し、より付加価値の高いコア業務に集中させられる点です。
経費精算のような定型業務をアウトソーシングすることで、経理担当者は財務分析や資金繰り改善、経営戦略の立案サポートといった、企業の成長に直結する業務に時間とエネルギーを注ぐことができます。
これにより、従業員のモチベーション向上と企業全体の生産性向上が期待できます。
メリット2:人件費・採用コストの削減
経理担当者を一人雇用するには、給与だけでなく社会保険料や採用・教育コストなど、多くの費用がかかります。
特に中小企業にとっては、この負担は決して小さくありません。
経費精算代行を利用すれば、必要な業務を必要な分だけ委託できるため、人件費を固定費から変動費に変えることができます。
結果として、トータルコストを大幅に削減できる可能性があります。
メリット3:属人化の解消と不正防止(ガバナンス強化)
経理業務が一人の担当者に集中していると、その担当者が休職や退職した場合に業務が滞ってしまう「属人化」のリスクがあります。
また、チェック体制が不十分だと、カラ出張や経費の水増し請求といった不正行為が起こりやすくなります。
代行サービスを利用すれば、業務フローが標準化され、第三者の客観的な視点が入るため、属人化の解消と内部統制の強化につながります。
▷経理業務が属人化しやすい原因とは?属人化のリスクや解消する方法を解説
▷経理が属人化する要因はマニュアルがないから?作成方法と業務効率化のポイントを解説
メリット4:法改正へのスムーズな対応
電子帳簿保存法やインボイス制度など、経理に関わる法律は頻繁に改正されます。
これらの情報を常にキャッチアップし、正確に対応していくのは大変な労力が必要です。
その点、経理の専門家である代行業者であれば、最新の法令に準拠した形で適切に業務を処理してくれます。
法改正への対応漏れといったリスクを回避し、コンプライアンスを遵守した経営が可能になります。
経費精算代行の3つのデメリットと対策
次に、導入前に知っておくべきデメリットと、その対策について解説します。
デメリット1:社内にノウハウが蓄積されにくい
経費精算業務を完全に外部委託してしまうと、社内に実務的なノウハウが蓄積されにくくなるという側面があります。
将来的に内製化に戻すことを考えた際に、業務フローがわからなくなってしまったり、対応できる人材がいなくなってしまったりする可能性があります。
対策としては、委託先に業務フローのマニュアル化を依頼したり、定期的にレポーティングを受けたりすることで、社内でも業務内容を把握できる体制を整えておくことが重要です。
デメリット2:情報漏えいのリスクがある
経費精算に関するデータには、従業員の個人情報や取引先の情報など、多くの機密情報が含まれます。
これらの情報を外部に預けることになるため、情報漏えいのリスクはゼロではありません。
万が一、情報が漏えいしてしまった場合、企業の信用問題に発展する可能性があります。
対策として、委託先を選定する際には、プライバシーマーク(Pマーク)やISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証を取得しているかなど、セキュリティ体制を厳しくチェックすることが不可欠です。
契約時には、秘密保持契約(NDA)を締結することも忘れないようにしましょう。
デメリット3:緊急時の対応に時間がかかる場合がある
社内で業務を行っていれば、急な修正や確認が必要になった場合でもすぐに対応できます。
しかし、外部に委託している場合は、コミュニケーションにタイムラグが生じ、対応が遅れてしまう可能性があります。
特に、海外の業者に委託する場合などは、時差や言語の壁も考慮する必要があります。
対策としては、委託先の営業担当者や実務担当者と、日頃から円滑なコミュニケーションが取れるかを確認しておくことが大切です。
チャットツールやWeb会議システムなど、迅速に連絡が取れる手段を確保しているかどうかも、選定のポイントになります。
経費精算代行の費用相場と料金体系
経費精算代行の導入を検討するうえで、最も気になるのが費用ではないでしょうか。
料金体系はサービス会社によってさまざまですが、主に「月額固定制」と「従量課金制」の2種類に分けられます。
自社の業務量や予算に合わせて、最適なプランを選ぶことが重要です。
▷経理代行の料金相場とは?業務別の料金目安や依頼できる業務を解説
料金体系の種類(月額固定制・従量課金制)
まずは、主な料金体系の特徴を理解しましょう。
| 料金体系 | 特徴 | 向いている企業 |
|---|---|---|
| 月額固定制 |
|
|
| 従量課金制 |
|
|
【業務別】経費精算代行の費用相場
次に、委託する業務内容ごとの費用相場を見ていきましょう。
これはあくまで目安であり、企業の規模や業務の複雑さによって変動します。
記帳代行の費用相場
領収書の整理や会計ソフトへの入力といった記帳代行は、従量課金制の場合「1仕訳あたり50円~100円」程度が相場です。
月額固定制の場合は、仕訳数に応じて変動し、「月100仕訳までで1万円前後」からが目安となります。
給与計算・振込代行の費用相場
給与計算や従業員への振込代行は、従業員数に応じて料金が設定されることが多く、「従業員1人あたり月額1,000円~2,000円」が相場です。
年末調整などのスポット業務は、別途料金が必要になる場合があります。
決算・税務申告の費用相場
決算書の作成や法人税の申告といった専門的な業務は、企業の売上規模や業務の複雑さによって大きく変動します。
小規模な企業であれば「15万円~」、大規模になると「50万円以上」になることもあります。
これらの業務は税理士の独占業務となるため、税理士事務所への依頼が基本です。
費用を抑えるためのポイント
コストパフォーマンスを高めるためには、いくつかのポイントがあります。
まず、委託したい業務の範囲を明確にすることです。
「どこからどこまでを任せたいのか」を整理することで、不要なオプションを省き、最適なプランを選ぶことができます。
また、領収書を整理しておく、申請ルールを統一するなど、社内でできる準備を整えておくことも重要です。
代行業者側の作業負担を減らすことで、結果的に費用を抑えられる可能性があります。
複数の業者から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することも忘れないようにしましょう。
失敗しない経費精算代行サービスの選び方5つのポイント
数多くの経費精算代行サービスの中から、自社に最適な一社を見つけ出すのは簡単なことではありません。
ここでは、サービス選定で失敗しないための5つの重要なポイントを解説します。
ポイント1:委託したい業務範囲に対応しているか
まず最も重要なのが、自社が委託したい業務内容にサービスが対応しているかを確認することです。
単に領収書のチェックと入力だけを任せたいのか、それとも振込業務や月次レポートの作成までお願いしたいのか、まずは社内の要望を明確にしましょう。
そのうえで、各サービスの提供範囲を詳細に比較し、自社のニーズに過不足なく応えてくれるサービスを選ぶことが大切です。
将来的に委託範囲を拡大する可能性も視野に入れておくと、より長期的な視点で選定できます。
ポイント2:セキュリティ対策は万全か
経費精算業務では、個人情報や財務情報といった機密性の高いデータを取り扱います。
そのため、委託先のセキュリティ体制は徹底的に確認する必要があります。
具体的には、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である「ISMS認証」や、個人情報の適切な取り扱いを証明する「プライバシーマーク(Pマーク)」を取得しているかは、信頼性を判断するうえでの大きな指標となります。
契約前には、秘密保持契約(NDA)の内容もしっかりと確認しましょう。
ポイント3:自社の規模や業種での実績は豊富か
代行サービスの実績を確認することも重要です。
特に、自社と同じくらいの企業規模や、同じ業種の企業をサポートした実績が豊富であれば、業界特有の慣習や経理処理にも精通している可能性が高く、スムーズな業務遂行が期待できます。
公式サイトの導入事例などを参考に、どのような企業がどのような目的でそのサービスを利用し、どんな成果を得ているのかを確認してみましょう。
ポイント4:料金体系は明確で予算に合っているか
料金体系が明確で、分かりやすいかどうかも重要な選定基準です。
基本料金に含まれるサービス範囲はどこまでで、どこからがオプション料金になるのかを事前にしっかりと確認し、追加費用の発生で後からトラブルにならないようにしましょう。
複数の会社から見積もりを取り、サービス内容と料金のバランスを比較検討することが、コストパフォーマンスの高いサービスを選ぶコツです。
安さだけで選ぶのではなく、品質やサポート体制とのバランスを総合的に判断することが大切です。
▷経理代行の料金相場とは?業務別の料金目安や依頼できる業務を解説
ポイント5:円滑なコミュニケーションとサポート体制があるか
アウトソーシングを円滑に進めるためには、委託先の担当者とのスムーズなコミュニケーションが不可欠です。
疑問点やトラブルが発生した際に、迅速かつ丁寧に対応してくれるサポート体制が整っているかを確認しましょう。
メールや電話だけでなく、ビジネスチャットなど、手軽に連絡が取れる手段が用意されていると安心です。
契約前の打ち合わせの段階で、担当者の対応の質やコミュニケーションの取りやすさを見極めることも重要です。
▷経理アウトソーシングで失敗する原因・事例|失敗しないための秘訣を紹介
経費精算は「代行」と「システム化」どちらが良い?自社に合った方法を選ぼう
経費精算の効率化を目指すとき、「代行(アウトソーシング)」と「システム化(ツールの導入)」という2つの選択肢が考えられます。
どちらが自社にとって最適なのかは、企業の規模や課題、目指すゴールによって異なります。
それぞれの特徴を理解し、自社に合った方法を選びましょう。
「経費精算代行(BPO)」がおすすめの企業
業務プロセスそのものを外部の専門家に任せる「代行」は、以下のような課題を持つ企業におすすめです。
- 経理担当者が慢性的な人手不足に陥っている
- 担当者がコア業務に集中できる環境を作りたい
- 経理の専門知識を持つ人材が社内にいない
- 内部統制を強化し、不正のリスクを低減したい
- 法改正への対応に不安がある
「人」が介在することで得られる専門性や、柔軟な対応力を重視する場合に、代行サービスは大きな力を発揮します。
「経費精算システム(SaaS)」がおすすめの企業
一方で、ITツールを導入して社内での業務効率化を図る「システム化」は、このような企業に適しています。
- 申請者や承認者の手間を削減したい
- ペーパーレス化を進め、テレワークに対応したい
- 経費精算のフローを社内で標準化したい
- 経費データを分析し、経営に活かしたい
- ある程度のITリテラシーを持つ従業員が多い
申請から精算までの一連の流れをデジタルで完結させ、社内全体の効率を底上げしたい場合に有効です。
ハイブリッド型も有効!オンラインアシスタントの活用
「代行」と「システム化」は、二者択一で考える必要はありません。
両方の良い部分を組み合わせた「ハイブリッド型」も非常に有効な手段です。
例えば、経費精算システムを導入して申請・承認プロセスを効率化しつつ、最終的なチェックや会計ソフトへの入力といった専門的な作業は、オンラインアシスタントのような代行サービスに委託するという方法です。
オンラインアシスタントは、必要な業務を必要な分だけ柔軟に依頼できるため、システムではカバーしきれない「あと少し」の部分を、低コストで補うことができます。
このハイブリッド型アプローチにより、コストを最適化しながら、最大限の業務効率化を実現することが可能になります。
まとめ:経費精算代行をうまく活用して、企業の成長を加速させよう
この記事では、経費精算代行のメリット・デメリットから費用相場、そして失敗しないための選び方まで、幅広く解説しました。
経費精算代行は、単に面倒な業務を外注するだけのサービスではありません。
ノンコア業務から解放された経理担当者が、より付加価値の高いコア業務に集中することで、企業全体の生産性を向上させ、持続的な成長を後押しする戦略的な一手となり得ます。
「何から始めたらいいかわからない」「自社に合ったサービスが知りたい」という方は、ぜひ「Chatwork 経理アシスタント」にご相談ください。
経費精算をはじめとするバックオフィス業務のプロフェッショナルが、お客様一人ひとりの課題に寄り添い、最適な解決策をご提案します。
採用、実務、労務管理までワンストップでサポートし、高品質な業務を低コストで実現します。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
あわせて読みたい