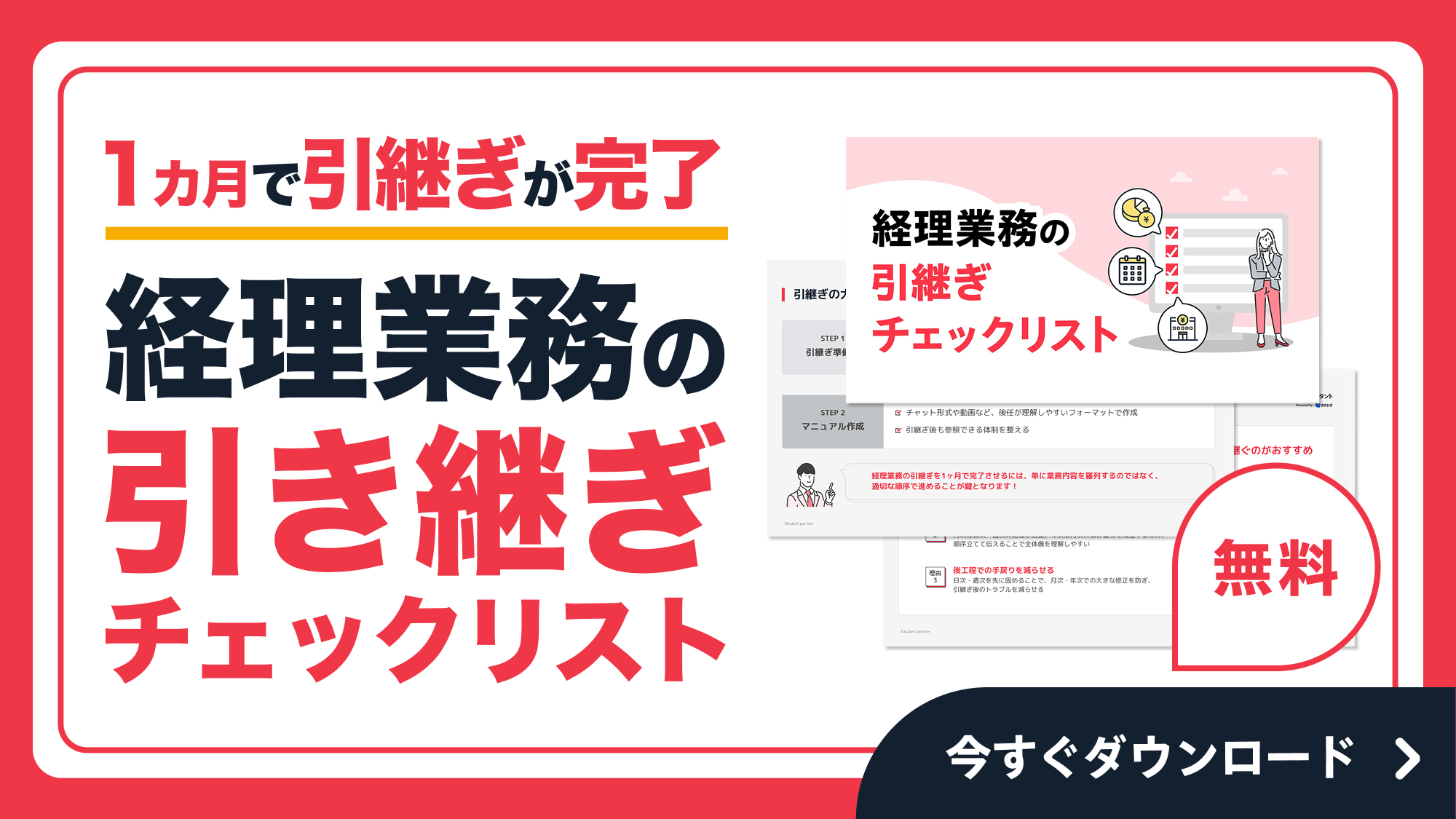経理が辞める会社は本当にヤバい?突然の退職が招くリスクと解決策

終わらない!

- リリースからわずか2年で
累計1000社以上が採用したサービス - 厳選された優秀なアシスタントが支援
- あらゆる経理業務を専門チームが代行
- 人手不足を解決し、安定した経理体制へ

目次
経理担当者の突然の退職は、会社の経営に深刻な影響を与えます。
「経理が辞める=やばい」と言われる理由を退職の裏側にある問題点から解説します。
経理業務の停止を防ぎ、会社を立て直すための具体的な対処法を紹介します。
経理担当者が辞めるのはなぜ?「やばい」と言われる理由
「経理の担当者が辞めてしまった」。その事実を知ったとき、会社は大きな危機に直面しているのかもしれません。
経理担当者の退職は、単なる人手不足ではなく、会社の根幹に関わる問題のサインである可能性が高いからです。
経理は、会社の「お金」の流れをすべて把握している部署です。
そのため、経営状況の悪化や社内の不正、業務の非効率性といった「会社の闇」を最も早く察知してしまいます。
もし、経理担当者が何の引き継ぎもなく突然辞めたとしたら、それは会社が抱える問題が深刻なレベルに達していることを示唆していると言えるでしょう。
この記事では、経理担当者の退職がなぜ「やばい」と言われるのかを深掘りし、退職が会社に与える具体的なリスク、そしてその危機を乗り越えるための解決策について詳しく解説します。
経理担当者が突然辞める3つの深刻な理由
経理担当者が退職を決意する理由は、他の職種とは少し異なる側面があります。
ここでは、特に深刻な退職理由を3つご紹介します。
1. 経理業務の属人化とブラックボックス化
中小企業では、経理業務を一人で担当しているケースが少なくありません。
給与計算、振込処理、経費精算、決算業務など、多岐にわたる業務がその担当者一人に集中し、他の社員は内容を把握していない「属人化」が起こりがちです。
この状況は、担当者が長期休暇を取れないだけでなく、業務のノウハウが共有されずにブラックボックス化する原因となります。
担当者へのプレッシャーや責任が過剰になり、退職を決意する大きな理由となります。
2. 会社の将来性への不安
経理担当者は、会社の財務諸表や資金繰りを日々チェックしているため、経営状況の良し悪しを最も正確に把握しています。
売上が伸び悩んでいる、資金繰りに余裕がないなど、会社の将来に不安を感じると、「このままこの会社にいても大丈夫だろうか?」と考えるようになります。
経営層が危機感を持っていなかったとしても、経理担当者はそのリスクを肌で感じ取っているのです。
3. 評価やキャリアパスが見えない環境
経理は会社の基盤を支える重要な仕事ですが、その貢献度が数字で表れにくいため、正当な評価を受けにくい側面があります。
「会社の縁の下の力持ち」として頑張っているにもかかわらず、その努力が報われず、給与や昇進に反映されないと感じると、モチベーションを失ってしまいます。
また、経理部門が一人しかいない場合、その先にあるキャリアパスが見えにくく、自身の成長を求めて転職を決意する人も多いです。
経理担当者の退職が引き起こす3つの致命的リスク
経理担当者が一人しかいない会社で、担当者が突然辞めてしまうと、事業の継続にすら影響するリスクが生じます。
1. 業務の停止と資金繰りの悪化
経理担当者がいなくなると、まず日々の業務がすべてストップします。
取引先への支払いや銀行への振込ができなくなり、会社のキャッシュフローが滞り、資金繰りが一気に悪化します。
最悪の場合、支払いが滞って取引先との信用問題に発展したり、事業停止に追い込まれたりする可能性もあります。
2. 法令違反とペナルティ
法人税の申告や社会保険の手続き、年末調整など、経理業務には多くの法律や期日が関わっています。
担当者が不在になると、これらの手続きが滞り、法律違反による罰金や追徴課税といったペナルティを科されるリスクが高まります。
会社の信用失墜にもつながるため、非常に危険な状態と言えるでしょう。
3. 不正や情報漏洩のリスク増大
経理担当者が不在になると、お金の流れを監視する目がなくなります。
これにより、経費の不正請求や横領など、内部不正のリスクが高まります。
また、会社の機密情報や個人情報が適切に管理されなくなり、情報漏洩のリスクも増大します。
経理が辞めても業務を回す!今すぐできる解決策
経理担当者の退職リスクを回避するには、事前の対策が不可欠です。
しかし、もしすでに経理担当者が辞めてしまったとしても、会社の業務を止めるわけにはいきません。
ここでは、経理の知識がない方でもすぐに取り組める、会社を守るための具体的な解決策をご紹介します。
1. 経理業務を「見える化」して全員で共有する
まずは、経理担当者が行っていた業務のすべてをリストアップし、それぞれの作業内容を可視化しましょう。
どの業務にどれくらいの時間がかかっているか、誰が何を担当していたかを明確にするだけで、業務の全体像を把握できます。
次に、それぞれの業務について、可能な限りマニュアルを作成してください。
これにより、たとえ経理の知識がなくても、誰でも同じように作業を進められるようになります。
業務の「見える化」は、引き継ぎをスムーズにするだけでなく、経理担当者への負担を軽減し、退職リスクそのものを下げる効果も期待できます。
▷経理マニュアルを作成するコツ|作り方やマニュアルの重要性を紹介
▷経理が属人化する要因はマニュアルがないから?作成方法と業務効率化のポイントを解説
2. ITツールを活用して業務を自動化する
手作業で行っていた経理業務を、ITツールで自動化することも有効な手段です。
例えば、経費精算システムやクラウド会計ソフトを導入すれば、領収書の入力や仕訳作業を自動化でき、手作業によるミスや時間が大幅に削減されます。
これにより、専門的な知識がない方でも最低限の経理業務をこなせるようになります。
また、オンライン上で情報が共有されるため、経理業務の属人化を防ぐことにもつながります。
3. 経理業務を専門家に任せるアウトソーシング
経理担当者の採用や育成には、時間もコストもかかります。
もし、今すぐに経理担当者を確保できないのであれば、経理業務を外部の専門家に委託するアウトソーシングを検討しましょう。
経理担当者の採用・育成コストが不要になる
担当者の急な退職リスクを回避できる
専門家による質の高い業務を安定して確保できる
担当者が不在でも、業務が滞ることがない
経理業務を専門家に任せることで、社内のリソースを本来の事業活動に集中させることができます。
また、経理のプロによるチェックが入るため、不正防止やコンプライアンス強化にもつながります。
もし、経理業務のアウトソーシングにご興味があれば、ぜひ無料相談をご活用ください。
あなたの会社に最適な解決策をご提案します。
▷【2025年最新】経理アウトソーシングのおすすめ14選比較|メリットや費用の目安
▷経理アウトソーシングで失敗する原因・事例|失敗しないための秘訣を紹介
▷経理アウトソーシングの大手会社を比較!選び方や大手に依頼するメリット
まとめ|経理の退職を危機から成長へのチャンスに
経理が辞めることは、会社にとって大きな危機です。
しかし、その危機は、属人化や非効率な業務体制といった、これまで目を背けてきた問題に気づく良い機会でもあります。
この機会を活かして、経理業務を効率化し、専門家に任せる体制を築くことができれば、会社はより強く、持続可能な組織へと生まれ変わることができるでしょう。
経理業務の属人化や急な退職リスクにお悩みなら、弊社の「Chatwork 経理アシスタント」がお役に立てるかもしれません。
このサービスは、日々の記帳から請求書作成、経費精算まで、経理のプロがあなたの会社の経理業務を代行します。
これにより、経理担当者の負担を減らし、もしもの事態にも安心して対応できる体制を構築できます。
まずは無料相談から、経理業務の課題についてお話ししてみませんか。
会社の成長を支えるための第一歩を、私たちがお手伝いします。