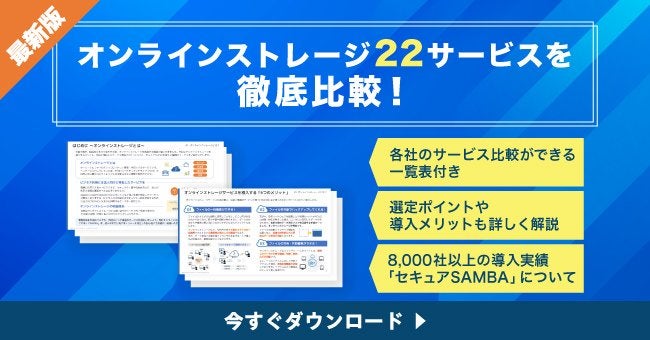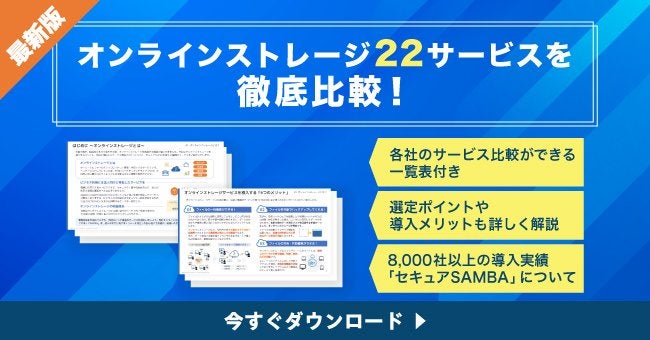オンラインストレージアプリおすすめ7選!無料版や失敗しない選び方

目次
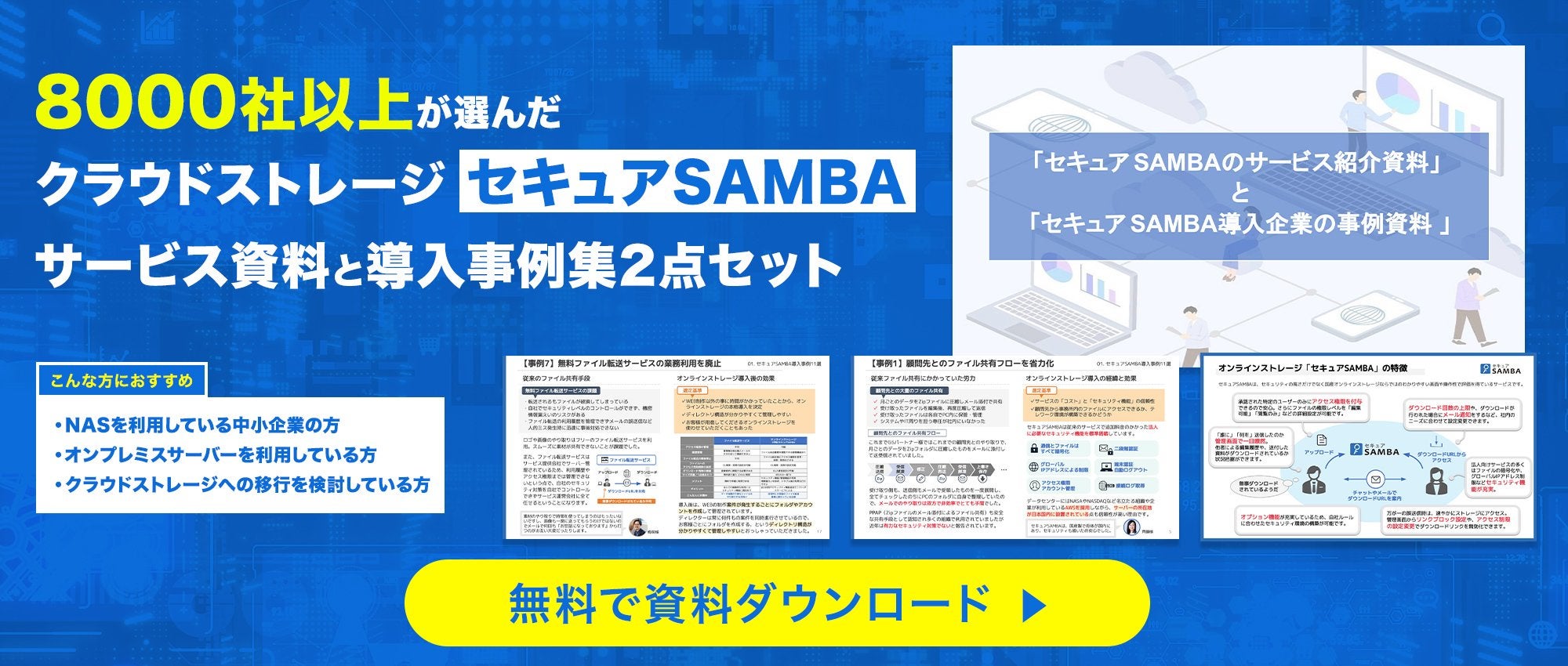
アプリ版のオンラインストレージとは?
ストレージとは「補助記憶装置」を指し、パソコン本体でいえば、内蔵されているHDDのほか、USBメモリ、外づけのHDDなどが該当します。
そのストレージをインターネット上に設定したサービスがオンラインストレージで、写真、動画、文書ファイルなどのデータ保管が可能です。さまざまな業者がサービスを提供し、一般的にパソコン端末を通じて利用されてきました。
アプリ版のオンラインストレージは、スマートフォンやタブレットに専用アプリをインストールすることで、パソコン端末と同じようにオンラインストレージが活用できるというものです。
インターネット環境さえあれば、パソコンがなくても手軽にストレージにアクセスすることができ、利用が広まっています。
オンラインストレージの特徴
オンラインストレージの特徴としては、以下の2つが挙げられます。
インターネット上でデータを保存できる
オンラインストレージは、インターネット上にデータを保存できるため、インターネット環境があれば時間や場所を問わずデータにアクセスできます。
これまでは、打ち合わせや商談の際、紙の資料を持ち歩いたり、データを保管したパソコンを持ち歩いたりすることが一般的でした。しかし、オンラインストレージを活用すれば、資料やパソコンを持ち歩くことなく必要なデータにアクセスが可能です。資料を準備する手間も省け、業務効率化にもつながります。
ファイルの共有が円滑にできる
オンラインストレージに保存されたファイルは、そのストレージにアクセスできるすべてのユーザーと共有できます。パソコンに保存しているデータのように、受け渡しの必要がありません。ファイルごとにアクセス権限を設定することも可能なため、関係者以外の閲覧は制限することもできます。また、オンラインストレージに保存されているファイルは、複数人での同時編集も可能です。離れた拠点にいるユーザーと、リアルタイムで情報を共有しながら編集できるため、作業にタイムラグが生じることもありません。メールなどで確認しながら編集を行う煩わしさも回避できます。
オンラインストレージの無料版・有料版の違い
オンラインストレージには、無料で利用できるものも多く提供されているため、個人、法人を問わず無料版を利用するユーザーが多いようです。
しかし、オンラインストレージの無料版と有料版には、主に以下3点の違いがあります。
- ストレージ容量
- 機能数
- セキュリティ性
そのため無料版は、容量が少ない個人データの一時保管などに向いているといえます。法人で無料版を利用すると、「容量が足りない」「使いたい機能がない」といった問題が生じるかもしれません。
もうひとつ、無料版と有料版の大きな違いとして、セキュリティ性が挙げられます。有料版には、暗号化、二段階認証、アクセス権限設定機能など、セキュリティ機能が豊富に備わっている点が、無料版との大きな違いです。
企業など、データの流出や不正利用などのリスクを避けたい場合には、有料版のオンラインストレージが安心といえます。
【無料あり】アプリ対応のオンラインストレージおすすめ
アプリ対応のオンラインストレージには、どのようなものがあるのでしょうか。無料で利用できるものも含めた、おすすめを紹介します。
1.セキュアSAMBA
セキュアSAMBAは、直感的な操作で簡単にファイルの共有、編集ができるオンラインストレージです。ファイルごとにアクセス権限を設定できるため、社外とのファイル共有も円滑に行えます。パソコン、スマートフォン、タブレットなど、さまざまな端末で利用できる点も魅力です。
| 提供元 | 株式会社kubellストレージ |
|---|---|
| 国 | 日本 |
| 課金タイプ | データ容量課金 |
| 容量・料金 | フリー 月額料金:¥0、容量:1GB スタンダード 月額料金:¥25,000、容量:300GB ビジネス 月額料金:¥35,000、容量:500GB エンタープライズ 月額料金:¥48,000、容量:1TB エンタープライズ 月額料金:¥88,000、容量:3TB エンタープライズ 月額料金:¥128,000、容量:5TB エンタープライズ 月額料金:¥178,000、容量:10TB エンタープライズ 月額料金:¥298,000、容量:30TB |
| 利用可能ID数 | 無料のみ2IDまで、有料版は無制限 |
| 導入実績 | 8000社以上 |
| 特徴 | 操作性・サポート体制・料金プラン・専門性に優れ、中小企業を中心に導入実績あり |
| URL | 公式サイト |
2.MEGA
MEGAは、ファイルの保管、チャット、ミーティングを1つのプラットフォームで完結できるオンラインストレージです。必要なユーザー数、ストレージ容量、転送容量に応じて料金が変動するため、高い費用対効果が期待できます。
デスクトップアプリやモバイルアプリだけでなく、Webから直接クラウドファイルにアクセスできる点も魅力です。
| 提供元 | MEGA Limited |
|---|---|
| 国 | ニュージーランド |
| 課金タイプ | ID課金 |
| 容量・料金 | 無料 月額料金:¥0、容量:10GB Pro I 月額料金:¥1,364、容量:2TB Pro II 月額料金:¥2,728、容量:8TB Pro III 月額料金:¥4,092、容量:16TB ビジネス 月額料金:要見積り、容量:要見積り |
| 利用可能ID数 | 1IDのみ。法人利用は要問合せ |
| 特徴 | 無料版でも10GBを利用可能だが、法人向けではさらに容量を拡張できる |
3.Google Drive
Google Driveは、手持ちのモバイルデバイス、タブレット、パソコンから、ファイルやフォルダの保存、共有、共同編集ができるオンラインストレージです。マルウェア、スパム、ランサムウェアに対する保護機能も標準搭載されています。
Google Driveは、Googleドキュメント、Googleスプレッドシート、Googleスライドなどと連携して利用することも可能なため、効率的かつリアルタイムなコンテンツ作成が実現するでしょう。
| 提供元 | グーグル合同会社 |
|---|---|
| 国 | アメリカ |
| 課金タイプ | ID課金・容量課金 |
| 容量・料金 | 無料 月額料金:¥0、容量:15GB ベーシック 月額料金:¥290、容量:100GB プレミアム 月額料金:¥1,450、容量:2TB Google AI Pro 月額料金:¥2,900、容量:2TB |
| 利用可能ID数 | 1IDから利用可能 |
| 特徴 | Googleアカウントを持っていればすぐに利用可能 |
4.iCloud Drive
iCloud Driveは、Appleが提供するオンラインストレージです。iPhone、iPad、iPod touch、Macのファインダーだけでなく、Windowsコンピュータからも利用できます。
個人利用が多いというイメージがあるかもしれませんが、Apple製品との互換性が高いため、社内の主な使用端末にApple製品が多い場合におすすめです。
| 提供元 | Apple Inc. |
|---|---|
| 国 | アメリカ |
| 課金タイプ | ID課金 |
| 容量・料金 | iCloud 月額料金:¥0、容量:5GB iCloud+ 月額¥150 月額料金:¥150、容量:50GB iCloud+ 月額¥450 月額料金:¥450、容量:200GB iCloud+ 月額¥1,500 月額料金:¥1,500、容量:2TB iCloud+ 月額¥4,500 月額料金:¥4,500、容量:6TB iCloud+ 月額¥9,000 月額料金:¥9,000、容量:12TB |
| 利用可能ID数 | 1IDのみ |
| 特徴 | Apple製品との連携に優れ、写真や動画の自動保存が可能。Appleユーザーに最適 |
5.One Drive
One Driveは、どのデバイスでもどこからでも、ストレージに保存したファイル、フォルダ、写真にアクセスできるオンラインストレージです。1つのドキュメントを複数人かつリアルタイムで共同作業できます。
マイクロソフトから提供されているため、Word、Excel、PowerPointなどOfficeアプリとの互換性が高い点も魅力です。
| 提供元 | 日本マイクロソフト株式会社 |
|---|---|
| 国 | アメリカ |
| 課金タイプ | ID課金 |
| 容量・料金 | OneDrive for Business (Plan 1) 月額料金:¥749、容量:1TB Microsoft 365 Business Basic 月額料金:¥899、容量:1TB Microsoft 365 Business Standard 月額料金:¥1,874、容量:1TB |
| 利用可能ID数 | 1~300ID |
| 特徴 | Microsoft office、TeamsやSharepointから共有ファイルを追加可能 |
6.Box
Boxは、各種コンテンツを1つのプラットフォームに集約できるオンラインストレージです。他システムからのコンテンツの移行も可能で、各コンテンツに付随するアクセス権限やバージョン履歴などの情報も継承してくれます。
| 提供元 | 株式会社Box Japan |
|---|---|
| 国 | アメリカ |
| 課金タイプ | ID課金 |
| 容量・料金 | Individual 月額料金:¥0、容量:10GB Personal Pro 月額料金:¥1,320、容量:100GB Business Starter 月額料金:¥605、容量:100GB Business 月額料金:¥1,980、容量:無制限 Business Plus 月額料金:¥3,300、容量:無制限 Enterprise 月額料金:¥4,620、容量:無制限 Enterprise Plus 月額料金:¥6,600、容量:無制限 |
| 利用可能ID数 | 法人向けプランは最低3ID以上 |
| 特徴 | アメリカのbox社が提供。容量・人数が無制限、セキュリティの高さが評判 |
7.pCloud
| 提供元 | pCloud International AG |
|---|---|
| 国 | スイス |
| 課金タイプ | ID課金 |
| 容量・料金 | 無料 月額料金:¥0、容量:10GB Premium 500 GB 月額料金:4.99USD、容量:500GB Premium Plus 2 TB 月額料金:9.99USD、容量:2TB Ultra 10 TB 月額料金:19.99USD、容量:10TB |
| 利用可能ID数 | 1IDのみ |
| 特徴 | 買い切り型プランを提供し、長期保存したい個人ユーザーに人気。GDPRにも対応。 |
オンラインストレージアプリの失敗しない選び方
無料のオンラインストレージアプリもありますが、できれば選択での失敗は避けたいところです。その選び方を確認しておきましょう。
データ容量はどのくらいか
オンラインストレージアプリによって、保存できるデータ容量が異なります。まず、自身が保存したいデータ容量に対して、アプリの保存容量が十分かどうかを見極めましょう。
ただし、データは将来的に増えていく可能性があります。保存したいデータ容量が増えたとき、追加できる保存容量はどの程度なのかも確認しておくとよいでしょう。
例えば、1GBで保存できる写真データは、サイズにもよりますが、スマートフォン撮影のもので300~500枚程度といわれています。法人がパソコン内のファイルをすべて保存する場合は、100GB程度は必要になるでしょう。
そういったことも念頭に、無料利用の保存容量だけでなく、データ容量が増えた際に対応できるものを選ぶことがポイントです。
導入・運用にかかる費用はどのくらいか
有料版のオンラインストレージを利用する際は、月額や年額で利用料金が発生するため、予算面で継続的に運用できるものを選ぶ必要があります。
利用料金は、保存容量やユーザー数に応じて変動し、データ容量やユーザー数が増えるほど、高くなるのが一般的です。だからといって、使いきれないほどの保存容量があるプランを導入しても、無駄になってしまうでしょう。
基本的にオンラインストレージは、保存容量が足りなくなったタイミングで、プランを変更したり保存容量を追加したりすることが可能です。予算を見積もり、導入、運用にかかる費用が見合うものを選びましょう。
セキュリティ・サポート体制は万全か
オンラインストレージでは、インターネット上にデータを保存するため、少なからず情報漏えいやデータ不正利用などのリスクをともないます。そのため、オンラインストレージを導入する際は、セキュリティ性の高いものを選ぶことが大切です。
セキュリティ機能の例としては、「送受信時にデータが暗号化される」「アクセスに二段階認証の設定が可能」「ファイルごとにアクセス権限を設定できる」などが挙げられます。
また、外部の事業者によって提供されているオンラインストレージに不具合やエラーが生じた場合、利用者側で対応することは困難です。緊急時に備え、いつでも事業者に問い合わせることができる、迅速に対応してもらえるなど、サポート体制の充実度も確認するとよいでしょう。
操作性・利便性は高いか
オンラインストレージアプリによって、搭載されている機能や操作性、利便性が異なります。機能が多ければ利用の幅も広がりますが、操作が複雑になった場合、アプリの利用が定着しないなどの問題につながりかねません。
また、アップロードやファイル操作に時間がかかると、利用者にとってストレスになることもあるでしょう。
アプリによっては、無料トライアルや無料プランが提供されています。積極的に活用し、本当に必要な機能を見極めたうえで、使い勝手のよいアプリを選ぶことが大切です。
特徴を理解しオンラインストレージを効果的に運用しよう
パソコンを通じて利用されることの多かったオンラインストレージですが、昨今はアプリ版も多く提供され、スマートフォンやタブレットでも気軽に利用できるようになりました。
無料版と有料版がありますが、有料版はストレージ容量や機能も多く、セキュリティ性に優れていることもあり、法人での利用におすすめです。
ただし、オンラインストレージはインターネット上に設定されるため、情報漏えいなどのリスクをゼロにすることはできません。提供業者が講じているセキュリティ対策をしっかりと確認したうえで、自社に最適なアプリを選定・運用していきましょう。