「人手不足倒産」はなぜ起こる?原因や前兆、多発する業種、回避できた事例や解決策まで一挙に解説
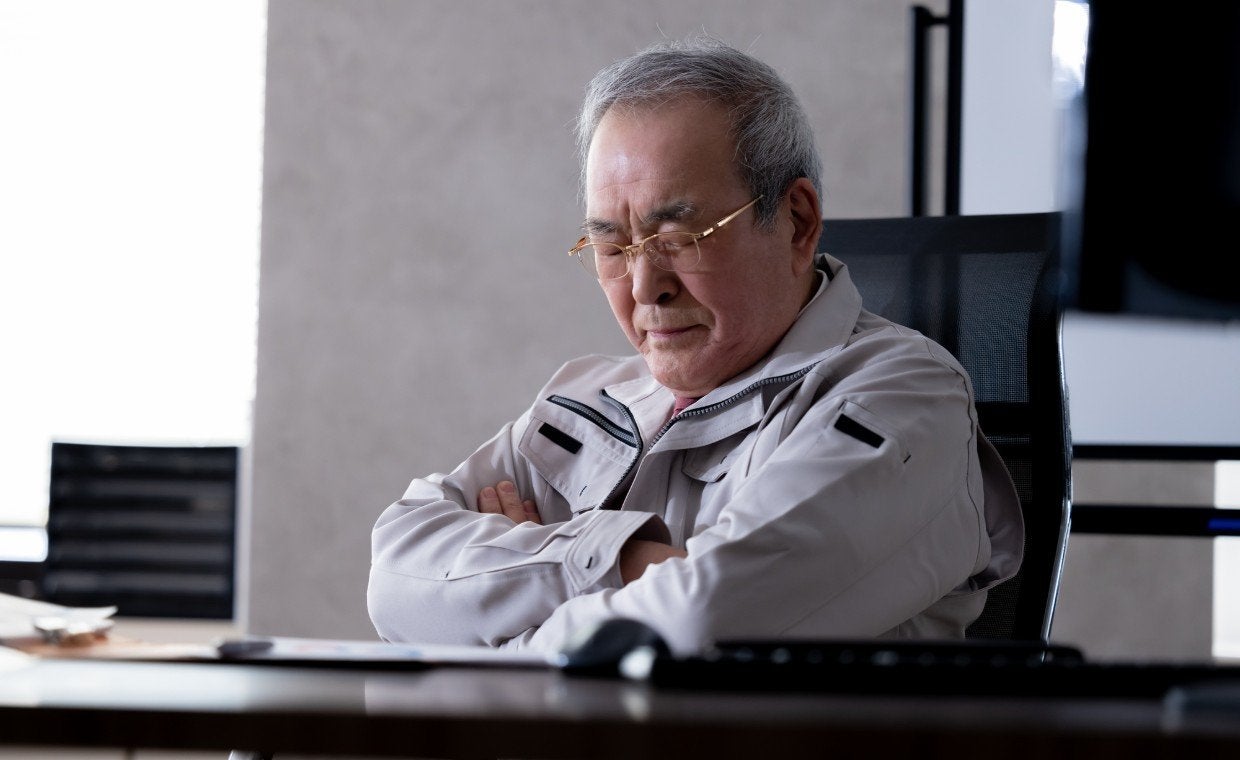
目次
近年、人手不足を理由として企業が倒産する「人手不足倒産」が深刻な問題となっています。
本記事では、人手不足倒産の原因や件数の推移、多く見られる業種や企業の特徴を深く掘り下げます。
あわせて、人手不足倒産を回避できた事例や、具体的な解決策も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
「人手不足倒産」とは?
「人手不足倒産」とは、企業の従業員が不足することによって事業の継続が困難になり、倒産に至ることを指します。
人手不足倒産の大きな特徴は、必ずしも業績が悪化しているわけではないという点です。
むしろ、受注が増えて業績が好調であるにもかかわらず、人手が足りないために、その受注をこなしきれずに倒産してしまう「黒字倒産」の一種として現れることが少なくありません。
具体的には、以下のような要因が複合的に絡み合って発生します。
後継者難:経営者が高齢化し、事業を引き継ぐ後継者が見つからないために廃業・倒産するケース。
従業員退職:中核となる従業員の退職が相次ぎ、事業の運営に必要なスキルやノウハウが失われ、事業が立ち行かなくなるケース。
求人難:事業拡大に必要な人員を募集しても、応募が集まらず、受注に対応できないケース。
人手不足倒産は、単に人がいないという問題だけでなく、企業の存続そのものを揺るがす深刻な経営課題として、特に中小企業を中心に大きな脅威となっています。
人手不足倒産の件数推移
人手不足倒産の件数は、近年、増加傾向にあり、その深刻さは各種調査からも明らかになっています。
株式会社帝国データバンクが令和7年(2025年)10月6日に発表した「2025年度上半期(4-9月)の『人手不足倒産』動向調査」によると、2025年度上半期の人手不足倒産の件数は、過去最多を記録しました。
この調査では、人手不足に起因する倒産を「後継者難」「従業員退職」「求人難」の3つの要因に分類しています。
特に、賃上げの動きが活発化する中で、十分な賃上げ原資を確保できない企業から人材が流出し、事業継続が困難になる「賃上げ格差」を背景とした倒産が目立っています。
また、建設業や物流業における「2024年問題」の影響も継続しており、これらの業種での倒産件数を押し上げる一因となっています。
令和の時代に入り、日本の労働市場が構造的な変化を迎える中で、人手不足という問題は、企業の経営体力を徐々に奪い、倒産という形で表面化しています。
人手不足倒産件数の推移は、人手不足がもはや一時的な問題ではなく、すべての企業が向き合うべき恒常的なリスクであることを示していると言えるでしょう。
人手不足倒産が起こる理由や前兆
人手不足倒産は、ある日突然起こるわけではありません。
その背景には構造的な理由があり、倒産に至るまでにはいくつかの前兆(サイン)が現れます。
なぜ人手不足倒産が起こるのか、その理由と前兆を理解することが、対策の第一歩です。
人手不足倒産が起こる理由
人手不足倒産が起こる主な理由として、以下のようなものが挙げられます。
少子高齢化による労働人口の減少:日本の生産年齢人口は減少の一途をたどっており、労働市場全体で人材の獲得競争が激化しています。
これが、人手不足の根本的な理由です。
労働条件のミスマッチ:求職者は、給与だけでなく、休日数や労働時間、働き方の柔軟性といった労働条件を重視する傾向が強まっています。
低い賃金や厳しい労働環境のままでは、求職者から選ばれず、人材が集まりません。
需要と供給のギャップ:特定の業種や職種(建設、物流、介護など)では、需要の増加に対して、働き手の供給が全く追いついていません。
この構造的なギャップが、深刻な人手不足を引き起こしています。
ベテラン従業員の退職と技術承継の失敗:長年会社を支えてきたベテラン従業員が定年退職を迎える一方で、その技術やノウハウを若手に引き継ぐ「技術承継」がうまくいっていないケースです。
事業の核となる技術が失われ、品質の維持や生産が困難になります。
人手不足倒産の前兆
自社に以下のような前兆が見られたら、注意が必要です。
離職率の上昇・定着率の低下:特に、将来を期待していた若手や中堅社員の離職が続くのは危険なサインです。
労働環境やキャリアパスに何らかの問題がある可能性があります。
求人への応募が全くない:求人媒体に広告を出しても、応募がゼロ、あるいは極端に少ない状態が続く場合、自社の採用条件や魅力が市場のニーズと合っていない可能性があります。
既存従業員の残業時間の恒常的な増加:人手が足りない分を、既存の従業員が残業でカバーしている状態です。
従業員の疲弊を招き、さらなる離職につながる悪循環に陥ります。
サービスの質の低下や納期の遅延:人手不足から、顧客への対応が雑になったり、製品の納期が守れなくなったりするケースです。
顧客満足度の低下は、売上の減少に直結します。
従業員からの不満の声の増加:「給料が上がらない」「休みが取れない」「将来が不安だ」といった、従業員からの不満やネガティブな発言が増えるのは、組織の活力が失われている証拠です。
人手不足倒産の危険性が高い企業の特徴
人手不足倒産はどの企業にも起こり得ることですが、特に以下のような特徴を持つ企業はリスクが高いと言えます。
1. 労働集約型のビジネスモデルである
事業の運営を、機械やシステムではなく、人間の労働力に大きく依存しているビジネスモデルの企業です。
建設業、運送業、介護サービス、飲食・宿泊業などがこのタイプに該当します。
1人でも従業員が欠けると、事業の運営に直接的な影響が出やすいという一面を持っています。
2. 賃金水準が業界平均より低い
売り手市場が続く現在、賃金は企業を選ぶ上で重要な要素です。
業界の平均的な水準や、地域の同業他社と比較して賃金が低い場合、人材はより条件の良い企業へと流出してしまいます。
価格競争の激化などから、人件費を抑制せざるを得ない中小企業が人手不足倒産に直面しやすいのは、賃金の問題が大きな理由と言えるでしょう。
3. 労働環境が厳しい
長時間労働や休日出勤が常態化している、有給休暇が取得しにくい、ハラスメントが横行しているなど、従業員にとって働きやすいとは言えない環境の企業も高リスクです。
このような企業は、従業員の心身の健康を損ないやすく、離職率も高くなる傾向があるため、人手不足倒産を招く危険性があります。
4. DX化・IT化が遅れている
DX化・IT化が遅れている企業では、手作業や紙ベースのアナログな業務プロセスが多く残っています。
本来であればITツールで自動化できるはずの業務に多くの人手と時間を費やしているため、生産性が低い傾向にあります。
このような企業は、少ない人数で効率的に業務を回すことができなかったり、十分な利益を生み出せなかったりするため、人手不足の影響を受けやすくなります。
5. 経営陣の後継者がいない
経営者が高齢であるにもかかわらず、事業を継いでくれる親族や従業員がいない企業にも人手不足倒産の可能性があります。
経営者自身の引退と共に会社を畳まざるを得ない「後継者難」による倒産は、人手不足倒産の大きな割合を占めており、特に地域経済を支える中小企業において深刻な問題となっています。
人手不足倒産が多い業種
帝国データバンクの調査によると、人手不足倒産は特定の業種に集中する傾向が見られます。
ここでは、特に倒産件数が多い業種とその背景を解説します。
1. 建設業
人手不足倒産が最も多い業種です。
職人の高齢化と若者の入職者減が深刻で、技術者の確保が非常に困難になっています。
2024年4月から時間外労働の上限規制が適用された「2024年問題」も、人件費の高騰や工期の長期化を招き、経営を圧迫する要因となっています。
2. 物流業(道路貨物運送業)
建設業と同様に、「2024年問題」の影響を大きく受けている業種です。
ドライバーの長時間労働に支えられてきたビジネスモデルが、法規制によって成り立たなくなりつつあります。
ドライバーの高齢化も進んでおり、若手人材の確保が急務となっています。
3. サービス業
特に、介護サービスや飲食業、宿泊業といった、対人サービスを中心とする業種で人手不足が深刻です。
これらの業種は比較的賃金水準が低く、肉体的・精神的な負担も大きいことから、人材の確保・定着が難しいという課題を抱えています。
4. 製造業
熟練技術者の高齢化や、技術の承継が大きな課題となっている業種です。
特に、地方の中小製造業では、若者人材が都市部へ流出し、後継者が見つからないという厳しい問題に直面しています。
5. 小売業
小売業では、店舗で働く販売員やバックヤードで作業するスタッフの確保が難しくなっています。
非正規雇用の割合が高い業種ですが、最低賃金の上昇などによる人件費の増加が経営を圧迫していることも倒産を招く一因です。
人手不足倒産を回避するには?
人手不足倒産を回避するためには、企業経営の根本的な部分に目を向けた多角的なアプローチが必要です。
ここでは、人手不足倒産を防ぐために有効な対策を紹介します。
1. 採用戦略の見直し
従来の採用手法だけに頼るのではなく、採用戦略そのものを見直すことが重要です。
採用ターゲットの拡大:若手や経験者だけでなく、主婦(主夫)層、シニア層、外国人材など、これまでアプローチしてこなかった層にも目を向け、多様な人材が活躍できる環境を整えます。
採用手法の多様化:求人広告だけでなく、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用(社員紹介)、SNSを活用した採用広報など、複数の手法を組み合わせ、積極的に情報発信を行います。
働き方の多様化:フルタイム正社員だけでなく、時短勤務、パート・アルバイト、業務委託など、求職者のニーズに合わせた多様な雇用形態を用意します。
2. 労働環境・待遇の改善
人材に「選ばれる」企業になるためには、魅力的な労働環境と公正な待遇が不可欠です。
賃金の引き上げ:周辺地域の同業他社の賃金相場を調査し、競争力のある給与水準を設定します。
生産性向上と連動した賃上げ計画を立てることが重要です。
働きやすい環境づくり:長時間労働の是正、有給休暇の取得促進、ハラスメントのない職場風土の醸成、福利厚生の充実など、従業員が心身ともに健康で、長く働き続けたいと思える環境を整備します。
3. DX推進による生産性向上
デジタル技術を活用して、少ない人数でも効率的に業務を回せる体制を構築します。
業務の自動化:会計ソフトや勤怠管理システム、RPA(Robotic Process Automation)などを導入し、データ入力や書類作成といった定型業務を自動化します。
情報共有の効率化:ビジネスチャットツールやクラウドストレージを導入し、社内の情報共有を円滑にし、無駄な会議や報告作業を削減します。
4. アウトソーシングの活用
経理や総務、人事といった、企業の利益に直接結びつかないノンコア業務を、専門の外部業者に委託(アウトソーシング)します。
社内の従業員は、自社の強みであるコア業務に集中することができます。
アウトソーシングは、人手不足に対する即効性のある解決策です。
5. 従業員の定着率向上とスキルアップ支援
新たな人材を採用することと同じくらい、今いる従業員に長く活躍してもらうことが重要です。
キャリアパスの提示:従業員が将来のキャリアをイメージできるよう、明確なキャリアパスや評価制度を設けます。
教育・研修制度の充実:資格取得支援や研修機会の提供を通じて、従業員のスキルアップ(リスキリング)を支援し、モチベーションを高めます。
人手不足倒産を未然に防いだ事例
実際に、早期の対策によって人手不足の危機を乗りこえ、成長を続ける企業も存在します。
ここでは、2つの企業の事例をご紹介します。
事例1:ITツール導入と多能工化で生産性を向上させた建設会社
地方のある建設会社は、職人の高齢化と若手人材の不足に悩んでいました。
人材の不足によって残業が常態化し、離職者が増えてさらに人手不足が加速するという悪循環に陥りかけていました。
この課題に対して同社は、施工管理アプリや勤怠管理システムといったITツールを積極的に導入します。
図面の共有や業務報告をデジタル化し、現場と事務所間の移動や手作業による書類作成の時間を大幅に削減しました。
さらに、1人の職人が複数の工程を担当できる「多能工化」を推進する研修制度も導入した結果、従業員1人あたりの生産性が向上し、少ない人数でも多くの現場を回せるようになりました。
残業時間も大幅に削減され、働きやすい環境が整ったことで、若手人材の応募も増え始めました。
事例2:ノンコア業務のアウトソーシングで離職率を改善した介護施設
ある介護施設では、介護スタッフが本来の介護業務に加えて日々の記録作成やシフト管理、備品発注といった事務作業も行っていました。
複合的な業務負担によって介護スタッフの疲弊と離職が深刻化したことから、介護記録の入力やシフト管理、事務用品の発注といったノンコア業務をオンラインアシスタントサービスにアウトソーシングすることを決断しました。
その結果、介護スタッフは「利用者と向き合う」という本来の業務に専念できるようになっただけでなく、業務負担が軽減されたことで従業員の満足度が向上し、離職率が大幅に改善しました。
また、介護サービスの質も向上し、利用者からの評判も高まるという良い循環が生まれました。
人手不足の早期解決には『Chatwork アシスタント』がおすすめ!
前述した解消法の中でも、「即効性」と「コスト効率」を重視する中小企業やスタートアップにおすすめしたいのが、アウトソーシングの活用です。
数あるサービスの中でも、特におすすめなのは『Chatwork アシスタント』です。
『Chatwork アシスタント』は、国内利用者数No.1のビジネスチャット「Chatwork」が提供する、オンライン完結型のアシスタントサービスです。
経理、人事、総務、秘書といった、企業のノンコア業務を、厳しい採用試験を突破した優秀なアシスタントがチームでサポートします。
新たに人材を採用する場合に比べて、採用や教育にかかるコストと手間を一切かけることなく、月額制のリーズナブルな料金で、質の高いサポートをスピーディーに受けることができます。
人手不足という課題に対し、即時性のある解決方法のひとつと言えます。
Chatwork アシスタントを導入するメリット
『Chatwork アシスタント』の導入によって、以下のようなメリットを得ることができます。
1. 採用・教育コストゼロで、即戦力を確保
実務経験者を採用するには、多くの時間とコストがかかります。
また、採用後も自社のルールを教える教育期間が必要です。
『Chatwork アシスタント』であれば、契約後すぐに、さまざまな実務経験を積んだプロのアシスタントチームを活用できます。
採用や教育の手間とコストをかけることなく、質の高いバックオフィス機能をスピーディーに立ち上げることが可能です。
急な退職者の発生など、緊急性の高い人材不足にも迅速に対応できます。
2. 業務の繁閑に合わせて、柔軟にリソースを調整
企業の業務には、繁忙期と閑散期があります。
『Chatwork アシスタント』は、月々の実働時間に応じた料金プランのため、企業の状況に合わせて、依頼する業務量や内容を柔軟に調整できます。
「繁忙期だけ、集中的にサポートしてほしい」「閑散期は最低限の業務だけお願いしたい」などのように、繁閑の波に合わせた効率的なリソース活用が可能です。
3. Chatworkによる円滑な連携
アシスタントとの業務連絡やデータ共有は、すべてビジネスチャット「Chatwork」で完結します。
メールのように形式的な文章を作成する手間がなく、タスク管理機能で依頼内容の進捗も可視化できます。
このスムーズな連携が、業務のスピードを向上させ、コミュニケーションのストレスを軽減します。
まとめ
本記事では、人手不足倒産の原因や企業経営に与える影響、多く見られる業種や企業の特徴、具体的な回避策などを解説しました。
人手不足倒産は、日本の多くの企業にとって現実的な経営リスクであり、業務の停滞・サービスの質の低下・企業の成長阻害などを引き起こす大きな要因となります。
そのため、多角的な視点から早期に対策を講じることが重要です。
自社が抱える人材問題を明確にし、今回紹介したような方法で改善を図っていきましょう。







