労働条件通知書とは?雇用契約書との違いや記載事項、明示ルールを解説
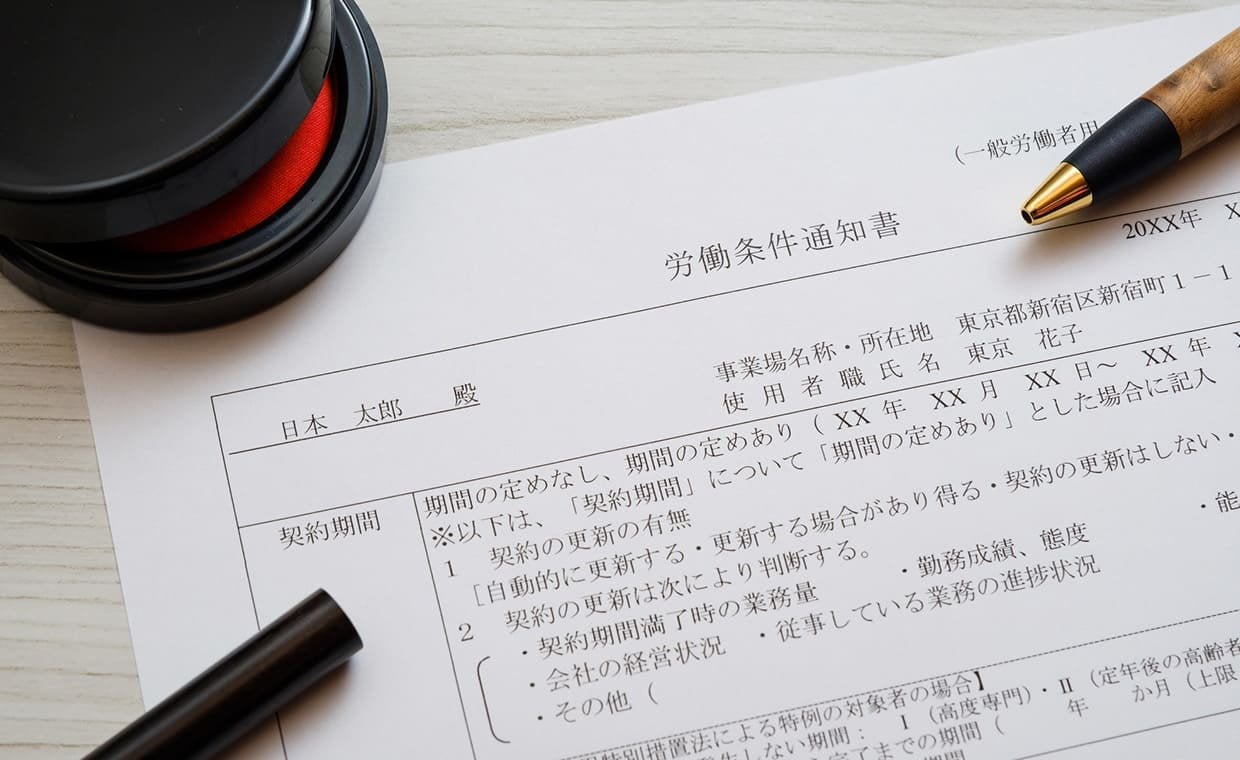
目次
労働条件通知書は、企業が労働者を雇用する際に交付が義務付けられている書類です。
労働条件通知書に明示する事項は法律で義務付けられており、その事項は必ず労働者に明示しなければなりません。
現在ではメール等による電子交付も認められ、業務の効率化も進んでいますが、明示事項や交付のタイミングなどは法令に沿った運用が求められます。
本記事では、労働条件通知書と雇用契約書との違いや記載事項、明示ルールなどを詳しく解説します。
労働条件通知書とは
労働条件通知書は、労働基準法第15条に基づき、企業が従業員に対して労働条件を明示するために交付する書類です。
労働条件を明示することで、労使間の認識の違いや後々の労働条件に関するトラブルを未然に防ぐことを目的としています。
労働基準法第15条には、以下のように記載されています。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
なお、労働条件通知書は書面の交付のほか、従業員の希望があれば電子交付も可能です。 [注1]
労働条件通知書の対象者・交付タイミング
労働条件通知書は、対象者と交付のタイミングに注意する必要があります。
対象者と交付のタイミングについて詳しく確認していきましょう。
労働条件通知書の対象者
労働条件通知書の交付は、企業と雇用契約を締結するすべての労働者が対象となります。
そのため、正社員だけでなく、契約社員やパートタイム・アルバイトも交付の対象です。
ただし、雇用契約書に労働条件通知書で明示が義務付けられている事項が記載されている場合は、雇用契約書の締結・交付により労働条件を通知したとみなされます。
労働条件通知書の交付タイミング
労働条件通知書を交付するタイミングは、労働基準法第15条では「労働契約締結時」と定められています。
労働契約締結時とは、原則として以下のタイミングを指します。
| 即時入社 | 入社時 |
|---|---|
| 内定期間がある場合 | 内定時 |
採用内定後すぐに入社する場合は、入社時に交付されるのが一般的です。
一方、内定から採用まで期間がある場合は、内定の時点で労働契約が成立すると考え、原則として内定通知書とともに労働条件通知書の交付が必要です。
ただし、内定の際に具体的な就業場所や従事すべき業務などを特定できない場合には、想定される内容を示すこととしても差し支えありません。
具体的に特定できなかった事項については、できる限り早期に決定するよう努め、決定次第改めて明示することとされています。[注2]
労働条件通知書と雇用契約書の違い
労働条件通知書と雇用契約書は、どちらも労働者を雇用する際に作成する書類ですが、役割が異なります。
労働条件通知書は法的に交付が義務付けられている書類であり、雇用の基本条件を明示することを目的としています。
一方で、雇用契約書は契約内容を証明するための書面で、双方が合意した条件が記載されます。
雇用契約書は法的に作成は義務付けられていませんが、契約の締結を証明する書類として作成するのが一般的です。
| 目的・役割 | 義務 | |
|---|---|---|
| 労働条件通知書 | 義務付けられている | |
| 雇用契約書 | 義務付けられていない |
言い換えれば、労働条件通知書は「通知」目的で交付されるものであり、雇用契約書は「合意」を証明するものという違いがあります。
なお前述したとおり、雇用契約書に労働条件通知書に明示しなければならない労働条件が記載されている場合は、雇用契約書で労働条件通知書を兼ねることができます。
労働条件通知書を交付する理由
なぜ労働条件通知書の交付は義務付けられているのでしょうか。
労働条件通知書を交付する理由・目的を解説します。
雇用後のトラブルを防ぐため
労働条件通知書を交付することで、入社後に発生しがちなトラブルを未然に防ぐことができます。
たとえば、労働時間や賃金の認識の違い、休日や福利厚生に関する誤解などです。
具体的な条件を書面で確認することで、企業側と労働側との間に生じる齟齬を減らす効果があります。
また、トラブルが発生した場合にも、交付済みの書面を解決の証拠とすることができます。
安心して入社してもらうため
明確な労働条件を示すことは、入社希望者に対する信頼感を高める効果があります。
雇用条件が具体的に提示されていると、労働者は自分がどのような条件のもとで働くのかを事前に把握できるため、安心して入社ができます。
また、労働条件通知書の交付は、新入社員や転職者に企業側の誠実な姿勢を示す手段でもあります。
労働条件通知書に記載する内容
労働条件通知書に記載する内容は、必ず明示しなければならない「絶対的明示事項」と、定めがある場合に明示が求められる「相対的明示事項」に分けられます。
明示すべき事項の記載がない場合は労働基準法違反となるため、注意しましょう。[注3]
絶対的明示事項
絶対的明示事項は書面などでの明示が義務付けられている事項です。
明示する事項は以下のとおりです。
| 労働条件 | 詳細 |
|---|---|
| 労働契約の期間 | 期間の定めの有無・契約期間 |
| 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準 | 更新基準・更新上限の有無・無期限転換申込機会・無期転換と労働条件 |
| 就業する場所 | 採用直後の場所だけではなく、将来の配置・出向等も含めて明示 |
| 業務の内容 | 採用直後の業務だけではなく、将来の配置・出向等も含めて明示 |
| 始業・終業時刻 | 所定労働時間を明示 変形労働時間やシフト制、フレックスタイム制の適用がある場合は適用される時間を明示 |
| 時間外労働の有無 | 所定労働時間を超える時間や休日労働の有無 |
| 休憩時間 | 所定の休憩時間 |
| 休日・休暇 | 休日の日数や曜日、有給休暇日数、夏季休暇、年末年始休暇など |
| 賃金の決定・計算・支払い方法 | 給与や諸手当の金額、締め日、支払日、支払い方法など |
| 退職に関する規定(解雇の事由含む) | 定年や退職の手続きなど |
| 昇給 | 昇給の有無と時期、金額の決定方法など |
なお、「昇給」については必ず明示しなければなりませんが、書面での交付まで求められていません。
しかし、「昇給」についても書面での明示が望ましいです。
有期・パートタイム労働者の場合は、追加で以下の事項の明示が求められます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 昇給 | 昇給の有無 |
| 退職手当 | 退職手当の有無 |
| 賞与 | 賞与の有無 |
| 相談窓口 | パートタイム労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 |
相対的明示事項
相対的明示事項は、書面での明示は義務付けられておらず、設けている場合は口頭や就業規則で明示が義務付けられている事項です。
ただし、トラブル防止のためにもできるだけ書面での明示が求められています。
相対的明示事項は以下の事項です。
| 労働条件 | 詳細 |
|---|---|
| 退職手当に関する事項 | 一般的には退職手当がないときは「なし」と書面で明示される |
| 賞与に関する事項・最低賃金額に関する事項 | 一般的には賞与がないときは「なし」と書面で明示したされる |
| 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 | 該当する場合のみ明示 |
| 安全及び衛生に関する事項 | 安全衛生管理の体制や災害が発生した場合の措置など |
| 職業訓練に関する事項 | 社員教育なども含む |
| 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 | 福利厚生制度なども含む |
| 表彰及び制裁に関する事項 | 表彰・懲戒の種類など |
| 休職に関する事項 | 制度がある場合のみ明示 |
2024年改正の労働条件の明示ルール
2024年4月の労働基準法改正により、労働条件通知書において新たに以下の事項を明示することが義務付けられました。
- 就業場所・業務の変更の範囲
- 更新上限の有無と内容
- 無期転換申込機会
- 無期転換後の労働条件
改正の内容を詳しく確認していきましょう。[注4]
就業場所・業務の変更の範囲
就業場所・業務の変更範囲は、雇用形態を問わずすべての労働者が対象になる明示事項です。
改正により、雇用契約の締結ごとに、雇入れ直後の就業場所・業務内容の記載に加え、「変更の範囲」についても明示が必要になりました。
「変更の範囲」とは、将来的な配置転換などによって変わり得る業務や就業場所の範囲のことです。
たとえば、就業場所は「雇入れ直後:東京支社」「変更可能性:会社の定める支店」などのように変更範囲を明示しなければなりません。
また、テレワークを認めている場合は、「自宅または会社が指定する場所」など、想定される就業場所を明示する必要があります。
加えて業務の変更範囲についても、雇入れ直後と変更の範囲の明示が必要です。
ただし、明確でない場合は「すべての業務への配置転換あり」と記載することも可能です。
更新上限の有無と内容
有期労働契約の労働者に対しては、締結と契約更新の時期ごとに更新の上限の有無とその内容を明らかにする必要があります。
たとえば、「契約期間は通算4年を上限とする」「契約の更新回数は3回まで」 などです。
なお、現在雇用している労働者に対して更新の上限を新たに設ける場合、または上限の期間を短縮する場合は、その労働者に対して理由をあらかじめ説明しなければなりません。
無期転換申込機会
通算5年を超えて労働契約が更新される労働者には、更新のタイミングごとに無期転換を申し込むことが可能な旨(無期転換申込機会)を明示する必要があります。
また、はじめて無期転換申込権が発生する労働契約が満了した後も労働契約を更新する場合は、更新の都度、無期転換申込機会について明示が必要になります。
無期転換後の労働条件
無期転換ができる有期契約労働者には、更新のタイミングごとに無期転換後の労働条件を明示する必要があります。
明示方法は、項目ごとに明示する、もしくは無期転換後の労働条件の変更内容を別紙で明示するなどの方法でも問題ありません。
また、無期転換申込機会と同様、はじめて無期転換申込の権利が発生する有期労働契約が満了し、その後も契約を更新する場合には、更新のたびに無期転換後の労働条件を明示する必要があります。
労働条件明示義務に違反した場合の罰則
労働条件の明示義務に違反した場合、労働基準監督署による指導や是正勧告がはいります。
指導後も改善されない場合は、30万円以下の罰則が科される可能性があります。
また、企業名が公表されたり、ハローワークを介しての求人も募集できなくなったりする可能性もあるため、注意が必要です。[注5]
労働条件通知書の交付に関する注意点
労働条件通知書を交付する際は、以下の2点に注意する必要があります。
- 改正内容を反映する
- 最新の正確な内容を記載する
適正な労働条件通知書の交付ができるように、2つの注意点を確認していきましょう。
改正内容を反映する
労働条件通知書を作成する際は、最新の法改正内容を必ず反映する必要があります。
とくに2024年の改正事項に対応していない場合、法令違反として指摘されるリスクが高まります。
必要に応じて専門家の助言を受け、改正内容の正確な把握・反映ができるように努めましょう。
最新の正確な内容を記載する
労働条件通知書の内容が曖昧であったり古い情報が記載されていたりすると、労働者に不信感を与える可能性があります。
内容は最新かつ正確であることを常に確認するようにしましょう。
たとえば、最低賃金の改定があった際に、以前の賃金のまま交付していないかなど、毎回確認する必要があります。
労働条件通知書の電子交付とは
従来、労働条件通知書は書面で交付されるのが一般的でしたが、現在ではFAXや電子メール、SNSなどの電子交付も認められています。
電子交付には、コスト削減や業務効率化といったメリットがあり、とくにリモートワークを導入している企業での利用が進んでいます。
ただし、電子交付は労働者が希望した場合のみ可能となります。
企業側の判断のみで電子交付はできないため、注意しましょう。[注6]
労働条件通知書の交付にも「Chatwork」
労働条件通知書は、労働基準法第15条に基づいて企業が従業員に対して労働条件を明示するための書類です。
労働条件通知書の交付は、労働条件に関するトラブルを防ぎ、従業員が安心して働けるようになる効果があります。
また、2024年4月の法改正により、就業場所や業務内容の変更範囲、無期転換後の労働条件などの明示義務が加わりました。
労使間のトラブルを防ぐためにも労働条件通知書は必ず交付しましょう。
ビジネスチャット「Chatwork」はチャット形式で簡単にメッセージが送れるコミュニケーションツールです。
また、チャット機能に加えて、資料や画像、動画などを添付することも可能であるため、従業員が希望する場合は「Chatwork」を活用して、労働条件通知書を交付することも可能です。
「Chatwork」は、ビジネス専用のコミュニケーションツールのため、高いセキュリティ水準に則って運用がされています。
「Chatwork」を活用して、安全かつ効率的な労働条件通知書の交付を目指してください。
Chatwork(チャットワーク)は多くの企業に導入いただいているビジネスチャットです。あらゆる業種・職種で働く方のコミュニケーション円滑化・業務の効率化をご支援しています。

[注1]出典:e-Gov法令検索「労働基準法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
[注2]出典:厚生労働省「採用内定時に労働契約が成立する場合の労働条件明示について」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/201712_saiyounaitei.pdf
[注3]出典:厚生労働省「労働基準法の基礎知識」
https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/content/contents/000841541.pdf
[注4]出典:厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000916194.pdf
[注5]出典:厚生労働省「労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません!」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000184718.pdf
[注6]出典:厚生労働省「平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります」
https://www.mhlw.go.jp/content/000481172.pdf
※本記事は、2025年2月時点の情報をもとに作成しています。








記事監修者:北 光太郎(きた こうたろう)
きた社労士事務所 代表。大学卒業後、エンジニアとして携帯アプリケーション開発に従事。その後、社会保険労務士として不動産業界や大手飲料メーカーなどで労務を担当。労務部門のリーダーとしてチームマネジメントやシステム導入、業務改善など様々な取り組みを行う。2021年に社会保険労務士として独立。労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。法人向けメディアの記事執筆・監修のほか、一般向けのブログメディアで労働法や社会保険の情報を提供している。