固定残業代とは?計算方法やメリット・デメリットを解説
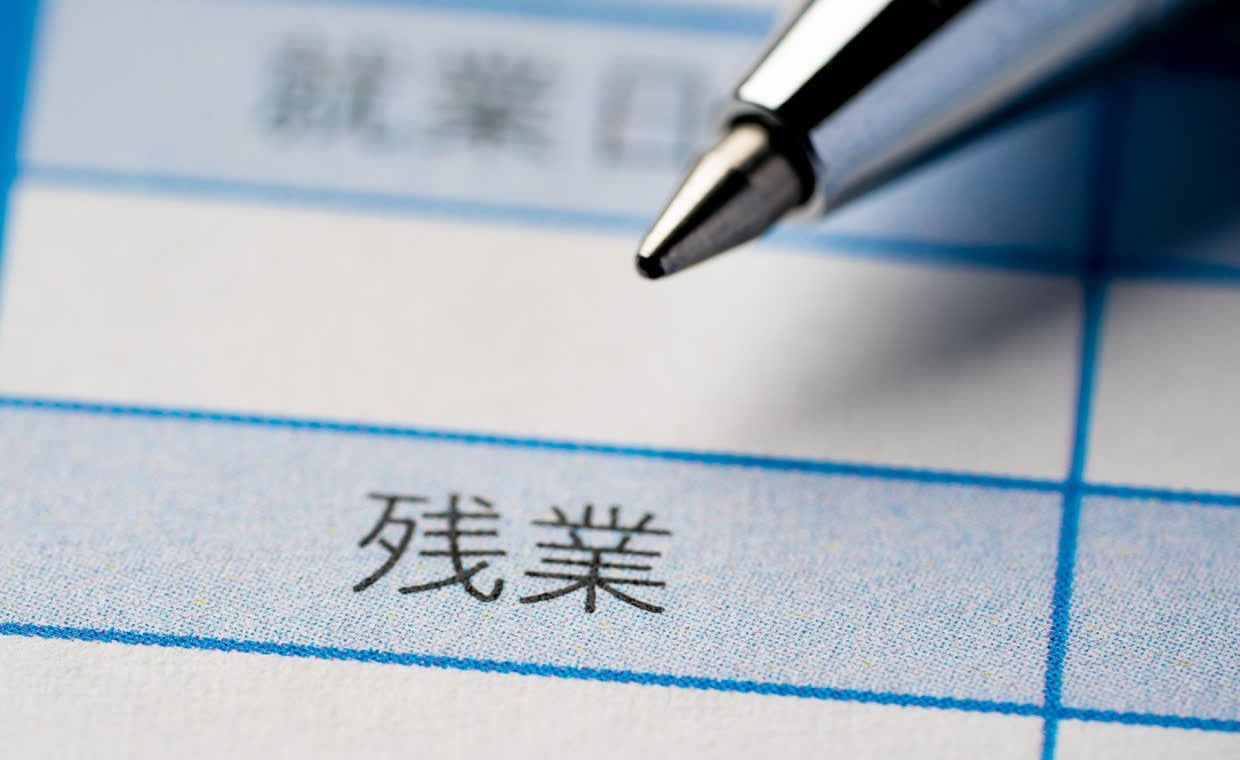
目次
固定残業代とは、あらかじめ一定時間分の残業代を固定給として支払う制度です。
従業員の給与が安定しやすいなどのメリットがある一方で、企業側には制度の理解と適切な運用が求められます。
今回は、固定残業代の仕組みや計算方法、企業側・従業員側の双方のメリット・デメリットを解説します。
固定残業代とは
固定残業代とは、あらかじめ一定時間分の残業代を、基本給とは別に固定給として支払う制度のことです。
「みなし残業代」とも呼ばれることもあります。
実際の残業時間に関わらず、あらかじめ決められた時間分の残業代が支払われるのが特徴です。
たとえば、「月30時間分の固定残業代を支給」と定められている場合、従業員が30時間未満の残業をした場合でも、企業は必ず30時間分の残業代を支払わなければなりません。
一方で、30時間を超えた場合は、超過分の残業代を追加で支払う必要があります。
また、固定残業代を導入する際は雇用契約書や就業規則に「固定残業代を含む給与額」や「何時間分の残業代に相当するのか」などを明確に記載することが求められます。
[※1]固定残業時間の上限
固定残業代制度を導入する際は、法律上、固定残業時間の明確な上限は定められていません。
しかし、労働基準法に基づく労働時間の上限を超えて定めることはできません。
労働基準法では、時間外労働の上限を原則 月45時間・年360時間と定められています。
また、特別条項付き36協定を締結した場合でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間以内と制限が設けられています。
固定残業代として設定する時間が労働基準法で定める時間外労働時間の上限を超える場合、法的に問題となります。
[※2]固定残業とみなし労働時間制の違い
固定残業制度は、あらかじめ一定の残業時間を定め、毎月その時間分の残業代を支払う制度です。
一方、みなし労働時間制は、労働時間の把握が困難な場合や特定の業務に対し、あらかじめ定められた時間を労働時間とみなすことができる制度です。
業務の性質上、労働時間を正確に把握することが難しい場合に適用されます。
また、固定残業代は実際の残業時間があらかじめ定められた残業時間を超えた分は別途支払いが必要なのに対し、みなし労働時間制は実際に残業をしていても、みなし労働時間分を超過した分の支払い義務がない点に違いがあります。
固定残業代のメリット
固定残業代を導入することでどのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは従業員側と企業側に分けてメリットを解説します。
従業員側のメリット
固定残業代があることで、毎月の給与が安定しやすくなります。
特に、残業時間が一定しない職場では、あらかじめ決まった額の残業代が支給されることで、収入の見通しが立てやすくなります。
また、業務効率を上げて実際の残業時間を減らした場合でも、固定残業代は支給されるため、働き方次第で実質的な時給が上がる可能性もあります。
企業側のメリット
給与計算が簡素化され、事務負担が軽減されます。
また、あらかじめ残業代を含めた給与を提示することで、求職者に対し給与水準の高さをアピールできるのもメリットの一つです。
加えて、生活費を稼ぐ目的でおこなう残業(生活残業)をする従業員が多い企業では、一定の残業時間分の支払いが約束されることで、だらだら残業をする習慣を是正する効果が期待できます。
固定残業代のデメリット
固定残業代はメリットがある一方、デメリットもあります。従業員側と企業側に分けてデメリットを解説します。
従業員側のデメリット
「固定残業時間分の残業をしなければならない」という風習ができ、労働時間が長くなる可能性があります。
また、実際の残業が少ない場合でも、固定残業代が含まれることで基本給が低めに設定されることがあるため、賞与や退職金に影響を及ぼす可能性があります。
企業側は、賞与や退職金などを考慮したうえで固定残業代を設定する必要があります。
企業側のデメリット
制度を正しく理解せず運用しなければ未払賃金が発生する可能性があります。
特に「いくら残業させても固定残業代以上の残業代は払わなくていい」と思い込んで運用している場合は、注意が必要です。
また、残業時間が少ない時期でも固定残業代を支払うため、固定残業代を導入する前よりも人的コストが高くなる可能性があります。
固定残業代を導入する際は制度理解はもちろんのこと、自社に適しているのかの検討をしたうえで導入しましょう。
固定残業代の計算方法
固定残業代は、基本給をもとに残業時間分の賃金を計算し、あらかじめ給与に組み込む形で支給されます。
主な計算方法は以下の2つのケースです。
ケース①:残業時間単価を算出して固定残業代を決定する
時間単価の算出
基本給 ÷ 1ヶ月の所定労働時間 = 1時間あたりの賃金
固定残業代の算出
1時間あたりの賃金 × 割増率(通常25%) × 固定残業時間 = 固定残業代
例)
・基本給:30万円
・1ヶ月の平均所定労働時間:160時間
・固定残業時間:20時間
300,000円 ÷ 160時間 = 1,875円(1時間あたりの賃金)
1,875円 × 1.25 × 20時間 = 46,875円(固定残業代)
ケース②:総支給額から逆算して固定残業代を決定する
・固定残業代の算出
固定残業代 ={ 給与総額 ÷ (月平均所定労働時間 + 固定残業の対象時間 × 割増率)} × 固定残業の対象時間 × 割増率
・基本給の算出
総支給額 − 固定残業代
例)
・総支給額:30万円
・1ヶ月の平均所定労働時間:160時間
・固定残業時間:20時間
固定残業代
{300,000 ÷ (160 + 20時間 × 1.25)}× 20時間 × 1.25 =40,541円(10円未満切上げ)
基本給
300,000 − 40,541 = 259,459円
※固定残業代の切り上げ位置は任意
なお、固定残業代を導入する際は、基本給が最低賃金を下回らないように注意しましょう。
固定残業時間を超えた場合の扱い
固定残業時間を超えた場合は、超過分の残業代を別途支払う必要があります。
たとえば、固定残業時間が20時間で、実働30時間の時間外労働が発生した場合は、10時間分の残業代を追加で支払う必要があるということです。
固定残業代を支給していても労働時間の管理が求められるため、タイムカードや勤怠管理システムを活用し、実際の労働時間を把握しましょう。
固定残業と割り増し賃金の関係
固定残業代には、一般的に時間外労働の割増賃金(25%)が含まれていますが、企業によっては深夜労働や休日労働分を含んで固定残業代として支給している場合もあります。
もし、深夜労働(22時~翌5時)や休日労働を固定残業代に含めない場合には、別途割増賃金が適用されるため注意が必要です。
たとえば、固定残業代の範囲内で深夜残業を行った場合でも、深夜労働に該当する時間には追加の割増賃金(25%)を支払う必要があります。
固定残業代を導入する際は、割増賃金の適用範囲を正しく理解し、適切に計算することが求められます。
固定残業代が違法になるケース
固定残業代は適切に運用しないと違法となる可能性があります。
以下のようなケースでは、労働基準法違反に該当し、未払い残業代の請求や企業側の責任追及につながることがあるため注意が必要です。
超過分の未払い
企業が固定残業代の支払いを理由に超過分の残業代を支払わない場合、未払賃金が発生します。
本来、固定残業時間を30時間と設定していても、実際に40時間の残業を行った場合は、超過分の10時間の残業代を別途支給しなければなりません。
超過分の未払いが発覚した場合は、従業員側が未払い残業代を請求でき、企業側は未払賃金の支払いに加え、遅延損害金の支払いも発生する可能性もあります。
割り増し賃金の未払い
固定残業代には、一般的に時間外労働の割増賃金(25%)が含まれますが、深夜労働(22時~翌5時)や休日労働(法定休日)を含めていない場合が多くあります。
たとえ、固定残業代を支給していても深夜労働や休日労働の割増賃金は別途支払いが必要です。
自社の就業規則を確認し、固定残業代が含まれている割増賃金を確認したうえで、別途計算の必要な割増賃金を把握しておきましょう。
割増賃金の未払は労働基準法違反となり、行政指導の対象となる可能性があります。
最低賃金を下回る
固定残業代を含めた給与が最低賃金を下回る場合、違法となります。
たとえば、基本給が極端に低く設定され、固定残業代によって給与の総額を引き上げるような賃金設計をしている場合、基本給部分を時給換算したときに最低賃金を下回っていれば最低賃金法違反となります。
最低賃金を下回ると、企業は是正勧告を受ける可能性があるため、最低賃金が改定されたときは必ず確認しておきましょう。
固定残業代を導入する際の注意点
固定残業代を適切に運用するためには、法令を遵守し、従業員とのトラブルを防ぐことが重要です。
就業規則や求人情報への明記、最低賃金の確保、労働時間の適正管理など、導入時に注意すべきポイントを押さえておきましょう。
就業規則に明記する
固定残業代を導入する場合は、賃金規程や就業規則に具体的な内容を明記することが必須です。
記載すべき主な内容としては以下の項目が挙げられます。
- 固定残業代の名称
- 固定残業代の対象となる手当
- 固定残業時間
- 固定残業代の金額
- 超過分を追加で支払う旨
ここで注意しておきたいのは、固定残業代の名称です。
本記事では「固定残業代」という名称を用いていますが、名称については法律上の定められていないため、会社が任意に定めることができます。
たとえば、「業務手当」や「職務手当」などの名称で性質上は固定残業代として支給することも可能です。
ただし、固定残業代を認識できないような名称にしてしまうと従業員とのトラブルを招く恐れがあります。
残業代として支払われていることが明確にわかる名称にすることが望ましいでしょう。
また、従業員ごとに時間数や金額が異なる場合は、就業規則に記載する必要はありませんが、労働条件通知書に時間数と金額を明記して本人に通知する必要があります。
求人情報に明記する
求人情報に固定残業代の詳細を記載しないと「基本給」と誤認させる表示とみなされ従業員とトラブルが発生する可能性があります。
「若者雇用促進法」に基づく指針では、「固定残業代」について求人票に以下のような表示をするよう定めています。
[※1]- 固定残業時間
- 固定残業代の金額
- 超過分を追加で支払う旨
たとえば、「月給30万円(固定残業代40時間分・8万円含む)」のように記載し、求人票を掲載するときは求職者が正確に理解できるようにしましょう。
不利益変更にならないようにする
既存の給与体系から固定残業代制度に変更する際、従業員にとって不利益な変更とならないようにしなければなりません。
基本給を引き下げて固定残業代を導入すると、実質的な賃下げと判断される場合があります。
賃金体系の変更には、原則として従業員の同意を得ることが必要であり、無断での変更はトラブルの原因になります。
基本給が最低賃金を下回らないようにする
固定残業代を含めた総額ではなく、基本給部分が最低賃金以上であることを確認する必要があります。
地域ごとの最低賃金を考慮し、基本給が適正な水準であるか慎重にチェックしましょう。
また、改正があった際は施行日までに賃金の見直しを行い、場合によっては雇用契約の再締結が必要な場合もあります。
最低賃金の情報は必ず確認し、早めに準備を進めておきましょう。
労働時間を適切に把握・管理する
固定残業代を導入していても、固定残業時間を超えた場合には超過分の残業代を支払う必要があるため、労働時間の管理は必須です。
勤怠管理システムの導入などを検討し、労働時間の管理を徹底しましょう。
適切な労働時間の管理に「Chatwork」
固定残業代制度を導入する企業では、労働時間の適正な管理がより重要になります。
固定残業代は一定時間分の残業代をあらかじめ給与に含める仕組みですが、適切に運用しなければ未払い残業代の発生や従業員とのトラブルにつながる可能性があります。
従業員の実際の労働時間を正確に把握し、固定残業時間を超えた分の残業代を適切に支払うことが求められます。
ビジネスチャットツール「Chatwork」を活用すれば、リアルタイムで情報共有ができ、業務の遅れや不明点を解消できます。
タスク管理機能を活用することで、各自の業務範囲を明確にし、不要な長時間労働の抑制にもつながります。
適切な労働時間管理と業務の効率化を実現するために、ぜひ「Chatwork」の導入をご検討ください。
Chatwork(チャットワーク)は多くの企業に導入いただいているビジネスチャットです。あらゆる業種・職種で働く方のコミュニケーション円滑化・業務の効率化をご支援しています。

[※1]出典:厚生労働省「固定残業代 を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000184068.pdf
[※2]出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」
https://www.mhlw.go.jp/content/001140962.pdf








記事監修者:北 光太郎
きた社労士事務所 代表。大学卒業後、エンジニアとして携帯アプリケーション開発に従事。その後、社会保険労務士として不動産業界や大手飲料メーカーなどで労務を担当。労務部門のリーダーとしてチームマネジメントやシステム導入、業務改善など様々な取り組みを行う。2021年に社会保険労務士として独立。労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。法人向けメディアの記事執筆・監修のほか、一般向けのブログメディアで労働法や社会保険の情報を提供している。