総務が突然辞めた!会社の機能不全を防ぐ後任探しと外注活用の完全ガイド
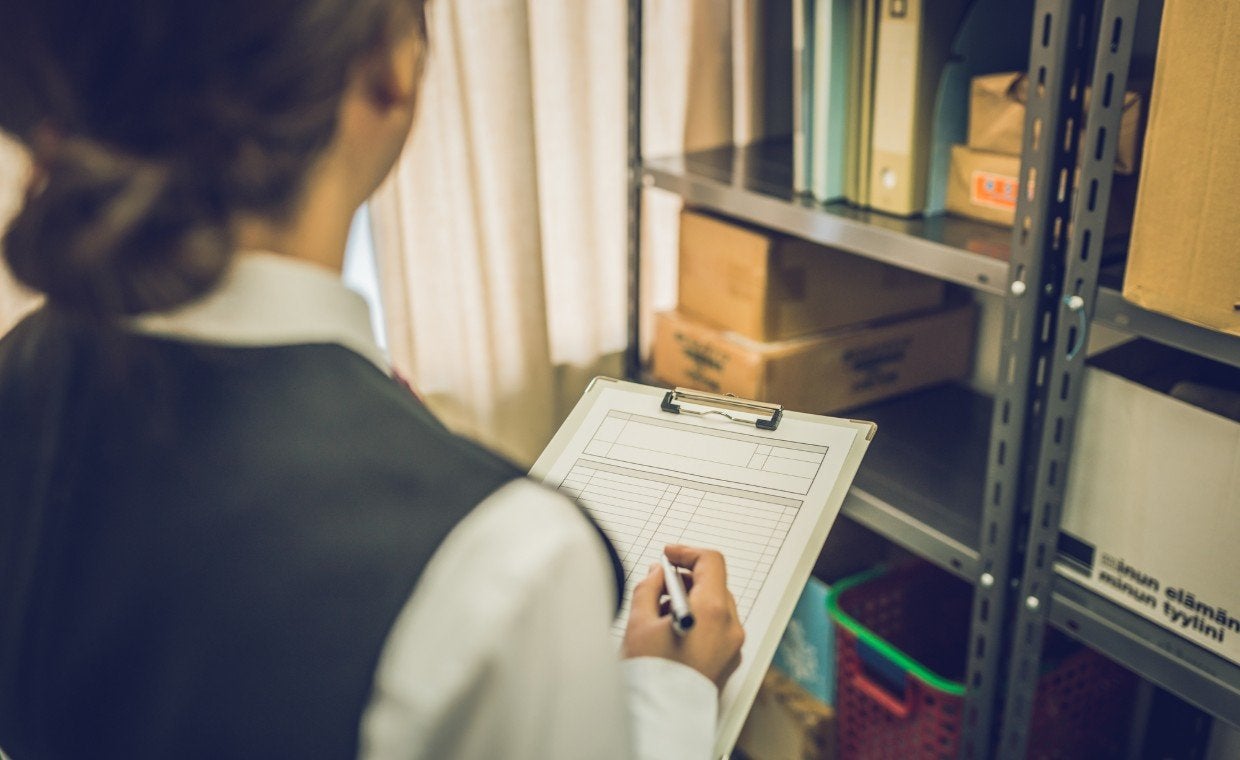
目次
会社の「縁の下の力持ち」として、潤滑油の役割を担う総務担当者。
もし、そのキーパーソンが十分な引き継ぎもなく突然辞めたとしたら、あなたの会社は正常に機能し続けることができるでしょうか。
総務の仕事は、範囲の広さゆえに業務内容が見えにくく、特定の担当者に知識やノウハウが集中する「属人化」が極めて起こりやすい領域です。
本記事では、総務担当者が突然の退職を選んでしまう理由や、実際に起きてしまった場合の具体的な対処法、退職を防ぐための事前対策などを徹底解説します。
さらに、後任探しの選択肢として、社内登用と「外注(総務代行)」を比較しつつ、企業の状況に応じた解決策も紹介します。
総務担当者が突然退職すると何が起こるのか
まず、総務担当者がいなくなると、具体的にどのような混乱が生じるのかを理解しておく必要があります。
総務の業務は「会社のあらゆる部署が担当しない、その他すべての業務」と言われるほど広範です。
オフィス・ファシリティ管理:オフィスの賃貸借契約管理、レイアウト変更、備品・消耗品の発注・管理、複合機などのリース管理、清掃業者の管理など。
文書・規程管理:契約書や重要書類のファイリング・保管、社内規程の策定・改訂・管理、印章(社印・角印など)の管理。
受付・来客対応:代表電話の応対、来客の取次、会議室の予約管理。
福利厚生・安全衛生:健康診断やストレスチェックの実施、防災訓練の企画・運営、社宅の管理、慶弔関連業務。
株主総会・取締役会運営:招集通知の発送、会場設営、議事録の作成・保管など。
社内イベント企画・運営:社員総会や忘年会、社員旅行などの企画・手配。
これらの業務がストップすると、従業員は「電球が切れたけど、誰に頼めばいい?」「この契約書、どこにある?」といった細かな疑問やトラブルを解決できなくなり、本来の業務に集中できなくなります。
社内の至る所で業務が滞り、組織全体の生産性が著しく低下するおそれがあります。
総務担当者が突然退職する理由
会社の土台を支える重要なポジションでありながら、なぜ総務担当者は突然の退職を決意してしまうのでしょうか。
その背景には、総務特有の構造的な課題が潜んでいます。
理由1:業務範囲の広さと曖昧さ
総務の業務範囲には明確な境界線がなく、「誰の仕事でもない仕事」がすべて押し付けられがちです。
次から次へと舞い込む多種多様な依頼に対応するうちに、本来やるべき重要業務が後回しになり、常に何かに追われている状態になります。
この幅広い業務範囲が、精神的な疲弊につながる大きな理由です。
理由2:評価されにくい「減点評価」の仕事
総務の仕事は、できて当たり前、問題が起きた時だけ非難される「減点評価」になりがちです。
コスト削減や業務効率化で成果を上げても、それが売上のように直接的な数字で見えにくいため、正当な評価や昇給に結びつきにくい傾向があります。
「感謝されることもなく、評価もされない」という不満が、モチベーションの低下を招きやすくなります。
理由3:キャリアパスの描きにくさ
総務担当者は「何でも屋」として器用貧乏になりがちであり、特定の専門性を磨きにくいことが悩みです。
「このまま総務を続けていても、自分の市場価値は上がるのだろうか」という不安から、専門職やよりキャリアアップが見込める他社への転職を決意することがあります。
理由4:調整役としてのストレス
総務は、社内の様々な部署や従業員から依頼や要望を受けます。
時には部署間の利害調整を行ったり、会社のルールを盾に厳しいことを言わなければならなかったりする場面もあります。
この調整役としてのストレスが、人間関係の悩みにつながることも少なくありません。
総務担当者が突然退職した場合のリスク
十分な引き継ぎもなく総務担当者が不在となった場合、企業は事業運営の根幹に関わる深刻なリスクに直面します。
以下、主なリスクを紹介します。
契約更新漏れによる事業リスク:オフィスの賃貸借契約や重要なリース契約の更新が漏れ、突然オフィスを退去しなければならなくなったり、事業に必要な機器が使えなくなったりするリスクがあります。
法令違反・コンプライアンスリスク:消防法の規定に沿った防災設備の点検や、法定書類の保管義務など、総務が担う法令関連業務が滞ることで、行政指導や罰則を受ける可能性があります。
社内インフラのブラックボックス化:各種システムの管理者IDやパスワード、重要な契約書の保管場所、取引先業者の連絡先などが分からなくなり、組織運営が麻痺します。
この属人化こそが最大のリスクです。
従業員のエンゲージメント低下:備品が補充されない、問い合わせに誰も答えてくれない、といった状況は、従業員に「この会社は大丈夫か?」という不信感を抱かせます。
働きやすい環境が失われることで、優秀な人材の流出につながります。
総務業務の急な引き継ぎを円滑に行うには
万が一、総務担当者が十分な引き継ぎなしに退職してしまった場合、残された従業員はパニックに陥りがちです。
以下のようなステップで。冷静に対応を進めましょう。
残された情報の洗い出し:まず、前任者のPCやデスク周りを確認し、業務マニュアル、年間スケジュール、取引先リスト、契約書ファイルなどを探します。
クラウドストレージや社内サーバーもくまなくチェックしましょう。
関連部署へのヒアリング:経理部(支払先)、情報システム部(ITツール)、各部署のアシスタントなど、前任者と関わりの深かった従業員にヒアリングし、断片的な情報を集めます。
主要な取引先への連絡:ビルの管理会社、リース会社、清掃会社、社労士・税理士事務所など、定期的にやり取りのあった取引先に連絡し、担当者不在の旨を伝え、今後の窓口や契約状況を確認します。
業務の優先順位付け:集めた情報をもとに、直近で対応が必要な業務(支払、契約更新など)と、そうでない業務をリストアップし、優先順位をつけて対応します。
緊急性の高い業務から、暫定的な後任者が対応していきましょう。
総務担当者の退職に備えてすべきこと
突然の退職という事態を避けるため、そして万が一の事態に備えるためには、日頃からの対策が不可欠です。
以下のような対策を行っておきましょう。
業務の可視化とマニュアル作成:「あの人にしか分からない」状態をなくすことが最も重要です。
誰が担当しても業務を遂行できるよう、業務フローや手順を文書化し、共有フォルダなどで一元管理しましょう。
これが属人化を防ぐ最大の対策です。
複数担当者制の導入:可能であれば、総務業務を一人に任せず、メイン担当とサブ担当を置く体制を構築しましょう。
互いに業務を把握し合うことで、急な欠勤や退職にも対応できます。
ITツールの活用:備品管理システムや契約書管理システムなどのITツールを導入し、業務を効率化・標準化しましょう。
アナログな管理から脱却することが、属人化の解消につながります。
アウトソーシング(外注)の検討:定型的・専門的な業務は、外部の専門業者に外注することも有効な手段です。
社内リソースをコア業務に集中させるとともに、退職リスクをヘッジできます。
総務担当者の後任を社内で探すメリット・デメリット
欠員が出た際、まず検討するのが社内からの後任者の選出です。
しかし、それにはメリットとデメリットの両方があります。
メリット
人柄や能力を把握している:すでに社内にいる人材なので、性格やコミュニケーション能力、仕事への姿勢などを理解しており、ミスマッチが起こりにくいです。
企業文化への理解がある:会社の理念や文化、人間関係をすでに理解しているため、スムーズに業務に入りやすいです。
採用コストがかからない:求人広告費や人材紹介手数料といった採用コストが発生しません。
デメリット
適任者がいない可能性がある:総務には、几帳面さ、コミュニケーション能力、マルチタスク能力など、特有の適性が求められます。
社内に適任者がいない場合、無理な配置転換は本人と組織の双方にとって不幸な結果を招きます。
本人のキャリアプランとの不一致:本人が望まない異動の場合、モチベーションが上がらず、早期の退職につながる可能性があります。
結局、属人化が繰り返される:根本的な業務の仕組み化が行われないまま後任者を置いただけでは、新たな属人化を生むだけで、問題の先送りにしかなりません。
総務代行を外注するメリット・デメリット
社内で適任な後任者が見つからない場合や、属人化を根本から解決したい場合に有効なのが、総務代行の外注です。
メリット
専門性の高い人材を確保できる:総務業務の経験豊富なプロフェッショナルに業務を任せることができ、業務品質の向上が期待できます。
退職リスクからの解放:代行業者は組織として対応するため、担当者一人の退職によって業務がストップするリスクがありません。
採用・教育コストの削減:正社員を一人採用し、育成するコストと比較して、トータルコストを抑えられる場合があります。
コア業務への集中:経営者や他の従業員が雑務から解放され、本来のコア業務に集中できる環境が整います。
デメリット
社内にノウハウが蓄積されない:業務を外部に委託するため、社内に実務的なノウハウが蓄積されにくいです。
情報漏洩のリスク:社内の情報を外部と共有するため、セキュリティ体制が万全な業者を慎重に選ぶ必要があります。
柔軟性の低下:契約範囲外の突発的な業務や、社内独自の細かなルールへの柔軟な対応が難しい場合があります。
総務代行先を選ぶポイント
自社に最適な総務代行サービスを選ぶためには、以下のようなポイントを比較検討しましょう。
対応業務の範囲:自社が依頼したい業務(備品管理、電話対応、契約書管理など)にどこまで対応しているかを確認します。
料金体系:月額固定制か、時間制の従量課金制かなど、料金体系が自社の依頼内容や予算に合っているかを確認します。
セキュリティ体制:PマークやISMS認証の取得状況など、情報管理体制が信頼できるかを確認することは必須です。
実績と柔軟性:自社と似た業種や規模の企業での実績が豊富か、また、業務量の変動などに柔軟に対応してくれるかを確認しましょう。
おすすめの総務代行先10選
ここでは、実績が豊富で信頼性の高い総務代行・オンラインアシスタントサービスを10社ご紹介します。
1. CASTER BIZ(株式会社キャスター)
業界のパイオニア的存在。
秘書・人事・経理・Web運用など幅広い業務に対応可能で、厳しい選考を通過した優秀なアシスタントがチームでサポートするのが特徴です。
2. HELP YOU(株式会社ニット)
総務、経理、人事、営業サポート、メディア運用など、多岐にわたる業務をチームでサポート。
ディレクターが窓口となり、業務の切り分けからサポートしてくれるため、初めての外注でも安心です。
3. フジ子さん(BROテクノロジー株式会社)
月額5万円台(実働20時間)からとリーズナブルな価格設定が魅力。
必要な業務を必要な分だけ依頼でき、コストパフォーマンスに優れています。
4. タスカル(株式会社Colors)
月10時間・2.75万円からという低価格で始められるのが最大の特徴。
スタートアップや個人事業主にも導入しやすく、幅広い事務作業に対応しています。
5. i-STAFF(株式会社ビープラスト)
採用率1%の優秀なスタッフが、秘書・経理・人事・Web運用などをサポート。
返金保証制度もあり、品質に自信を持っています。
6. FOC総務アウトソーシングサービス(芙蓉アウトソーシング&コンサルティング株式会社)
約30年の歴史を持つ、国内有数の総務アウトソーサー。
長年の実績とノウハウに基づき、企業の課題に合わせた最適なサービスを提供します。
7. コクヨ&パートナーズ(コクヨ&パートナーズ株式会社)
オフィス用品でおなじみのコクヨグループが提供するサービス。
オフィス運営全般の総務業務に強みを持ち、コンサルティングも行っています。
8. クラウドワークスエージェント(株式会社クラウドワークス)
クラウドソーシング大手のクラウドワークスが運営。
豊富な人材データベースから、企業のニーズに合ったアシスタントをマッチングします。
9. パソナ(株式会社パソナ)
人材派遣業務と数多くのBPOの受託実績から得られたノウハウを持つ企業です。
ニーズに合わせて、派遣や業務委託などの形態で提案をしてもらうこともできます。
10. Remobaアシスタント(株式会社Enigol)
月30時間から利用可能で、経理、人事労務、営業アシスタントなど、各分野の専門スキルを持ったアシスタントが在籍しています。
総務代行なら『Chatwork 総務アシスタント』がおすすめ!
数あるサービスの中でも、とくに幅広い業務を少しずつサポートしてほしい、というニーズに最適なのが『Chatwork 総務アシスタント』です。
『Chatwork 総務アシスタント』は、採用率1%の厳しい基準をクリアした優秀なアシスタントが、チームで業務をサポートするオンラインアシスタントサービスです。
最大の特徴は、月10時間からという短い時間から契約でき、総務、経理、人事、秘書といった様々な業務を、契約時間の範囲内で自由に組み合わせて依頼できる圧倒的な柔軟性にあります。
Chatwork 総務アシスタントを導入するメリット
メリット1:コストを抑えてスモールスタートできる
月10時間という短時間から契約できるため、正社員を一人採用するのに比べて圧倒的に低コストで導入可能です。
まずはノンコアな定型業務から外注し、効果を見ながら依頼範囲を広げていくことができます。
メリット2:業務の属人化を防ぎ、安定した体制を構築できる
業務はアシスタントチームが組織として対応し、マニュアルを整備しながら進めます。
これにより、特定の担当者に依存する「属人化」体制から脱却し、担当者の急な退職にも動じない安定した業務基盤を築けます。
メリット3:総務以外の業務もまとめて依頼できる
中小企業では、総務担当者が経理や人事業務を兼任しているケースも少なくありません。
Chatworkアシスタントなら、契約時間内でこれらの業務もまとめて依頼できるため、「ひとりバックオフィス」が抱える課題を包括的に解決できます。






