ファイル共有の最適な方法は?比較ポイントや効率化のコツなど徹底解説!
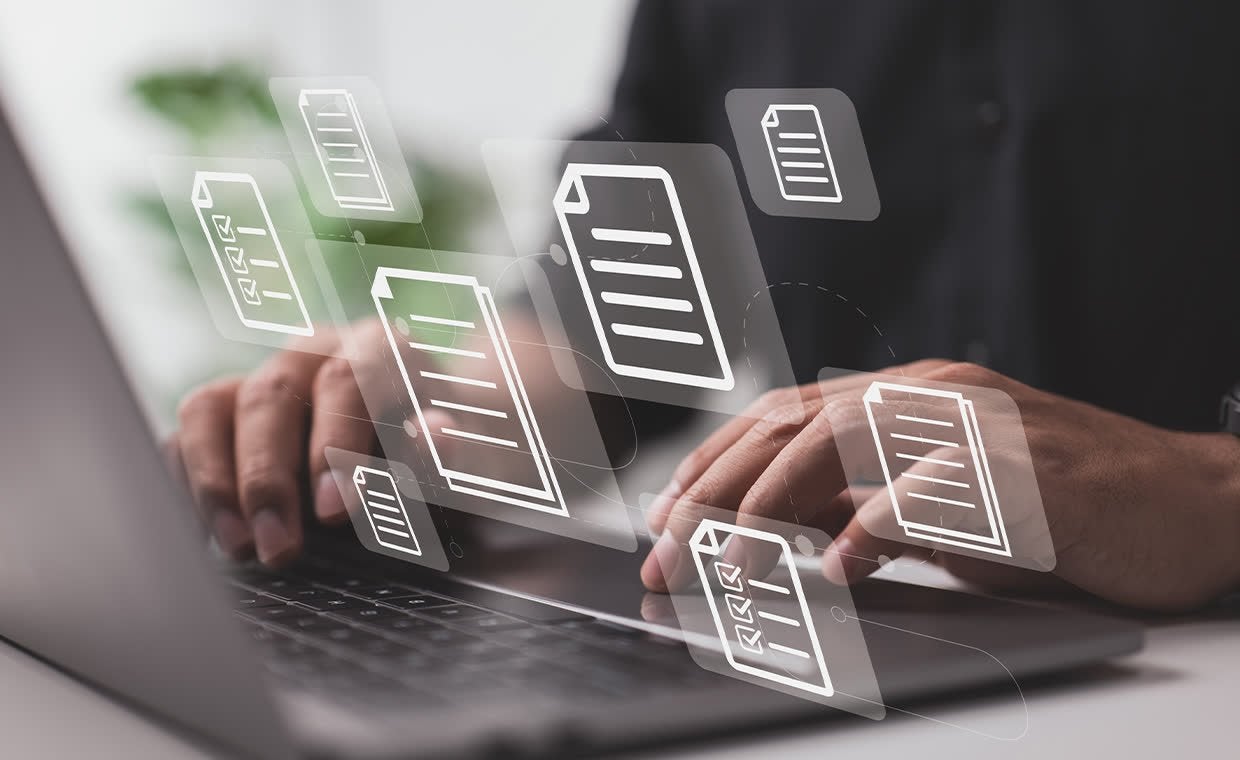
目次
「どのファイル共有方法が一番効率的なのか、正直よくわからない」
そんなお悩みはないでしょうか?
適切でないファイル共有方法を選ぶと、情報漏えいのリスクや、作業の手間・混乱が増える原因になります。
この記事では、ファイル共有方法の特徴や、効率化のポイントなどをわかりやすく解説します。
業務効率とセキュリティを両立させたい方は、ぜひ参考にしてください。
ファイル共有の基本
ビジネスの現場では、複数人で同じファイルを扱う場面が日常的に発生するため、ファイル共有が不可欠です。
ここでは、ファイル共有の基本と得られるメリット・注意すべきデメリットについて解説します。
ファイル共有とは
ファイル共有とは、文書や画像、動画、音楽などのデジタルデータを、複数のユーザーやデバイス間でやり取り・共有する仕組みです。
従来はメール添付やUSBなどを使ってファイルを「送る」形式が一般的でしたが、最近では「同じファイルへ同時アクセスして作業する」というスタイルが主流になりつつあります。
クラウドストレージやファイルサーバーなどの共有サービスを利用すれば、ユーザーごとに「閲覧のみ」「編集可」などの権限を設定でき、誰が・いつ・どのようにアクセスしたのかも記録できます。
その結果、場所を問わずスムーズな情報共有と共同作業が可能になります。
ファイル共有のメリット
ファイル共有には、チームでの作業効率を大きく高める利点がいくつもあります。
とくにテレワークや柔軟な働き方が進む現代では、その恩恵を受ける機会が増えています。
【メリット】
・情報共有のスピードが向上:リアルタイムでの情報共有が可能になるため、業務のタイムロスが減ります。
・共同編集で作業効率アップ:複数人が同じファイルを同時編集できるため、確認・修正の手間を省けます。
・データのバックアップが容易:クラウドストレージなどでは、自動的にファイルが保存・保護され、紛失のリスクを抑えます。
・アクセスの自由度が高い:社外や自宅からでも、インターネット経由で安全にアクセス可能です。
・コスト削減につながる場合も:ハードディスクやサーバーを導入する必要がない場合、初期投資や保守コストを抑えられます。
ファイル共有のデメリット
便利な一方で、ファイル共有には注意すべきポイントも存在します。
とくにセキュリティや管理面でのトラブルが起きやすいため、導入前にリスクを理解しておくことも重要です。
【デメリット】
・セキュリティリスクがある: 権限設定やウイルス対策を怠ると、機密情報の漏えいや不正アクセスの危険があります。
・バージョン管理が煩雑になりやすい :複数人が同時にファイルを編集すると、どれが最新か混乱することがあります。
・ストレージ容量に制限がある :使い続けるうちにファイル容量が膨れ上がり、保存や同期に支障をきたす可能性があります。
・導入コストや運用負荷が発生することも :高機能な共有サービスでは、初期費用や月額費用が発生する場合があります。
ファイル共有の主な方法とそれぞれの特徴
ファイル共有の方法には、従来より使われてきたメール・USBから、インターネットを活用したクラウド型の方法まで、さまざまな選択肢があります。
ここでは、代表的な7つのファイル共有方法について、特徴をわかりやすく解説します。
ビジネスチャットツール
ビジネスチャットツールでは、テキストのやり取りと同時にファイルも送受信できるため、リアルタイムのコミュニケーションに向いています。
送った資料をその場で確認しながらやり取りができ、業務のスピード感を損なわずに情報共有が可能です。
ただし、過去のファイルを探しづらかったり、大容量のファイルには不向きだったりといった制限もあるため、他の共有手段と併用されることが一般的です。
ビジネスチャットツールChatworkでは、共有されたファイルの前後のやり取りをすぐにさかのぼれる「追加時点へ移動できる機能」(※ファイル投稿時点の会話にジャンプ)があり、共有の経緯を簡単に確認できます。
また、ファイル名検索にも対応しているため、必要な資料にすばやくアクセスできる点も魅力です。
USBメモリ・外付けHDD
USBメモリや外付けHDDは、ネット環境がなくても手軽にファイルをやり取りできる物理的な手段です。
小型で持ち運びしやすく、社内外で直接ファイルを受け渡す際などに使われます。
ただし、紛失や盗難による情報漏えいリスクが高く、ウイルス感染の可能性もあるため、セキュリティ面では注意が必要です。
企業によっては、重要データの取り扱い時にのみUSB利用を制限している場合もあります。
メール添付
メールにファイルを添付して送る方法は、誰もが手軽に使えるスタンダードな手段です。
特別なツールが不要で、すでに導入されているメール環境で対応できます。
しかし、宛先の入力ミスによる誤送信や、ファイルサイズの制限(10〜25MB程度)がデメリットとなることがあります。
また、通信経路の暗号化が不十分だと第三者に情報が漏れる可能性もあるため、機密性の高いデータの共有には不向きです。
>メールで大容量の添付ファイルが送れない原因と対処法に関する記事はこちら
ファイル転送サービス
ファイル転送サービスは、クラウド上にデータをアップロードし、相手に専用のURLを通じてダウンロードしてもらう方法です。
大容量ファイルにも対応しており、通信の暗号化やパスワード設定などセキュリティ面でも安心です。
ただし、サービスによって操作性や料金、機能に違いがあり、自社の用途に合わないサービスを選ぶと、かえって不便に感じることもあるため、使用の際には注意が必要です。
オンラインストレージ
Google DriveやDropboxなどのオンラインストレージは、インターネット経由でいつでもどこでもファイルにアクセスできる利便性が魅力です。
閲覧や編集の権限を細かく設定でき、複数人での共同編集にも対応しています。
一方で、クラウドサービスの仕様に沿った使い方しかできないため、自由度には限りがあります。
また、インターネット環境がないと利用できない点もデメリットとなることがあります。
社内ファイルサーバー
社内にファイルサーバーを設置し、組織内でファイルの共有や保管をおこなうケースもあります。
アクセス権限の設定やセキュリティ対策も整備されており、重要なデータを社内で安全に管理できます。
パソコンの故障時にもデータが守られるという安心感もありますが、サーバーの導入やメンテナンスにはコストがかかり、容量の増設も簡単ではありません。
中〜大規模の企業に多く導入されている方法です。
P2Pファイル共有
P2P(ピア・ツー・ピア)方式は、サーバーを介さずに利用者同士が直接ファイルをやり取りできる仕組みです。
一部の用途では効率的ですが、ウイルス感染や著作権問題などリスクも多く、ビジネス用途としてはあまり一般的ではありません。
個人で利用する際には便利な面もありますが、企業におけるファイル共有にはセキュリティや管理の観点からあまり推奨されない方法といえます。
最適なファイル共有方法の選び方と比較ポイント
先ほど紹介したとおり、ファイル共有サービスは多種多様で、それぞれ機能や使い勝手に違いがあります。
導入後に「思っていたのと違った」とならないように、選定時にはいくつかの観点から慎重に比較することが大切です。
ここでは、ファイル共有方法の選定・比較のポイントについて解説します。
セキュリティの高さ
ファイル共有では機密情報を扱うこともあるため、セキュリティ対策は欠かせません。
データ通信の暗号化ができるかどうかについてはもちろんのこと、アクセス制限の柔軟さやIP制限、ログ管理などの機能が整っているかを確認しましょう。
また、提供元の企業がどのようなセキュリティポリシーを掲げているかも重要です。
セキュリティの甘いサービスを選ぶと、情報漏えいなどのリスクを招くおそれがあるため注意が必要です。
共有ファイルの容量と種類
ファイル共有サービスを選ぶ際は、対応できるデータ容量とファイルの種類も確認しておきたいポイントです。
業務で動画や高解像度画像、大量のドキュメントなどを扱う場合は、大容量に対応しているサービスが必要となるためです。
サービスによってはアップロードできるファイルサイズの上限が決まっていることもあるため、扱うデータの種類や容量に合った共有方法であるかどうか、事前に確認しましょう。
使いやすさと簡単操作
どれほど高機能なサービスでも、使い勝手が悪ければ現場で活用されません。
ファイルのアップロードや共有、検索といった基本操作が違和感なく使えるかは非常に重要です。
初めて使う人でも戸惑わないシンプルな画面設計であるか、サポート体制やマニュアルが充実しているかも確認ポイントとなります。
トライアル期間などを活用して、実際の使用感を試すことも効果的です。
コスト
コスト面もファイル共有サービスを比較するうえで欠かせない要素です。
多くのサービスは、無料プラン・スタンダードプラン・ビジネス向けプランといった複数の料金体系を用意しており、ストレージ容量や利用できる機能の範囲によって金額が異なります。
予算に見合っているか、今後の利用拡大に対応できるかなども考慮し、費用対効果の高いサービスを選びましょう。
OS・デバイス対応
業務で使う端末の種類やOSに対応しているかどうかも、見逃せないポイントです。
WindowsやMacに加えて、外出先からのアクセスを想定する場合はiOSやAndroid端末への対応も必須です。
マルチデバイスで利用できるサービスであれば、場所を問わずファイルにアクセスでき、柔軟な働き方にも対応できます。
また、利用できる端末の種類や環境とあわせて、ファイルの互換性についてもしっかり確認しておきましょう。
ファイル共有を効率化するコツと注意点
ファイルの共有ミスや情報漏えいを防ぎつつ、スムーズなやり取りを実現するには、いくつかの基本的なルールや仕組みを整えることが重要です。
ここでは、ファイル共有を効率化するためのコツと注意点を解説します。
ファイル名やフォルダ構成のルール化
ファイル共有を円滑に進めるには、明確な命名ルールやフォルダ構成を設定することが大切です。
たとえば、「2025/07/03_営業部_〇〇社様見積書」などのように、「日付(yyyy/mm/dd)部署名_資料名」といった形式で統一しておくと、後から見返すときにどのようなファイルかがすぐにわかります。
また、関連ファイルは1つのフォルダにまとめ、階層を深くしすぎないことも重要です。
ファイル共有をルール化しておけば、業務の教育や引き継ぎもスムーズになります。
アクセス権限の適切な設定
誰でもファイルにアクセスできる状態では、情報漏えいや誤操作のリスクが高まります。
そのため、ファイルやフォルダごとに「閲覧のみ」「編集可能」などの権限を設定する必要があります。
必要最小限の権限を付与する原則を守り、重要なデータにはパスワードや2段階認証の導入も検討しましょう。
また、操作履歴が確認できるシステムを使えば、万が一のトラブル時にも原因を追跡しやすくなります。
定期的な整理と不要ファイルの削除
多くのファイルを共有する場合、古いファイルや不要なファイルの扱いについても決めておきましょう。
そのまま放置していると必要なファイルを探しづらくなり、業務効率が低下してしまいます。
定期的にフォルダ内を見直し、自分が作成した不要なファイル・古いファイルは削除する運用を習慣づけましょう。
あわせて、ファイルの保管期間や整理のルールも決めておくと、社内全体で統一感のある管理が可能です。
定期的なバックアップ取得
注意しながら作業をしていても、誤ってファイルを削除したり、共有中に上書きしてしまったりといった人的ミスは避けられないものです。
不測の事態を想定し、日頃から定期的なバックアップを取っておけば、迅速に元の状態へ復旧することができます。
自動バックアップ機能が備わっているファイル共有システムの場合、積極的に活用することがおすすめです。
セキュリティ対策の徹底
社外とファイルを共有する機会がある場合はとくに、セキュリティ対策を万全にしておく必要があります。
ウイルス対策ソフトの導入やファイアウォールの設定、ファイル転送時の暗号化など、基本的な対策は必ず実施しましょう。
また、OSやソフトウェアの更新を怠らないことも大切です。
社内全体でセキュリティ意識を高めるために、従業員向けの研修やルールブックの整備を検討することも効果的です。
著作権・プライバシーへの配慮
ファイルを共有する際には、著作権やプライバシーを侵害する内容が含まれていないかどうかも忘れずに確認しましょう。
とくに音楽、画像、動画、資料などを共有する場合には、使用許可や出典元の明記が必要なケースもあります。
共有する相手や範囲に応じて、取り扱いに注意を払うことで、法的トラブルや信頼低下などのリスクを回避できます。
最適なファイル共有方法を選んで、業務効率とセキュリティを向上させよう
ファイル共有は、業務効率を左右する重要な要素です。
用途や環境に合わない方法を選んでしまうと、作業効率の低下や情報漏えいなどのリスクにもつながります。
そのため、セキュリティ・操作性・容量・対応端末などの観点から慎重に選ぶことが大切です。
とくに、コミュニケーションとファイル共有を同時に行いたい場合は、ビジネスチャットと連携できるツールがおすすめです。
Chatworkなら、会話の流れで自然にファイルを共有でき、確認や意思決定もスムーズに進みます。
業務の効率化と安全性を両立したい方は、ぜひ活用を検討してみてください。
Chatwork(チャットワーク)は多くの企業に導入いただいているビジネスチャットです。あらゆる業種・職種で働く方のコミュニケーション円滑化・業務の効率化をご支援しています。








