残業の定義とは?平均時間や計算方法などの正しい知識をわかりやすく解説

目次
働き方改革に伴い、残業に関する法改正が進む中、多くの企業が残業時間削減に向けて対応を迫られています。
残業代についても時効年数や割増賃金の適用範囲の変更など、「残業」を取り巻く環境は大きく変化しているといっていいでしょう。
「今さら残業代の計算なんて......」と思わず、正しい知識を身につけることが重要です。
本記事では、残業の定義や種類、計算方法まで詳細をわかりやすく解説します。
残業の定義とは
残業の定義を、「定時を超えた就業」ととらえている方も多いのではないでしょうか。
その考え方も間違いではないですが、正確に残業を定義すると「所定労働時間を超えておこなった労働」となります。
残業を正しく理解するためには、「労働時間」を理解しておくことが必要です。
残業を理解するとともに、労働時間の仕組みについても理解を深めましょう。
平均的な残業時間はどれくらい?
厚生労働省の調査によると、日本の平均的な残業時間は全産業で月平均10.1時間とされています。
具体的には、一般労働者の月平均残業時間は13.9時間で、パートタイム労働者は2.3時間です。
一般労働者は、出勤日数が平均19.6日であることから、1日あたりの残業時間は約43分となります。[注1]
一方、民間の調査では残業時間が月21.9時間と報告されており、出勤日数を20日と仮定すると、1日あたりの残業時間は約66分となります。[注2]
日本では長時間労働が文化的に根付いている部分もありますが、働き方改革が進められ、多くの企業が残業削減に取り組んでいます。
特に2019年4月から施行された残業時間の上限規制により、長時間労働が年々減少していると考えられます。
総じて、日本の残業時間は減少傾向にあり、今後もこの流れが続くことが予想されます。
残業代請求の時効延長とは
働き方改革の影響で、残業に関する法改正も進んでいますが、「未払い残業代の支払いに関する時効延長」もそのうちのひとつです。
残業に関する考え方は、やや複雑な面があるため、図らずとも未払い残業代が発生してしまい、発覚後に従業員から未払い分を請求される、といったトラブルが度々みうけられます。
この未払い残業代の支払い義務は、従来「2年前まで」の残業代をさかのぼって請求することが可能とされていましたが、2020年4月からこの時効が3年間に延長されました。
未払い残業代は、場合によっては多額の金額になることも想定され、3年前までさかのぼれるとなると、支払い義務を負う企業にとっては存続に関わるダメージになる可能性もあります。
このような法改正の背景からも、いま一度、残業代に関する知識をアップデートし、正しい理解をすることが大切であることがわかるでしょう。
>未払い賃金の時効延長と企業に求められる対応に関する記事はこちら
所定労働時間とは
残業の正しい理解には、「労働時間」が欠かせない要素ですが、労働時間には、「所定労働時間」と「所定外労働時間」の2種類が存在します。
「所定労働時間」は、職場の就業規則や雇用契約で定められている通常の労働時間を指すもので、たとえば、
始業9:00、終業17:00、休憩は12:00から13:00までの1時間
この職場の場合は、所定労働時間が7時間ということになります。
所定労働時間の7時間を超える労働時間を所定外労働時間と呼び、この労働時間が残業代の対象となります。
>【社労士監修】労働基準法における休憩時間の定義とは?に関する記事はこちら
所定労働時間と法定労働時間の違い
所定労働時間とは、会社の就業規則や労働契約で決められた労働時間です。
所定労働時間は法定労働時間を超えない範囲で設定され、企業ごとに異なります。
一方、法定労働時間は労働基準法によって定められた1日8時間、1週間40時間までの上限時間のことです。
つまり、法定労働時間が法律で定められた上限であるのに対し、所定労働時間は各企業で個別に決められる実際の勤務時間となります。
たとえば、法定労働時間が1日8時間であっても、ある企業の所定労働時間が1日7時間と定められているといったケースがあります。
このように、法定労働時間は労働者を保護するための法的基準であり、所定労働時間はその範囲内で企業と従業員が合意した勤務時間ということです。
残業代の考え方と計算方法
残業代とは、所定労働時間を超えた労働時間に対して支払われる賃金です。
たとえば、所定労働時間が7時間だとすれば、7時間を超えた時間から残業時間となり、企業は残業代を支払う義務が発生します。
また、労働時間が法定労働時間である1日8時間を超えた時間(法定外残業)は、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。
一方、法定労働時間未満で所定労働時間を超えている時間(法定内残業)に対しては割増賃金の支払いは義務付けられていません。
たとえば、所定労働時間が7時間の企業で10時間働いた場合は、1時間が法定内残業時間、2時間が法定外残業時間となります。
この場合、1時間分の時間単価と2時間分の時間単価×1.25の賃金の支払いが必要になります。
具体的な残業代の計算方法を見ていきましょう。計算方法は以下のとおりです。
- 月給:30万円
- 月の平均所定労働時間:160時間
- 残業時間:20時間
- 時間単価 = 300,000円 ÷ 160時間 = 1,875円
- 残業代 = 1,875円 × 20時間 × 1.25 = 46,875円
月給の場合は一般的に「月給÷1か月の平均所定労働時間」で計算して時間単価を算出します。
その他、深夜労働や60時間超の残業の場合は、割増率が増加します。
残業代とそのほかの手当の関係
住宅手当や通勤手当などの基本給以外に支給される手当が、単価計算に加算されるかは、注視すべきポイントです。
基本的には、福利厚生の意味あいが強い手当(住宅手当や通勤手当)や、臨時的な手当などの一部手当を除いて「すべて単価計算に加算すべき」とされています。
つまり、職務手当や役職手当といった手当は、単価計算の際に加算すべき手当です。
しかし、住宅手当や家族手当といった名称の手当であっても、一律従業員全員に支給されている手当は、単価計算に組み込む必要がある点には注意しましょう。
たとえば、実家暮らしでも持ち家の場合でも、住宅手当が一律月額3万円支給されるといった制度を採用している場合は、単価計算に組み込みます。
残業の種類と残業代の割増率について
前述のとおり、法定労働時間を超えた場合には25%以上の割増賃金の支払いが義務付けられていますが、法定休日労働や深夜労働に対しても割増賃金の支払いが必要です。
支払いが義務付けられている割増賃金の種類は以下のとおりです。[注3]
| 種類 | 支払う条件 | 割増率 |
|---|---|---|
| 時間外手当 (残業手当) |
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき | 25%以上 |
| 時間外手当 (残業手当) |
時間外労働が1ヶ月60時間を超えたとき | 50%以上 |
| 休日出勤手当 | 法定休日に出勤したとき | 35%以上 |
| 深夜手当 | 22時から5時までの間に勤務した時 | 25%以上 |
具体的な計算例を4つ挙げるので、それぞれを見ていきましょう。
ケース(1):時間外労働を10時間おこなった場合
10時間の時間外労働に対しては、割増率が25%以上必要です。時間外労働にあたる10時間を計算する際は、時給換算した金額に25%以上をかけます。
たとえば、時給換算した給与が1,500円であった場合、1時間あたりの割増賃金は1,875円(1,500円×1.25)です。
そのため、10時間の時間外労働に対しての残業代は次のとおりです。
10時間×1,500円×1.25=18,750円
ケース(2):法定休日労働を7時間おこなった場合
法定休日に労働をした場合は休日労働として扱われます。
休日労働の割増率は35%です。時給換算した給与が1,500円であれば割増賃金は2,025円となります。
休日労働を7時間した場合の残業代は次のとおりです。
7時間×1,500円×1.35=14,175円
ケース(3):時間外労働を20時間、時間外の深夜労働を3時間おこなった場合
時間外労働が20時間であれば割増賃金率は25%です。
一方、時間外かつ深夜に勤務した場合は、深夜手当として25%が上乗せされます。
たとえば、時給換算した給与が1時間あたり1,500円の場合、時間あたりの時間外労働の割増賃金は1,875円です。
また、時間外労働かつ深夜労働の時間は割増率が50%となり、割増賃金は2,250円となります。
時間外労働を20時間と時間外・深夜労働を3時間した場合の残業代は次のようになります。
- 時間外労働:20時間×1,500円×1.25=37,500円
- 時間外の深夜労働:3時間×1,500円×1.5=6,750円
- 時間外労働・時間外の深夜労働の合計:37,500円+6,750円=44,250円
ケース(4):時間外労働を68時間おこなった場合
時間外労働を68時間した場合、60時間までは25%以上の割増率ですが、60時間をオーバーした部分は50%以上の割増率が求められます。
時給換算が1,500円の場合、1時間あたりの残業代は1,875円です。
対して、60時間をオーバーしている部分の1時間あたりの残業代は2,250円となります。
そのため、時間外労働を68時間した場合の残業代は次のように計算します。
- 60時間の時間外労働:60時間×1,875円=111,000円
- 60時間を超える時間外労働:8時間×2,250円=18,000円
- 時間外労働の合計:111,000円+18,000円=129,000円
勤務形態別の残業代の考え方
ここまで解説してきた残業代の計算は、比較的ベーシックな考え方です。
近年増えているフレックスタイム制や変形労働時間制を導入している企業においては、そもそもの所定労働時間の算出がやや困難であるため、残業代の計算も少し複雑になります。
ここでは、以下のパターン別に残業代の考え方を解説します。
- 管理職の残業代
- フレックスタイム制の残業代
- 裁量労働制の残業代
- 変形労働時間制の残業代
- 年俸制の残業代
- 日給制の残業代
勤務形態や働き方、役職別の残業代の考え方について理解を深め、正しい労務管理をおこないましょう。
管理職の残業代
課長や部長といった「管理職」の残業代については、その管理職の立場が、労働基準法でいうところの「管理監督者」に該当するのかによって、扱いが変わります。
労働基準法で定められた「管理監督者」に該当する場合は、残業代や休日出勤に対する割増賃金を支払う必要がありません。
「管理監督者」に該当するか否かは、厳格な判断が必要となるため、役職さえついていれば「管理監督者」として扱えるわけではない点に注意が必要です。
ただし、「管理監督者」の場合でも、深夜時間帯の労働に対する25%の割増賃金の支払い義務は残ります。
役職の扱いと、それにともなう残業代の支払い義務については、トラブルが発生しやすい点でもあるため、しっかりと理解するようにしましょう。
フレックスタイム制の残業代
「フレックスタイム制」は、始業終業時刻を一律に定めずに、一定の枠内で始業終業の時刻を従業員の裁量に委ねるという働き方のため、どこからが残業時間となるのかの判断が難しいでしょう。
企業でフレックスタイム制を導入する場合は、「清算期間」を設け、この清算期間に対応する法定労働時間の枠内で、所定労働時間を決めるようにしましょう。
フレックスタイム制の残業時間を考える際は、この清算期間内の労働時間のうち、清算期間の法定労働時間を超過した時間が、割増賃金の支払い対象となる残業時間ということになります。
フレックスタイム制は、労働時間を管理しにくい働き方ですが、導入によるメリットも大きいため、ルールや管理方法をしっかりと決めたうえで、スムーズな導入を目指すようにしましょう。
>フレックスタイム制の仕組みや導入のポイントに関する記事はこちら
裁量労働制の残業代
「裁量労働制」とは、所定労働日に、一定時間の労働をしたとみなす働き方です。
たとえば、所定労働日が月曜から金曜で、所定労働時間が各日8時間とすれば、月曜から金曜に、それぞれ、10時間働いていても、7時間働いていても、8時間労働したとみなすということです。
この働き方の場合、残業代が発生しないようにも思えますが、土日の勤務に対しては、裁量労働制の場合も、割増賃金の支払い対象になります。
また、月曜から金曜で、深夜時間帯に勤務していれば、深夜の割増25%の支払いの義務も発生します。
裁量労働制は、従業員側の裁量が大きい働き方ですが、長時間労働やサービス残業なども発生しやすい働き方のため、企業側の管理にも工夫が必要といえるでしょう。
変形労働時間制の残業代
労働基準法においては、法定労働時間は、基本的に1日8時間、1週間40時間以内と定められていますが、ある一定の期間内において、平均して1週間の所定労働時間が40時間以内であれば、法定労働時間を超過していても、割増賃金の支払い義務が発生しないというのが「変形労働制」です。
たとえば、1年間の変形労働時間制の場合、閑散期には8時間×週4日の勤務とし、繁忙期には8時間×週6日の勤務でシフトを組み、1年間を通じて、1週間の平均所定労働時間が40時間以内となるように設定したとします。
この場合、繁忙期の週48時間勤務のうち、40時間を超過する8時間に対しても、変形労働制をとっているため、割増賃金の支払い義務が発生しません。
ただし、所定労働時間を超過する以下のケースに該当する場合は、残業代を支払う必要があるため、注意が必要です。
- ある週で所定労働時間を超え、法定労働時間を超過する場合は、割増賃金
- ある週で所定労働時間を超え、法定労働時間を超えない場合は、通常単価
年俸制の残業代
近年、成果主義の一環として導入されることの多い「年俸制」の場合は、「年俸/1年間の所定労働時間」で、時間あたりの単価を算出することができるため、あとは、通常の残業代の計算と同じように計算することができます。
日給制の残業代
「日給制」に関しても、時間単位の単価を算出することができれば、通常の残業代の計算と同じように計算することができます。
- 時間単位の単価の計算方法
日給÷1日の所定労働時間
- 法定内残業の場合の計算方法
残業時間×時間単価
- 法定外残業の場合の計算方法
残業時間×時間単価×割増率
残業時間に該当するため注意すべき時間
残業時間(労働時間)は、上司などの使用者の指揮命令下にある時間をいいます。
では、どのような時間が労働時間になるのでしょうか。具体的な事例を紹介します。
始業前の準備時間
制服に着替える時間や、会社の決まりとしておこなう朝の掃除時間などは、「指揮命令下にある労働時間」とみなされ、それが時間外労働であれば残業代の支払いが必要になります。[注4]
たとえば、食品を扱っている仕事で安全衛生上の着替えが義務付けられている場合は、始業前の準備時間として労働時間に該当します。
ただし、自宅で制服に着替えて通勤できる場合は認められないケースもあります。
昼休憩中の電話対応
休憩は労働から解放され、労働者が自由に使える時間としなければなりません。
「電話が鳴ったら取って」という電話当番は、完全に労働から解放されていないため原則労働時間になります。
もし昼休み中の電話当番をした場合は、別途休憩が必要になります。[注5]
なお、使用者から指示がなく、たまたま居合わせた従業員が電話を受けるなど、労働者の自由意思で電話を受けた場合は労働時間には該当しません。
参加が強制されている研修や勉強会
参加を強制されている研修や勉強会は、労働時間に該当します。
たとえば、参加しなければ人事評価に関わるような研修や、始業前に参加を強制された勉強会は労働時間となります。[注4]
そのため、所定労働時間外に強制参加の研修や勉強会を実施する場合は、残業代を支払わなければなりません。
ただし、任意参加の研修や勉強会は労働時間にはなりません。
手待ち時間
手待ち時間とは、従業員が実際に作業をしていなくても、上司の指示があればすぐに業務に従事できるよう待機している時間です。[注4]
たとえば、店員が客の来ていない時間や、貨物積み込み係が自動車の到着を待つ時間、タクシー運転手が乗客を待つ時間などが該当します。
この時間は、従業員が使用者(上司など)の指揮命令下にあり、完全に労働から解放されていないため、労働基準法上の労働時間として扱われます。
そのため、手待ち時間に対しても賃金を支払う必要があります。
仮眠時間
仮眠時間が労働時間に含まれるかどうかは、その時間が指揮命令下にあるかどうかによって判断されます。
仮眠中も業務対応が必要な場合や、労働からの解放が保障されていない状況では、労働時間とみなされる可能性が高くなります。[注4]
具体的には、仮眠中にトラブル対応の可能性がある場合や、仮眠室にいることが義務付けられている場合、待機状態が求められている場合などが該当します。
一方、実際にトラブル対応が求められず、労働者が完全に休息のために解放されている場合は、労働時間に含まれない可能性があります。
仮眠時間が労働時間とみなされる場合、残業代の計算にも影響するので、注意しましょう。
残業時間が多いときの対処方法
労働基準法で残業時間の上限が定められている以上、残業時間が多いときは何かしらの対策が必要です。
残業時間が多いときの主な対処方法として、以下の方法が挙げられます。
- 労働時間を正確に把握する
- 不要な業務を洗い出して業務を見直す
- 業務の自動化を検討する
- 残業削減の取り組みを会社全体で推進する
それぞれの対策方法を詳しく解説します。
労働時間を正確に把握する
正確な労働時間データは残業の発生要因分析や部門別・従業員別の残業時間、繁忙期の特定などが可能になります。
人事部門は、これらの情報を分析することで業務の分散や人員配置の最適化などといった対策が可能になります。
正確な労働時間把握は残業時間削減の対策として有効な手段といえるでしょう。
一方、従業員側も労働時間を正確に把握することで自身の労働時間を客観的に見ることができます。
正確に記録を残せば、なぜ残業時間が多いのかを自身で把握できるため、業務改善に向けて対策としても有効です。
不要な業務を洗い出して業務を見直す
残業時間削減のために最も有効な方法は不要な業務をやめることです。
まず、すべての業務を洗い出し、その目的と価値、代替可能性などの観点から評価します。
この評価に基づき、目的が不明確な業務や習慣化された無駄な業務、過剰品質の業務などを「やめるべき業務」として特定しましょう。
次に、これらの業務を廃止・縮小する際の影響を分析し、上司や同僚、関係者との合意を取ります。
合意が得られた業務については、段階的に縮小または廃止を実行し、その効果を測定します。
業務をやめたあとは、実際の残業時間削減効果や他の業務への影響、組織全体への影響を確認しましょう。
不要な業務を洗い出し、業務を見直すことは残業時間削減だけでなく、コア業務への集中時間の確保や生産性向上にもつながります。
業務の自動化を検討する
残業時間の削減対策として、RPAやAI、チャットボットなどのツールを活用し、業務を自動化することを検討しましょう。
自動化には各業務のプロセスを棚卸しし、どの業務の工程が自動化できるか検討が必要です。
自動化できる業務は積極的にDX化し、自動化しましょう。
実際に、ある企業ではAIの導入により800時間の業務時間を削減した事例もあります。
ただし、システム導入にあたっては業務特性や企業文化を考慮し、従業員のスキルアップも併せて検討することが必要です。
残業削減の取り組みを会社全体で推進する
企業全体の残業時間削減のためには、経営層が明確な目標を設定し、率先して取り組むことが求められます。
適切な労働時間管理の徹底やノー残業デーの設定などが、基本的な残業削減対策となるでしょう。
その他、業務効率化の推進や従業員の意識改革、成果重視の評価制度への転換なども考えられます。
また、フレックスタイム制やテレワークなど、柔軟な働き方の導入も効果的です。
これらの取り組みにより、従業員のワークライフバランスの向上や生産性の向上、企業イメージの改善につながります。
残業削減は単なる労働時間の短縮ではなく、企業全体の変革と持続可能な成長につながる取り組みとなることを意識しましょう。
ビジネスコミュニケーションに「Chatwork」
働き方改革の影響で、残業に関する法改正も進んでいます。
「今さら残業代の計算なんて......」と思う方も多いかもしれませんが、誤った知識は思わぬ労務トラブルを引き起こしてしまう危険性もあります。
多様な働き方が推進されるなかで、労務管理はより複雑なものになることが予想されるため、今一度、自分の知識が正しいかの確認やアップデートをおこないましょう。
ビジネスチャット「Chatwork」は、個人間だけでなく、複数人でも円滑なコミュニケーションが実現できるビジネスツールです。
全社に一斉に情報共有することもできるため、労務管理の正しい知識の発信や、就業規則のアップデートの展開にも活用することができます。
「Chatwork」は、チャットコミュニケーションだけでなく、全社共有や勤怠管理などの活用もできるツールです。
ビジネスコミュニケーションにまつわるさまざまな課題解決に、ぜひご活用ください。
Chatwork(チャットワーク)は多くの企業に導入いただいているビジネスチャットです。あらゆる業種・職種で働く方のコミュニケーション円滑化・業務の効率化をご支援しています。

[注1]出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和5年12月分結果確報」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r05/2312r/dl/pdf2312r.pdf
[注2]出典:転職サービスdoda「平均残業時間ランキング【91職種別】」
https://doda.jp/guide/zangyo/
[注3]出典:東京労働局「しっかりマスター労働基準法」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf
[注4]出典:厚生労働省「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」
https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf
[注5]出典:厚生労働省「私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2~3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか。」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_11.html
※本記事は、2024年10月時点の情報をもとに作成しています。




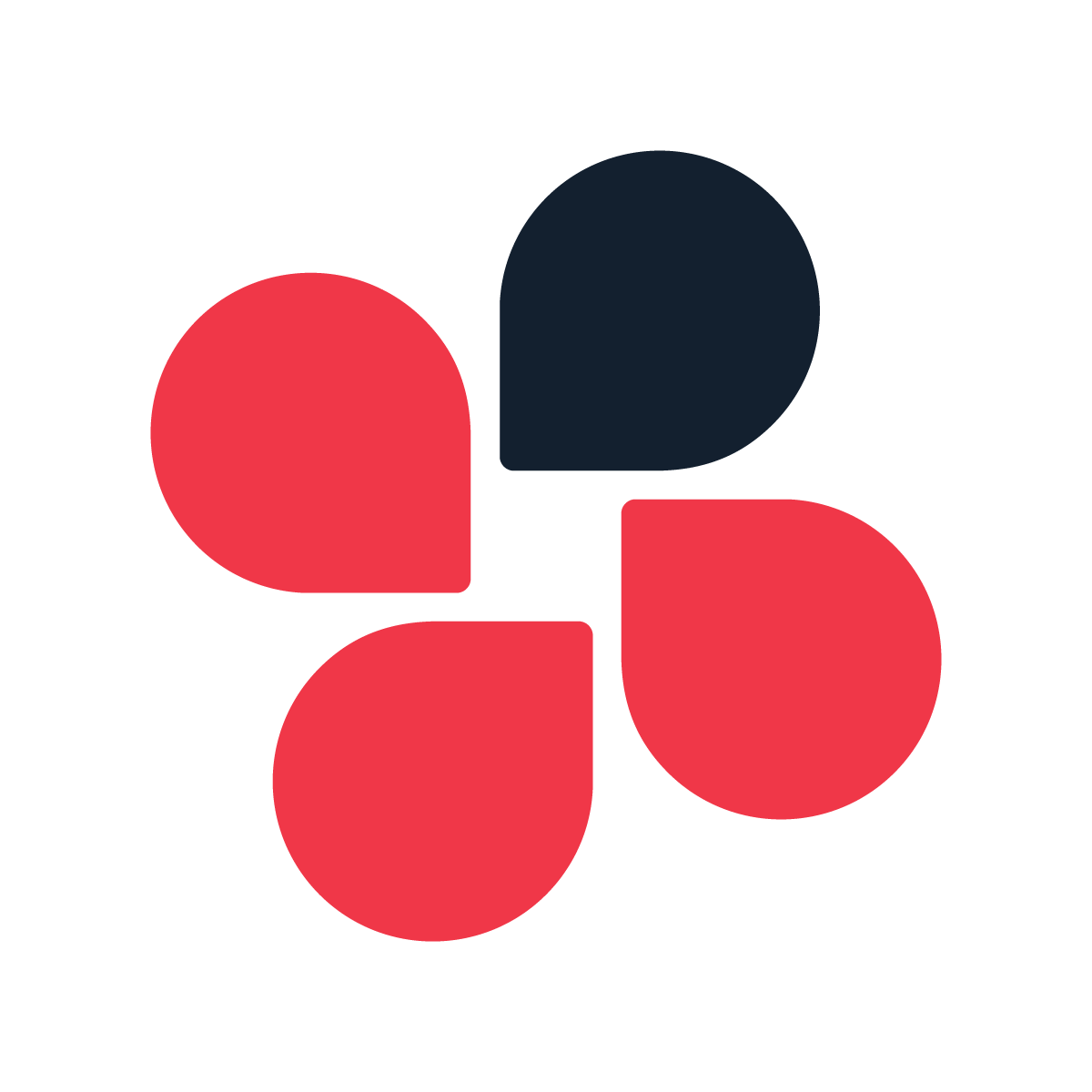



記事監修者:北 光太郎(きた こうたろう)
きた社労士事務所 代表。大学卒業後、エンジニアとして携帯アプリケーション開発に従事。その後、社会保険労務士として不動産業界や大手飲料メーカーなどで労務を担当。労務部門のリーダーとしてチームマネジメントやシステム導入、業務改善など様々な取り組みを行う。2021年に社会保険労務士として独立。労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。法人向けメディアの記事執筆・監修のほか、一般向けのブログメディアで労働法や社会保険の情報を提供している。